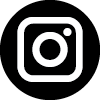ニューロダイバーシティの未来
個々のポテンシャルを最大限に活かす社会とは
―ニューロダイバーシティポテンシャルプロジェクト―
2025年4月18日

2024年10月12日、13日に港区竹芝で開催された「ちょっと先のおもしろい未来 2024」(ちょもろー2024)。そこでは、「みんなの脳世界2024〜超多様〜」の一環として、パネルディスカッション「ニューロダイバーシティポテンシャルプロジェクト」が実施されました。
ニューロダイバーシティの人々の可能性を最大限に引き出すには、どのようなテクノロジーが必要でどのようなソーシャルデザインが求められるのでしょうか。パネルディスカッションでは、テクノロジー、教育、社会の在り方をテーマに日本、アメリカ、イギリスの専門家たちが活発に意見を交わしました。
<パネリスト/登壇者>
- 伊藤 穰一氏:株式会社デジタルガレージ共同創業者 取締役/学校法人千葉工業大学 学長/Neurodiversity School in Tokyo 共同創立者
- ジェイミー・ガルピン氏:発達心理学者/スペシャルネットワークス Coファウンダー
- ルア・ウィリアムズ氏:パデュー大学UXデザインプログラム助教
- 伊藤 瑞子氏:カリフォルニア大学アーバイン校教授 / Connected Learning Lab ディレクター
- 石戸 奈々子 : B Lab所長
ニューロダイバーシティを「ポテンシャル」として捉えるプロジェクト
パネルディスカッションは、B Lab所長の石戸 奈々子(▲写真1▲)の挨拶で始まりました。
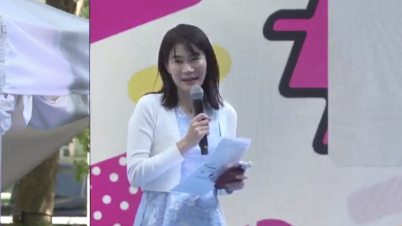
石戸:「私たち『ちょもろー』では2023年からニューロダイバーシティをテーマの一つに掲げ、脳や神経の多様性に着目したダイバーシティへの理解を深め、ニューロダイバーシティ社会を実現していくプロジェクトを推進しています。本日は、海外からニューロダイバーシティの第一線で活躍する研究者をお招きし、株式会社デジタルガレージ共同創業者・取締役、そして学校法人千葉工業大学学長、さらにはNeurodiversity School in Tokyo共同創立者である伊藤 穰一氏(▲写真2▲)をモデレーターにパネルディスカッションを実施します。このパネルディスカッションを通じて、『ニューロダイバーシティポテンシャルプロジェクト』についての理解を深めていただけると幸いです」。

伊藤氏:「本日のスペシャルなパネリストの3人をご紹介します。まずは、ジェイミー・ガルピン博士です。発達心理学者でスペシャルネットワークスのCoファウンダーです。続いて、パデュー大学UXデザインプログラムとコンピューターグラフィックステクノロジーの助教であるルア・ウィリアムズ氏、そして、私の妹でカリフォルニア大学アーバイン校の伊藤 瑞子教授です。文化人類学と学習科学の視点から若者のデジタル文化を研究しています。
さて、本日は、『ニューロダイバーシティポテンシャルプロジェクト』についてパネルディスカッションを通じて紹介します。自閉症、ADHD、ディスレクシアなどの神経多様性を持つ人たちの特性は、これまで、ディスアビリティー(障がい)と捉えられ、克服すべき課題として扱われてきました。しかし、ニューロダイバーシティの研究が進むにつれ、最近ではこうした特性をむしろ長所、ポテンシャルとして見直し、弱みとして補うという方向ではなく、アンプリファイ(特性として強化)する考え方が注目されています。
ただし、こうした考えのもとにニューロダイバーシティの人たちの可能性を最大限に引き出すには、強み(ポテンシャル)を活かせる環境づくりが欠かせません。そこで、千葉工業大学、Neurodiversity School in Tokyo、石戸さんのB Lab、伊藤 瑞子教授のカリフォルニア大学アーバイン校など日本とアメリカの専門家たちが協力し合い、環境づくりや課題解決のための革新的なアプローチを模索しています。それが『ニューロダイバーシティポテンシャルプロジェクト』です。
ニューロダイバーシティムーブメントの重要なポイントの一つは、社会も個人の多様性に合わせていかなくてはならないという意味で、社会の変革が必要だということ。
もう一つ。今の標準化された日本の教育は、個人の強みや好きなことを伸ばすのではなく、できないことや自分が嫌いなことを補い、できる限り標準化された試験に合格することをゴールとしています。ところが、最近ではテクノロジーにより弱いところはある程度、補えるようになりました。AIの時代になると、もっと多様な人たちが存在していたほうが世の中は活性化されるでしょう。神経多様性を持つ人たちが潜在能力を最大限に発揮できるように、革新的なテクノロジーを開発することも、この『ニューロダイバーシティポテンシャルプロジェクト』では目指しています」。
ニューロダイバーシティに関係なく
出来事に対する感じ方は人それぞれで異なる
伊藤氏:「ニューロダイバーシティを考えるときのキーワードのひとつは『バランス』です。多くの人に共通しているニーズとニューロダイバーシティの人たちの多様なニーズとのバランスをどのように取るか、マジョリティーの人たちが必要とするサポートと少数の人たちにとって必要なサポートとのバランスをどう取ることでフェアにするか、健常者の権限とやりたいことをサポートしながら、障がい者も含めた多様な脳の人たちをどうサポートしてバランスを取るかといったことです。まずは、この論点から始めたいと思います」。
ジェイミー・ガルピン氏:「まず、我々が理解しなければいけないのは、自分のことを健常者と思っているか、ニューロダイバーシティの人なのかに関係なく、ある出来事などに対する感じ方、体験の受け止め方は人それぞれで異なるということです。(▲写真3▲)

この会場にいらっしゃるみなさんも、一人ひとりが同じ空間を全く違う形で体験しています。体験は、それまでの自分の経験に基づいて処理されます。同じ体験がインプットされても、その体験をどう解析して処理するのかが一人ひとり違うのです。そこで、まずは一人ひとりの経験が多様で、さまざまな違いがあり、それに基づいて処理される体験もまた人それぞれで異なるということ、つまり障がい者を含めて多様な人たちが、自分が本当は何をどう感じ、何を求めているのかを全員が理解することが大切だと感じています。
我々は感覚を使ってインプットを処理します。その際、インプットによって自分がこうなるのではないかという予測や期待と、さまざまな刺激によってインプットが解析され、認知されます。例えば、あるイラストを見せて何に見えるかを尋ねたら、多様な答えが返ってくるはずです。ところが、最初に「水中を観察する丸い窓のまえを人魚が泳いで行った」というイメージを話してから、イラストを見せるとそのように見えたりするものです。
つまり、言葉が追加されるだけで、あるモノが違って見えてきたりするということです。このことから我々の体験とは、ある出来事についてそれまでの経験などをもとに何かしらの理屈をつけて解釈した、処理した結果なのです。我々の経験と処理の仕方の違いによって、人それぞれ同じ空間の中でも違う体験をしています。
ここで大切なことは、どういった体験が良いか悪いかといったことではなく、『どの体験も違う』ということです。ここが重要なポイントです。我々は、不確実な中でいろいろと推測をしています。一人ひとりの経験には多様性がありますが、『今、起きているのは何か』を理解しようとするモチベーションはみなに共通することです。不確実な世界の中で暮らすために、ある出来事がインプットされたときには、それまでの経験をもとに予測・解析・処理していく、それが体験であり、その行為はみなが共通しているのです。
それでは、なぜ、みなが不確実な世の中に対して不安を感じ、インプットを予測・解析・処理しようとするのでしょうか。それは、脳が我々が生きるためのエネルギーのバランスを取ろうと働くからです。不確実なことが起きると、外の環境と身体の中の環境との間でエネルギーのバランスが崩れます。人それぞれに多様性があり、多様な経験があり、多様な身体があり、そして、人それぞれの合理的なエネルギーのバランスがあるのではないでしょうか」。
『これがノーマル』という『普通の人間』は一人もいない
ルア・ウィリアムズ氏:「私には、オーティズムとADHDとその他のさまざまなニューロダイバーシティがあり、日常生活を送る中で、ときにさまざまな苦労を感じることがあります。ある人について健常者かそうでないかを判断するとき、平均的な人間である健常者から『どのぐらい離れているか』を確認することがありますが、じつは『これがノーマル』と考えられるところ、つまり『普通の人間』のところには誰もいないのです。これは、みなさんが全て障がい者という意味ではなく、また、誰も障がい者ではないという意味でもありません。真ん中の平均的な人間はいないので、障がい者のために役に立つことは、どの人にも役に立つのではないかということがポイントだと考えています。(▲写真4▲)

これまで、障がい者向けのテクノロジーの研究・開発は、障がい者を社会的、行動的な側面から考え、普通ではないところを直すためにテクノロジーを活用する方向で進められてきました。障がい者を考えるにあたっては、社会的と行動的な側面だけでなく、社会が障がい者を『認知』するという視点も重要です。ここにもテクノロジーが使えるのではないでしょうか。認知をサポートするツールとしての活用です。
ただし、社会的、行動的、認知的という3つの軸だけで考えてしまうと、まだそれでは足りません。すごく複雑で多様なランドスケープの中で、人それぞれの文脈によっていろいろなテクノロジーでサポートできます。そういう視点でテクノロジーについて考えたほうが良いでしょう。
例えば、ビーチにいる人、山にいる人、森にいる人、それぞれの人にとって必要なサポートはすべて違います。テクノロジーをサポートのためのツールと考えると、ある人をサポートするには、その人がどのような環境でどのような文脈にいるかということを聞いて、理解しなくてはなりません。そのうえで、どうサポートするかが重要になってくると思います。
さきほどのジェイミー・ガルピン氏の説明では、人は同じ場所にいても、それぞれの感じ方や受けとめている現実には違いがあります。ですから、その人を『見るだけ』では、その人の文脈と環境を理解することはできません。その人に、きちんと聞かないとなりません。自分は森にいると思っていても、友人から見ると山にいると見えるかもしれないのです。その違いによって、活用するテクノロジー、サポートも種類も異なってくるのです」。
普通の人を対象に実践されてきた教育はこれからどう変わっていくのか
伊藤氏:「ありがとうございました。次に教育や学びについて話し合いたいと思います。これまでの教育は、いわば標準化された普通の人間にして、そこから育てるというものでした。そこにテクノロジーが活用されていたと言えるでしょう。それに対して、ニューロダイバーシティの視点からは、もう少し違う考え方があるのではないでしょうか」
伊藤 瑞子氏:「私はこれまで、学習とテクノロジーの研究が中心で、ニューロダイバーシティが専門ではありませんでした。ただ最近、ジェイミー・ガルピン氏やルア・ウィリアムズ氏、他のニューロダイバーシティの研究者からいろいろと学び、非常に興味深く、研究に取り組んでいます。(▲写真5▲)

私の研究は『コネクテッドラーニング』、つまり『つながりの学習』という考え方のもとで進められます。つながりの学習はシンプルな概念で、子どもたちとの個々の興味やアイデンティティを起点に、その子どもの良さを自然に伸ばし、社会に重要な学びを身に付けていこうというものです。
つながりの学習は、誰でも自分が興味のあるものを学びたいという気持ちを基本としています。興味の対象はアニメでも鉄道でも音楽でも良く、多様性があっていいのですが、自分の興味、アイデンティティ、そこから生まれる学びへのモチベーションは誰もが持つと思います。興味自体がアニメだろうが鉄道だろうが音楽だろうが、みんな多様性はありますが、基本的な学びの楽しさ、その興味を共有している人と一緒に学ぶ楽しさは誰でも持つ気持ちです。
私はこれまで、子どもたち一人ひとりが文化や社会経済的地位などのさまざまな違いによってアイデンティティや経験が異なる中、普通の学校で実践されている一定化された学びではなく、つながりの学習の考え方のもとに個人の興味やアイデンティティ、文化的背景を自然に学びにつなげていく研究をしてきました。
そのうえで、ここにきてニューロダイバーシティにも強い興味を持つようになりました。最近の教育学では、子どもたちに自分ができないことを無理やり学ばせるのではなく、その子どもが興味を持ち、強みを伸ばせることを自然に学ばせようという動きがでてきています。まだ新しい考え方ではありますが、ニューロダイバーシティの側面も含めて、その方向で研究を進めていきたいと考えています。
例えば、数学の勉強の場合、今までの考え方だとみなが同じ勉強をしなければなりませんでした。つながりの学習の考え方は、そこが違います。機関車トーマスに興味がある子どもがいれば、そのストーリーの中で自然に数学を学べるような工夫を埋め込み、子どもたち一人ひとりが自分の興味やアイデンティティを起点に自然に学んでいけるようにしていきたいと考えています。最近のテクノロジーやAIを活用すれば、そういったことが簡単にできるようになりました。こうした考え方のもとに、みなさんのクリエイティビティの可能性を広げていただきたいと思います」。
ルア・ウィリアムズ氏:「さまざまな人が持つ障がいを修正するという視点に立つと、一人ひとりが受け止めている現実や体験しているものも違うので、ある人が受け止めている現実や体験していることは間違っている、だから修正が必要だというように聞こえてきます。つまり、人それぞれの違いをなるべくなくして、標準化した人間を作り上げようとしているように思えます。そうなると、その人は自分を否定し、自分のことが嫌いになり、自尊心を失いかねません。そういった子どもたちが多く育つという結果になってしまうでしょう。
一人ひとりが多様であるのに、特に脳に多様性がある子どもを限りなく健常者のように直そうとすると、行動は健常者に似てくるのですが、周囲からはその子どもが本当の自分の気持ちのもとに行動しているようには見えません。そうやって多くの子どもが自分を殺して、自分を隠して健常者のように行動していると、自分だけがみなと違っていると思い込み、孤独感から自殺未遂にいたってしまうケースも多くあります。ある調査では自閉症の人の自殺未遂率は49%で、自殺を考えたことがある割合は7割を超えています。自尊心が下がってしまうのです。
やはり、一人ひとりの現実を認めること、自分がどういう環境にいるのか、自分が自覚した現実に必要なサポートを自らが選んで、そのためのテクノロジーを提供してもらえるようになれば、自立している人間が育つのではないでしょうか。子どもたちをそのように育て、子どもたち自身が感じている現実の中で自信を持って生活できるようになれば、大人になったときに『多様な大人』が『多様な現実の中』で『多様な行動』をしていることが見えるようになるでしょう。すると、多様な大人たち、その多様な行動を見ている子どもたちも、もっともっと自信を持ってその多様性の中で生きられるようになります。これがポジティブなループになっていくのではないかと期待しています」。
ジェイミー・ガルピン氏:「さきほどルア氏が、さまざまなサポートのテクノロジーについてお話をされました。一部の人に重要で必要なサポートテクノロジーは、きちんと適用すれば誰にとってもサポートになる技術であると思います。例えば、階段や段差のあるところに設けるランプ(傾斜路・スロープ)は、車椅子の人にとっては不可欠なだけではなく、車椅子の人以外にもいろいろと役に立ちます。松葉杖の人にとっても、カートを押している人にとっても有効です。ユニバーサルデザインの考え方では、階段や段差を探して必ずランプを設置します。階段を使える人にも使えない人にも、誰にとっても助けになります。
例えば、メンタルヘルスにおいては診断された病気に対して、薬を処方することがあります。しかし、同じうつ病でも症状や原因などが一人ひとり違います。そこで、一人ひとりが異なるのに、うつ病というカテゴリーに入れてしまう『診断』という考え方そのものが良くないのではないかという意見もあります。『診断』を超えたサポートが必要なのではないか、そういったサポートができないかというのがトランスダイアグノスティック(診断横断的)の考え方です。
例えば、二人の人が同じようにうつ病と診断されても、同じ薬やセラピーに対して全く違う反応をすることは良くあることです。研究者たちは、そうしたさまざまな診断と反応をする人たちを観察し、違う診断結果だが共通するところはないかといった視点で解析します。例えば、うつ病など診断結果は人それぞれで異なっていても、根本原因には不安があるなど、共通していることがないかを探すのです。その共通している部分をサポートすることで、診断を超えて複数の患者が同時に快方に向かうことがあります。
このように共通したところをサポートするのは効率的でもあります。共通することでは、不確実なことはみな不安になります。不確実性を減らすと、みながハッピーになります。例えば、学校の中で不確実性をなくすと子どものサポートになりますが、何が起きるかわかるようになる、つまり不確実性が取り除かれることが助けにならない人は、ほとんどいません。みなのためになるのです。
同じように自分の心拍や呼吸、消化など身体の内部の感覚である内受容感覚と自分の感情的な感覚との関係性を考えると、自分の心拍や呼吸のレギュレーションを理解できるとポジティブになります。心拍や呼吸が速くなっているというのを自分できちんと認知できれば、それによって自分の気持ちが不安になるのを抑制することができるでしょう。内受容感覚を理解するためのサポートも、どのような子どもにも役に立つと思います。
自分がハッピーな時の身体の反応は、一人ひとり違います。しかし、その反応に対して好奇心を持って理解し、きちんとマネジメントすることによって、多くの人の安定につながると思います。このように身体の中の内受容感覚をトランスダイアグノスティックの視点でどうサポートするか、それが研究の大きなテーマです」。
ニューロダイバーシティのポテンシャルを伸ばす
テクノロジーとはどうあるべきか
伊藤氏:「ありがとうございます。次にテクノロジーについて議論したいと思います。テクノロジーをどう活用するとニューロダイバーシティの人たちのサポートになるのか、反対にどういったことをするとマイナスになるのか、意見を聞かせてください」。
ルア・ウィリアムズ氏:「私は、障がい者向けテクノロジーについて、これまでにさまざまな研究をしてきました。テクノロジーが良いのかそうでないのかについては、さまざまな考え方や議論があると思います。それらを踏まえて強調したいのは、障がいを持っている子どもたちにとって、自分が活用するテクノロジーを選ぶ権限がないケースが多くあるということです。子どもたちがタブレット端末に夢中になるのは、それを使いたいと自分で選んでいるからです。テクノロジーを選び使う権利を、その当事者に持たせられることが重要なポイントです」。
伊藤 瑞子氏:「私がずっと研究していたコネクテッドラーニングにおいては、健常者の子どもたちにとって良い技術は、自閉症やニューロダイバーシティの子どもたちにも適用できることがわかりました。
先ほどのルア・ウィリアムズ氏のお話にもありましたが、健常者の子どもたちにとって自分で選択する権利や自立する権利、カスタマイズする権利は、学びにつながっていきます。一方で脳の多様性のある子どもたちや自閉症の子どもたちにとっても重要です。健常者の子どもたちは、カスタマイズが必要で実施をしても我々の予測可能範囲の中におけるカスタマイズであることが多いです。それに対して、多様なニューロダイバーシティの子どもたちは、理解できない現実の中にいるケースもあります。どのようなテクノロジーをどう使うかの選択権を持たせることは特に重要であると思います。
日本のポケモンや他のアニメのキャラクターは世界的に人気です。ストーリーが深く、多様で選択とカスタマイズができ、子どもたちと関係性を構築するのに非常に良いツールだという研究をしていました。このようなプログラムを作ると、統計学的に脳が多様な自閉症の子どもたちが多く集まってきます。そのような子どもたちに特に好まれているように見えます」。
ルア・ウィリアムズ氏:「自分たちの生活を振り返っても、友達とスケジュールを組んだりコミュニケーションしたりするツールは積極的に使っていると思いますが、会社で自分の予定を報告したりスケジュールを管理したりするツールは、似ている技術であってもあまり積極的に使いたいとは思わないでしょう。それは、自分で選択している技術と押しつけられている技術との違いだと思います。誰が選んでいるかということはとても重要なのではないでしょうか」。
ジェイミー・ガルピン氏:「その環境を考える中で、子どもたちが必要としているのは、発言権、選択権、そして自立。この3つが必要で、テクノロジーによってはそれをきちんとサポートできるのではないでしょうか。」
伊藤氏:「ありがとうございました。健常者が健常者の視点だけでテクノロジーを開発しても、それがニューロダイバーシティの人たちにとっては実際に必要とされていないテクノロジーである可能性もあります。同じテクノロジーでも、その人が自ら使いたい、必要だといって提供されるテクノロジーと、学校や企業などが押しつけるものとでは有効性が違ってくることもあります。
やはり、大切なのは一人ひとりがそれぞれ異なるという前提に立って、『自分が本当は何を必要としているか』をしっかりと考えることです。以前に私があるカンファレンスに参加したとき、ある人が聴覚障がい者でも振動で音声を聞き取れるようになるジャケットについて講演していました。そこで、私を含めて多くの参加者が一緒にいた聴覚障がい者のアーティストに『見た?すごくいいでしょう』と尋ねていたのです。ところがそのアーティストは、『私はもう健常者の声を聞きたくないの。私はしゃべりたいの。どうして、聞きたくないものを聞こえるようにするテクノロジーばかり開発しようとするの』と怒っていました。
つまり、誰一人としてそのアーティスト、聴覚に『あなたはどういうテクノロジーが欲しいの』『あなたにとって必要なテクノロジーはどのようなもの』とは聞かずに、無理やりに健常者視点の想像で『こんなテクノロジーなら、あなたはハッピーになるよね』という押しつけをしていたのです。
押し付け系のテクノロジーがじつは多い中で、本日のようなディスカッションはとても意味があり、重要だと思います。テクノロジーを研究・開発する資金や技術力を持っている人たちと、障がいや違いを持っている人たちが話し合うこと、そして本当に必要なものをきちんと聞くこと、そこから始めることが重要です。
同じテクノロジーでも自ら使いたいと思うものと、『これを使え』と押し付けられるものとでは、その意味合いがまったく違ってきます。ソーシャルデザインも非常に重要なのです。すでに多くの大学で研究も始まっています。研究者同士のコミュニケーションもできるしメソッドもありますので、私たちの千葉工業大学でも新しい大学院を作ってテーマにしようと考えています。こうしたディスカッションが、アカデミック、産業界、教育界を含めてコラボレーションをするきっかけの一つになれば幸いです」。