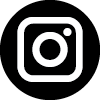「脳が長持ちする会話」で
認知症にならない社会の実現を目指す
2025年9月25日
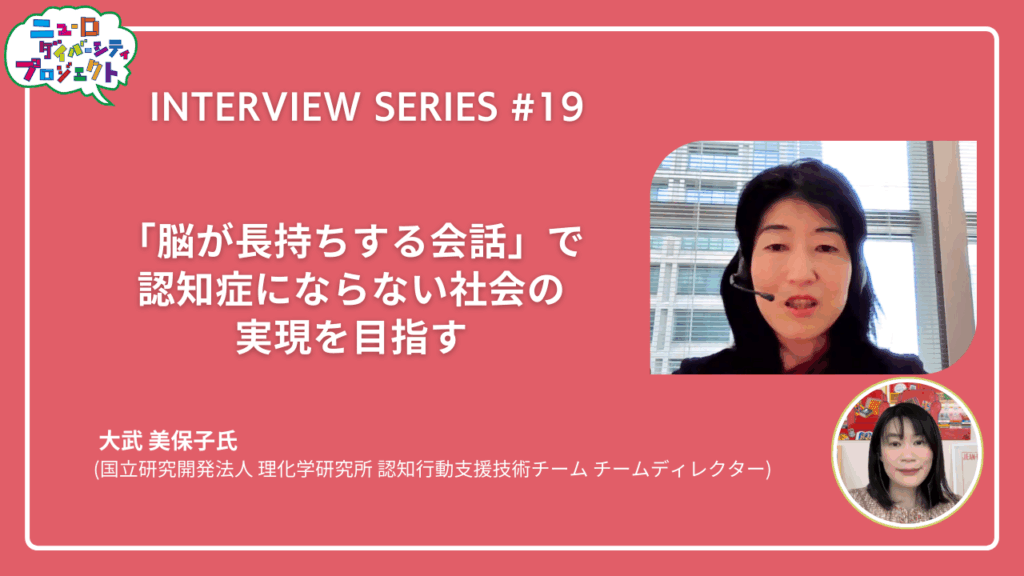
人間の脳や神経はとても多様で誰もが独自の特徴を持っています。B Labでは、そんな個人の特性を「強み」に変え、誰もが力を発揮できる社会の実現を目指すニューロダイバーシティプロジェクトを推進し、展示会「みんなの脳世界」を通じて企業や大学、研究機関の最新の研究成果や取り組みを紹介しています。今回は生理的・認知的・社会的の3方向のアプローチで認知症にならない社会の実現に取り組んでいる国立研究開発法人 理化学研究所 認知行動支援技術チームの大武 美保子氏(▲写真1▲)に、展示内容と最新の研究成果などについて、「みんなの脳世界」展を推進する B Lab所長の石戸 奈々子(▲写真18▲)がお聞きしました。
<MEMBER>
国立研究開発法人 理化学研究所
認知行動支援技術チーム
チームディレクター(インタビュー当時 チームリーダー)
大武 美保子氏

>> インタビュー動画も公開中!
認知症予防に必要な認知機能に介入する技術と
認知機能を検出する技術を研究
石戸:大武さんは、『脳が長持ちする会話』で認知症にならない社会の実現に取り組まれています。最近の理研での研究内容、今後の研究の方向性などについてお話をお聞かせください。
大武 氏:私は、国立研究開発法人 理化学研究所の革新知能統合研究センターの『認知行動支援技術チーム』でチームディレクターを務めています。同時に『NPO法人 ほのぼの研究所』の代表理事・所長、東京農工大学の客員教授でもあります。専門はロボット工学、人工知能学、人間情報学ですが、おもに認知症の課題に情報学の観点から取り組む研究をしています。2024年末には『脳が長持ちする会話』という書籍を出版しています。まさにニューロダイバーシティに関わる内容です。
◆書籍『脳が長持ちする会話』 https://www.amazon.co.jp/dp/4863102895/
認知行動支援技術チームでは、おもに認知症予防に取り組んでいます。そのために必要な技術は大きく2つあり、1つは認知機能に介入する技術、もう1つが認知機能を検出する技術です。今日は主に、介入する技術についてお話しをしますが、『みんなの脳世界』で展示したのは、検出する技術でした。まずは、認知機能を検出する技術をご紹介します。(▲写真2▲)
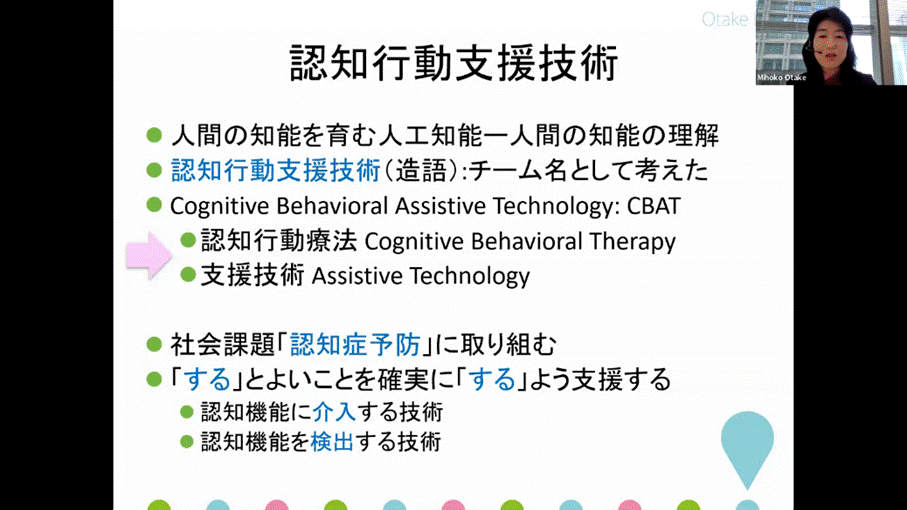
写真2●認知行動支援技術チームの研究テーマ
認知機能を検出するには、さまざまな手段があります。認知課題を設計して、その課題に取り組んでいるときにどのような脳波が出ているかを計測し、機械学習で認知機能が下がっているかどうかを判別するという研究に取り組んでいます。その一環として『みんなの脳世界』の展示では、『リラックスする』という課題に取り組んでもらうゲームを展示しました。多くの子供たちに参加していただきましたが、簡単に言うと「どちらがよりリラックスできるか」を競い合うものです。意識してリラックスする、意識して自分の状態をコントロールする力が下がっているかどうかを判別するデモでした。(▲写真3▲)
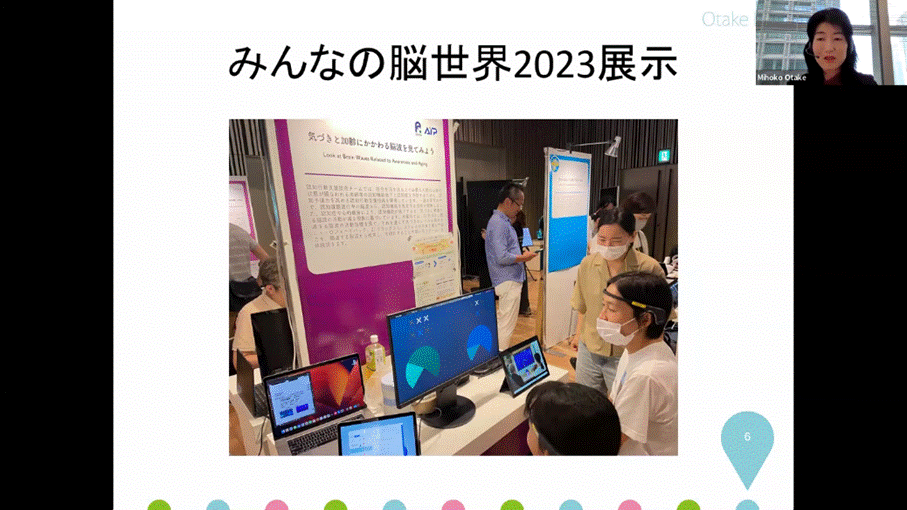
例えば、さまざまなことが覚えられなくなるという状況を考えてみます。覚える時はそれなりに意識をしないとなりませんが、意識をうまくコントロールできないと『覚えられるものも覚えられない』ことが起こります。どこに物を置いたのかを忘れるのは、ふとモノを置いた時には意識があまりなく、置いた記録が脳に残らないからです。実際に意識があったところを繋いで探し回ってみると、意識があったところの間、つまり無意識だった場所のどこかに置いてあるということがよくあります。認知機能が落ちてきた状態とは、このように意識をあまりコントロールできていない状態です。『みんなの脳世界』では、そんなことを理解できる展示をしました。
認知症の定義と
予防するための2つのアプローチ
次に、認知症とはそもそも何かをお話しします。認知症の定義は、脳や身体の疾患を原因として記憶・判断力などの障害が起こり、社会生活に支障がある状態とされています。『状態』ということは、最終的には困っているかどうかで認知症かどうかが決まるということです。ここは重要な点です。(▲写真4▲)
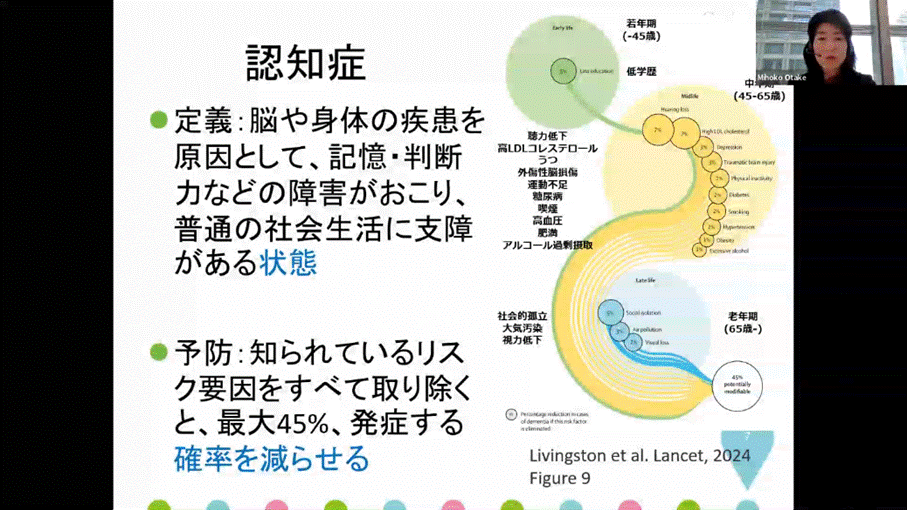
予防としては、若年期、中年期、老年期のそれぞれで知られているリスク要因をすべて取り除くと最大45%程度、発症する確率を減らせるとされています。2017年に医学雑誌『ランセット』にレポートが出稿され、現在も3~4年に1回ずつ更新されています。確定的なものではなく、現在の研究で分かっている範囲での数値であり、今後、新しい研究成果や知見が得られると、比率が変わる可能性があります。
認知症予防には2つのアプローチがあることが知られています。1つは生理的アプローチで、脳と身体の老化を遅らせるものです。もう1つが認知的アプローチで、たとえ脳や身体が老化しても認知機能に影響しないようにするアプローチです。私たちは2つ目の認知的アプローチについて興味を持ち、おもなテーマとして研究しています。具体的には、認知予備力と呼ばれるものの研究です。 認知予備力とは、脳の病理や加齢の影響を受けても、認知機能の低下や認知症の発症を抑える能力です。知性や経験が認知機能を保つ上で効果的な脳内の結合を生み出し、アルツハイマー病の病理変化による認知機能への影響を小さくするという考え方です。(▲写真5▲)
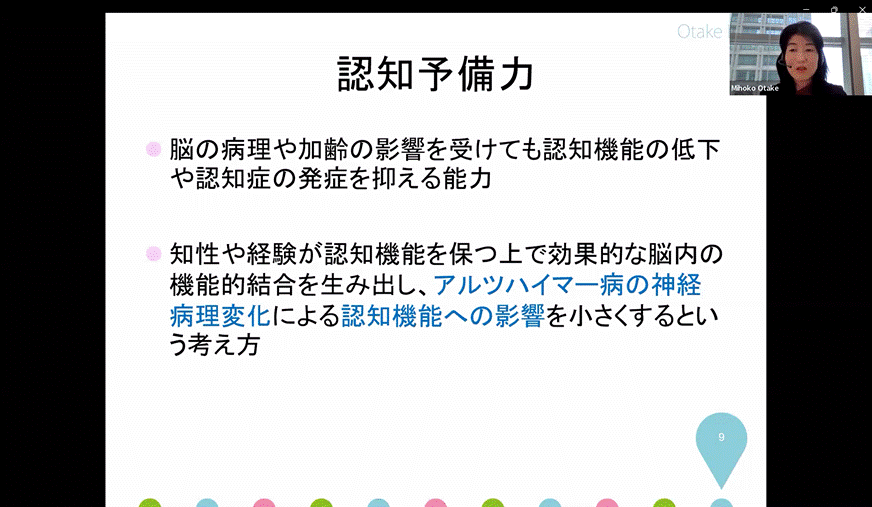
アルツハイマー病による病理変化とは、身体の中で細胞の状態が悪くなり、その結果、細胞が死に脳が萎縮してしまうことです。その場合でも、脳とその中の神経と神経の繋がりがたくさんある人は、たとえ細胞の数が減っても認知機能への影響が小さくなるということが知られています。このことが明らかになったのは、『修道女研究』と呼ばれる調査によってです。(▲写真6▲)
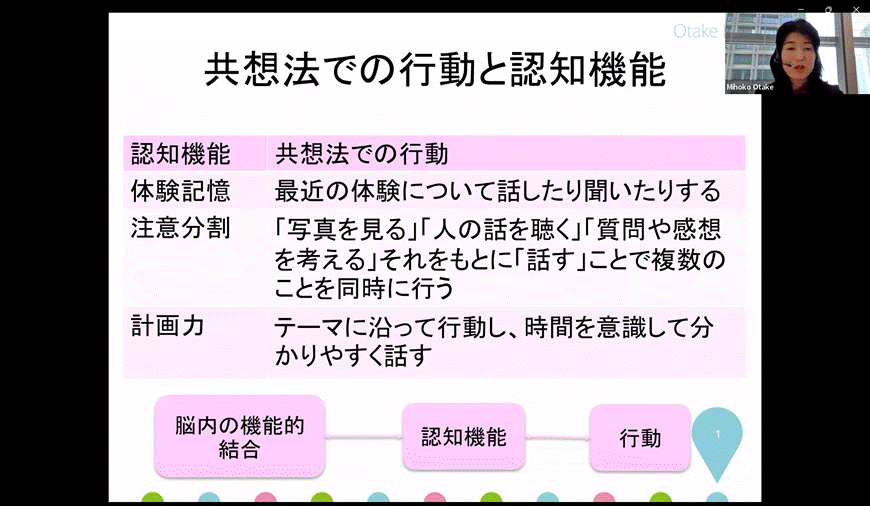
アメリカの修道女を対象に認知テストを行い、死後解剖して脳の状態を調べたところ、脳が萎縮してアルツハイマー型認知症の状態であるはずなのに全く認知症の症状が出なかった人が8%もいたということが知られています。つまり、『病理変化が起こっている状態』と『症状が出る』ことの関係が1対1ではないということ。そこで、『なぜ病理変化があっても発症しないのか』が重要となり、そこが予防の2段階目になります。
認知症の原因疾患は70種類ぐらいあると言われていますが、その中の7割はアルツハイマー型の疾患、2割が脳血管性の疾患、残りの1割が、その他さまざまな疾患です。そこでアルツハイマー型認知症を抑えようと考えた場合、まずは神経病理変化の進行を遅らせる生理的アプローチがあります。そして、もう一つ、同じ神経病理変化でも認知機能への影響を減らす、少なくなくする認知的アプロ―チがあります。(▲写真7▲)
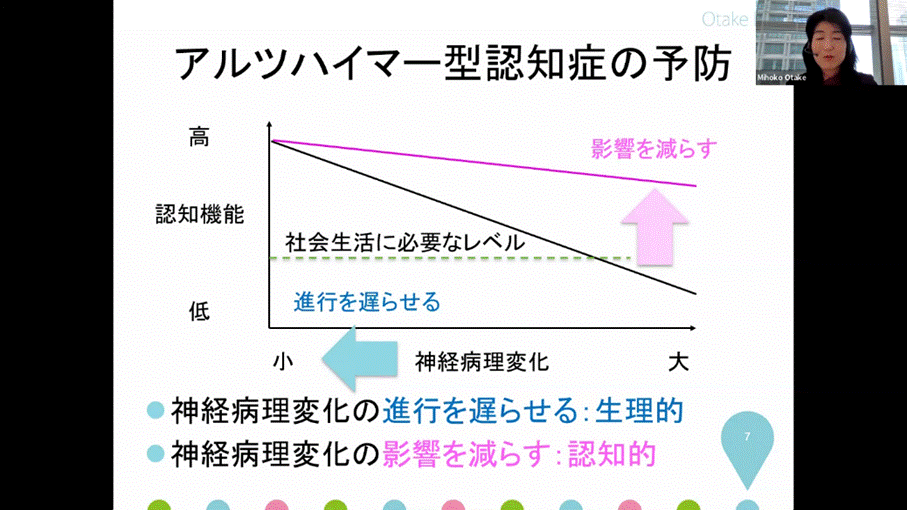
「体験記憶」「注意分割機能」「計画力」
3つを活用する「共想法」で認知機能を保つ
神経病理変化に抗う行動とは何かを考えてみます。認知機能を必要とする行動をすると認知機能が発揮され、認知機能を発揮するために必要な脳内の機能的結合において信号のやり取りがあり、ネットワークの中で電気信号が飛び交うことになって、結合が強まる可能性があると考えられています。これによって神経病理変化に抗うことになります。つまり、認知機能に対応する行動を習慣化しておくことが有効と考えられています。(▲写真8▲)
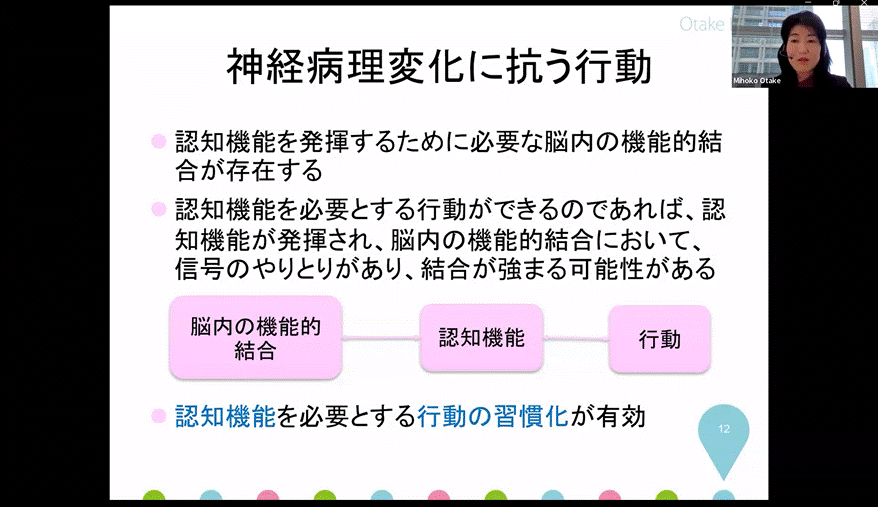
あることができるということは、あることができるために必要な機能が今、あるということを意味しており、ある機能が発揮できることは、そのために必要な脳の結合も存在するはずだとなりますので、行動を見ていると脳の中がある意味では『見えている』とも言えます。
例えば、言語機能が必要な社会的交流としては会話がありますが、言語能力が認知機能の維持に重要な役割を果たすことが知られています。修道女研究でも明らかになっています。病理変化があるのに認知症を発症していなかった人がどんな人だったのか調べたところ、言語能力が高かったことが分かっています。そして、言語機能は結晶性知能と呼ばれて、生涯にわたって向上するとされています。そして、社会的交流が多い人が少ない人に比べて、認知症発症リスクが小さいことも知られており、社会的孤立はリスク要因でもあるとされています。(▲写真9▲)
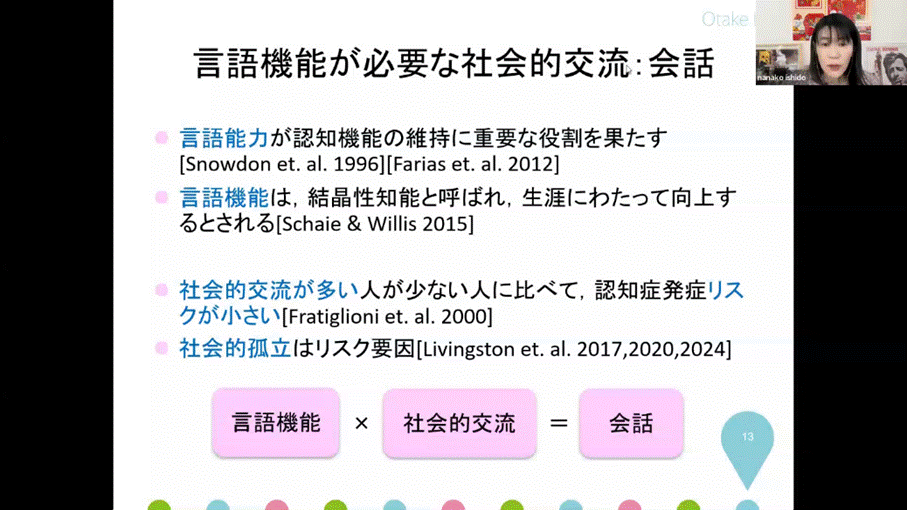
そこで、私たちは言語機能を使うもの、そして社会的交流の基礎である会話をうまく介入手段として使うことで、認知機能が維持できるとのではないかと考えました。さらに、どんな会話でもいいのかというと、おそらくそうではないと考え、認知機能を保つ性質を持った会話、すなわち認知機能を活用するような会話をうまく使えば認知機能が維持できると考えました。
どのような認知機能が低下しやすいのかというと、まずは体験の記憶です。次に複数のことに注意向ける注意分割機能、最後が計画力の3つです。ドイツの発生学者であるヴィルヘルム・ルーが提唱した『ルーの法則』によれば、人間の器官や機能は適度に使えば発達し、使わなければ退化・萎縮するとされています。そこで、この3つの低下しやすい認知機能を活用するようなルールを会話に加えることで、認知機能をフル活用できるようになると考えました。そのような会話ができるように支援する方法を考案し、それに『共想法』という名前をつけました。(▲写真10▲)
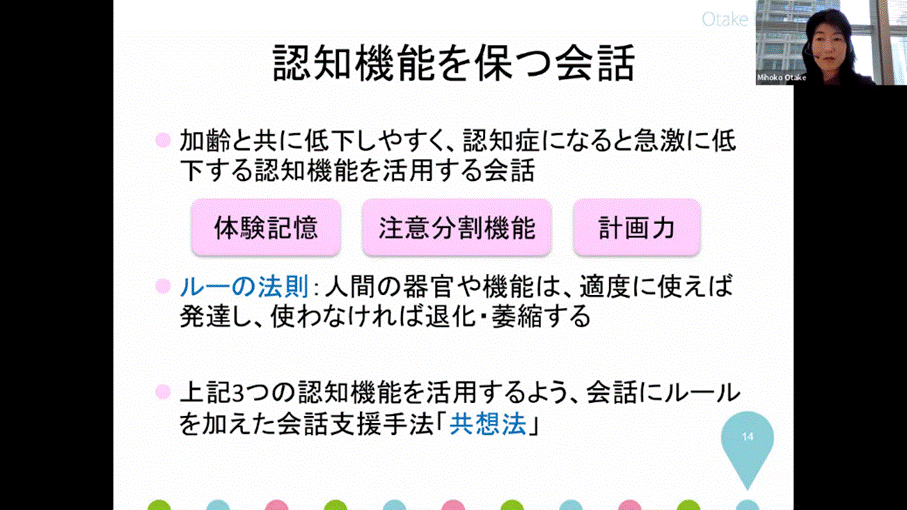
ニューロダイバーシティの観点からすると、この3つの機能はみながまんべんなく使っているわけではなく、得意なところや好きなところはよく使うし、苦手なところは周りの人にカバーしてもらっています。例えば、計画を立てるのが得意な人は、他の人の分まで計画を立てますし、逆に計画を立てるのが苦手だという人は、なるべく立てないで済むようなライフスタイルになっていたり、計画を立てるのが得意な友人に立ててもらったりしています。ただし、どちらが計画力という認知機能を使ったかというと、計画を立てた人です。長年の経験と機能の活用の積み重ねが最後、絶対値になって効いてきます。誰でも得手不得手や好き嫌いがあり、その結果としてそれらが時間積分していきますので、誰もがまんべんなく認知機能を保てるとは限らないということになるのです。
この3つの機能をまんべんなく使うのが会話支援手法である『共想法』です。参加者は、出題されるテーマに沿って写真を撮ってきて持ち寄ります。そして、話し手の写真が映し出されると、時間内に話し、そのあと周りの人から質問してもらい、自分の体験をより深く考えます。そして、周りの人はその人の撮影した写真を見て、話を聞いて、物の見方、視点を広げていきます。他の人の視点を使うことで、自分の考えないようなことを考えるきっかけになると、普段、眠っている自分の回路が起きてくるというイメージです。(▲写真11▲)
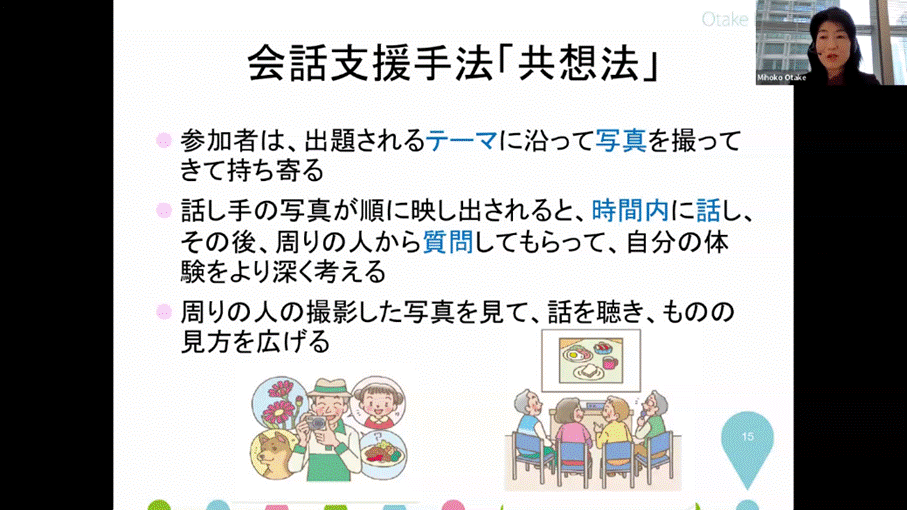
ロボット「ぼのちゃん」による
グループ会話支援システムでわかってきたことは?
この『共想法』では、最近の体験について話したり聞いたりすることで、体験の記憶、写真を見る、話を聞く、質問をする、考える、そして話すという複数のことを同時に行います。ここで注意分割機能を使うようになります。そして、テーマに沿って行動し、時間を意識して分かりやすく話すところで計画力を使います。このように3つの行動を行うことで3種類の認知機能が活用され、ひいては認知機能を発揮するのに必要な脳内の機能的結合も強化されうることになります。(▲写真12▲)
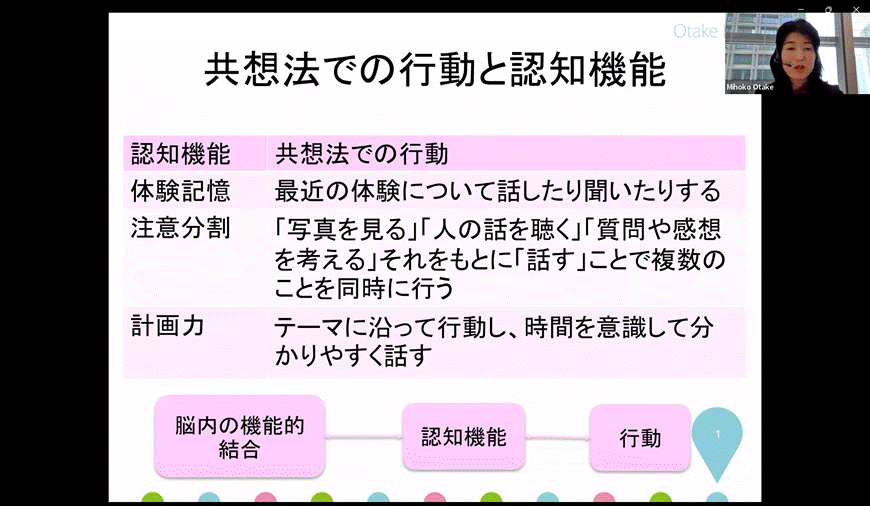
さらに、認知機能に介入する技術として、『共想法』に立脚した認知的介入を可能とするグループ会話支援システムを作りました。(▲写真13▲)
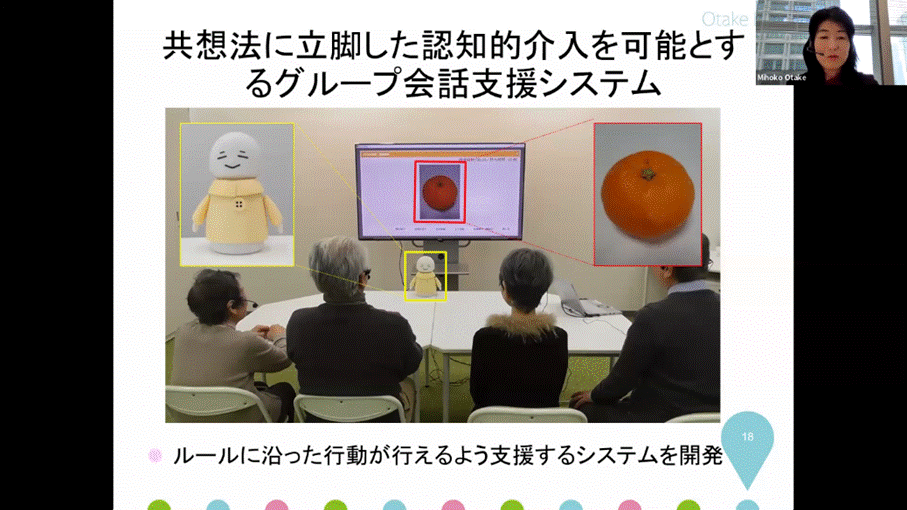
このシステムではロボットの『ぼのちゃん』がグループの会話を進行します。ロボットを使うことで、1人の実施者で複数の少人数グループの会話を同時に運営することができます。そして、ルールを守らない人がいた時にはロボットが遠慮なく指摘し、話が多い人を止めて少ない人に当てるといったことも自動で実行します。
ロボットの助けを借りて人間が行うことで、サービスの質と量をある程度、担保できるようになります。なお『ぼのちゃん』という名前は、「ほのぼの」という言葉に由来しています。参加者がほのぼのした気持ちで臆せず会話ができるような雰囲気を作ることを意図しました。「ぼのちゃん」は、ちょっと眠そうな顔をしていて、話をまとめられても仕方がないと言っていただけるような風貌にしてみました。
これを使った認知的介入プログラムを『PICMOR』と名付け、写真を用いた会話による認知的介入プログラムのランダム化比較試験を行いました。ランダム化比較試験というのは、ランダムに2つのグループを選び、一方には『共想法』に参加いただき、もう一方は何のテーマも決めずに30分の雑談をしていただき、その効果を比較するものです。その結果、『共想法』に参加いただいた方々は、言語流暢性という言葉をすらすら取り出す能力が有意に向上しました。
具体的には、1分間に言える『か』で始まる単語数で計測しました。『共想法』に参加いただいた介入群の方々は最初、平均で11.8個の『か』で、もう一方のテーマも何も決めずに雑談をしていただいた統制群は11.4個でした。終わった時に、介入群の方々は平均13.6個の単語を言えるようになったのに対し、統制群の方々は11.2個でした。この言語流暢性は認知症になると急激に落ちると言われており、『か』で始まる単語と言われても全然、思い出せないこともあります。つまり、後々落ちる可能性がある機能を底上げできたということになります。
それぞれのグループの会話にどのような特徴があったのかも調べています。介入群の会話では、単語に対する単語種類数が多く、たくさんの語彙が使われるような会話をしていました。雑談の統制群の会話では繰り返しが多くありました。『共想法』の方が、発言の種類としても、意味のある発言の割合が多いということも確かめられました。さらにMRIを用いて脳に与える影響を解析したところ、関連する脳の領域間のつながりが良くなって体積が増加する可能性を予備的に確かめました。
認知機能を発揮するために必要な脳内の機能的結合が存在していて、その行動ができるのであれば、認知機能が発揮されて、機能的結合において、結合が強まる可能性があります。そして、中長期的には、機能的結合が強まった結果、脳の構造が変化する可能性も示唆していることがわかりました。(▲写真14▲)
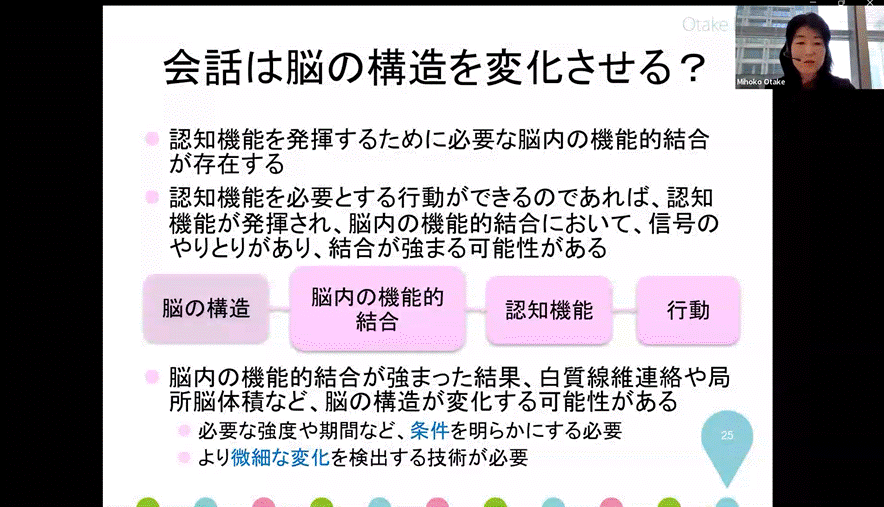
ただ、その必要な強度、どのぐらいの頻度、会話が必要なのか、どのぐらいの期間を要するのかなど条件を明らかにする必要があります。また、どのような状態の人に最も効くのかといったことも明らかにする必要があります。そして、より微細な変化を検出する技術も必要であり、そうした視点から現在、脳波で調べる方法も開発しています。
生理的アプローチ、認知的アプローチに続く
3つめの「社会的アプローチ」の重要性
ここで、「もともとは体験記憶と注意分割と計画力の3つを鍛えようとしていたのではなかったのか」という観点に立ち戻って考えますと、この言語流暢性はその3つの元となる機能を全部組み合わせた認知機能といえます。(▲写真15▲)
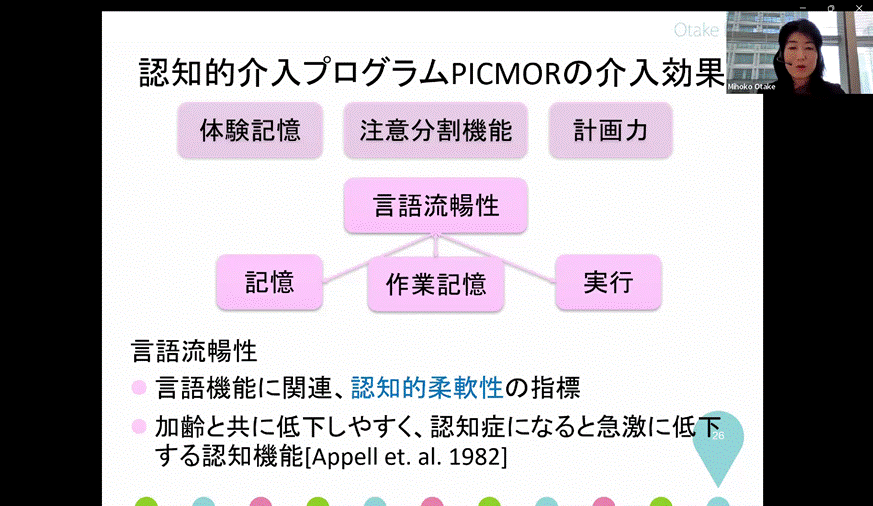
記憶と作業記憶、実行機能が言語流暢性の元になる領域です。それら単体での変化を正確に捉えるのはまだ難しいのですが、少なくともこの3つを統合した言語流暢性では差異を捉えることができます。言語流暢性は認知的柔軟性の指標とされ、認知症になると下がりやすい認知的柔軟性、『頭の柔らかさ』の指標を底上げできるということを確かめました。
中長期的には、数年後や10年後の認知症発症率まで見ていく必要があるのですが、まずは短期的に良い効果がありそうだということを確かめました。
この対面型システムはコロナ禍の前に制作して実験しました。その後、2020年からのコロナ禍の中では、自宅で対話ロボットを質問攻めにするシステムを作り、それを検証しました。スマートフォンを使い遠隔で会話をするシステムも作り、実証実験を実施してきました。(▲写真16▲)
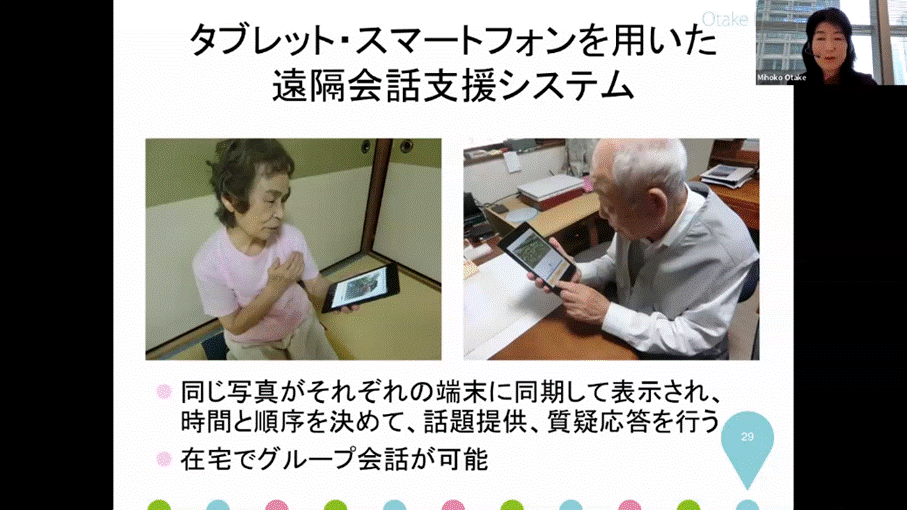
タブレットやスマートフォンを用いた遠隔会話支援システムでは、同じ写真がそれぞれの端末に同期して表示され『共想法』ができます。在宅でグループ会話が可能なことから、コロナ禍を機に当事者研究でも導入しました。家から出られない状態の人や遠方の人でも参加できるので、コロナ禍が明けた2023年以降も継続してこのシステムを使い、現在月1回、定期的に開催しています。対話支援ロボットは、埼玉県和光市、遠隔会話支援システムは、埼玉県和光市と大阪府岸和田市の自治体の協力を得て実験を行いました。
そして、脳が長持ちする社会の実現に向けて『街歩き共想法』の取り組みもしています。街歩きをして、それから会場に戻ってきて『共想法』でその日の体験について話すという取り組みで、今後もさまざまな地域で行っていきたいと考えています。こちらに参加すると、皆さん、興味をお持ちになって、継続参加につながることもわかっています。
継続コースについては『ほのぼの研究所』で実施していて、80歳だった方が94歳になるまで14年間継続して参加されるなど、全国から多世代の方々が参加されています。そのほかにも、介護施設などと協働事業を行っており、実施者が集まって知見を持ち寄り議論する合同研修も年に1回行っています。こういった施設とのコラボレーションなどが出発点になって、自治体との連携に繋がっています。自治体では最初、ランダム化比較試験の協力をいただいていたのですが、今後は地域全体にこのサービスが根付くためにどうしたらいいかという研究を一緒に行っていく計画です。
また、研究しながら認知症の予防の知識がまだ全く普及していないという課題を実感していまして、公式LINEを作ったり、Instagramで発信したり、YouTubeで動画を配信したりといった取り組みもしていますので、よろしかったらぜひ登録ください。(▲写真17▲)

◆【長持ち脳】大武美保子 公式LINE https://lin.ee/7zAfQl2Q
◆【長持ち脳の専門家】大武美保子 Instagram https://www.instagram.com/brain.robot/
◆【長持ち脳】NPO法人ほのぼの研究所 YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@brain.fonobono
こうした活動をしてきた中で、先般、『脳が長持ちする会話』という書籍を出版することにしました。特に、『共想法』に立脚して、日常会話で脳を活用するにはどんな会話をしたら良いのか、どんな生活習慣を持っていれば脳が長持ちするのかを具体的に列挙していますので、1つでも多く取り入れてみていただければと思います。
脳の認知症の予防のアプローチとして、この本には2つのアプローチまで書いているのですが、実は3つめがあるのではないかと思っています。今後、本を書く時には3つめも書こうかと思っています。生理的アプローチが老化を遅らせる、認知的アプローチが認知機能の低下を遅らせるという2つの方法に続いて、3つめは社会的アプローチです。認知機能が低下しても困らないように社会性を向上することや、社会環境を整えるというアプローチです。
これは、予防と共生の中の共生と言われていますが、認知症の定義からすると、社会生活に支障がある状態を指していますので、認知機能が下がっても、社会的生活に支障がなければ定義上、認知症とは呼ばないことになります。認知症にならない社会と言うと『認知症の人を排除するのか』とよく聞かれますが、そうではありません。そもそも困っていないのであれば、認知症の厳密な定義からは外れるということになりますので、少々認知機能が下がったぐらいでは困らない仕組みを用意できれば、原因疾患を持っている人はもちろん減らせますし、原因疾患がある、かつ認知機能が下がってしまったという人がいたとしても、それほどには困らない状況が作り出せるはずです。脳が長持ちする会話をみんなで実践していければ、より認知症にならない社会になっていけるのではないかと考えています。
多様性、得意不得意、そんな個人の「でこぼこ」を
お互いに認め合い、「ほのぼのできる社会」の実現を目指す
大武氏による研究内容の説明に続いて、B Lab所長の石戸 奈々子(▲写真18▲)が、ニューロダイバーシティの観点からさまざまな個人の特性と認知症との関係性などについてお聞きしました。
石戸:ありがとうございます。非常に示唆に富んだお話で、大変勉強になりました。私も『脳が長持ちする会話』を読んでいて、意外に思うことが多く、驚きでした。それらを踏まえて、いくつか質問させてください。
最後におっしゃっていたお話は、ニューロダイバーシティの文脈での議論と同じです。つまり、社会的に困っていなければ厳密には認知症とは定義されないという指摘は、発達障害の特性が強かったとしても、社会的に困りごとが起きていなければ発達障害とは診断されないという話と同様です。また、社会の環境を整備し、頼る先を増やしていくことで認知症を認知症でなくすというのもニューロダイバーシティにおけるアプローチと同じです。認知機能が落ちることを防ぐことの大切さのお話もありましたが、それに取り組むと、認知機能が上がることもあるということですよね。
大武氏:言語流暢性に関して言うと、介入することで認知機能が上がっています。ただ、その他についてはそう簡単には上がりません。評価方法も、もっと長い時間介入して、何もしない人は下がるけれども、やっている人は下がり方が緩やかであるといった方法で、違いを示す必要があります。そうすることで、今、注目している3つの機能の違いも出る可能性が今後あると考えています。
基本的には、下がるスピードを落とせばよく、言語能力も上がると言われていますので、上がりうるものを上げていく、伸び代がある種類の機能に対しては上がるように介入し、逆に計算速度のような処理速度は残念ながら下がる、生理的な状態の変化に起因すると言われていますので、下がるものは生理的アプローチでできるだけ老化を遅らせるのが効果的と考えられます。
石戸:ニューロダイバーシティは、1人ひとりの脳や神経は多様であると考えて全ての人を対象に取り組んでいますが、当初、この考え方は発達障害当事者の方の権利運動として始まりました。先ほど『意識して自分の状態をコントロールする力』という表現を使われていました。例えば、ADHDの方に忘れ物が多いことについては意識がほかに移り変わってしまうからだと言われます。つまりコントロールがしにくいとも言えるわけですが、そこをコントロールする力と認知症の発症とは関係性があるのでしょうか。
大武氏:ADHDの方だとこうなる、ならないというのは、まだ統計としては整備されていません。ただ、うつ病の方は認知症のリスクが2倍になることが知られています。ADHDの方が意識をうまくコントロールできない、意識が移り変わってしまう特性があると思いますが、その場合の対処法としても、物を置く場所を決めたり、ルールを決めて必ずそこに置くと決めることで気まぐれに置かないというルールを自分に課せば、ADHD傾向があっても失敗の数を減らせるようになります。
意識という点で言うと、ルールを作る、あるいは、これだけはこうすると自分の失敗が減るからそうするという意思の力である程度カバーできると考えられます。認知症の方であっても全く覚えられないわけでなく、根気よく繰り返せば覚えられるのと同じで、覚えられるまで粘り強くやってみることが大事です。あとは、目についている間は記憶できるということがあります。人の名前を覚えきれなくても、みなが名札を付けることにすればいつでも目に付きます。わからなくても見ればわかるようにすることもできます。
認知症の方は、まだらに正気に戻るとも言われており、例えば元気な日でも夕方になり疲れて覚醒度が落ちてくると、だんだん調子が悪くなってくることがあります。朝、元気なうちであれば意識が保たれていることも多いので、意識の波にうまく乗ることが大切です。例えば、集中できる朝方に難しいことをやった方がいいなど、仕事のハウツーとして知られていますが、同じ人でも1日の中で状態が良かったり、良くなかったりしますので、自分は朝の方が調子が良いとわかっていたら、認知症の方であっても、ややこしいことは朝やって、夕方には難しいことをやらないというような、特性に応じた方法やルールを決め、それを自他ともに認めて実践することが大切です。そこは覚えられるまでなんとかやってみるようにすることで、社会生活に対しての影響を小さくできると考えられます。そこは認知症もADHDの方にも言えることではないかと思います。
石戸:なるほど。『みんなの脳世界』に出展いただいたリラックスする脳波の話では、リラックスするように意識をコントロールすることは自分のウェルビーイングを保つ上で大事だと思いますが、それも練習していくと出せる状態に持っていけるようになるのですか。
大武氏:それはあると思います。私は大学時代に合気道をやっていたのですが、無意識に吸ったり吐いたりしている呼吸を、意識して吸ったり吐いたりできるようになりました。呼吸は意識と無意識を切り替えられる面白い題材だと思っています。
また、はーっと強く息を吐くと、かなりリラックスできますので、呼吸が浅くなっているかを意識して、自分が今どんな呼吸をしているか見ていき、今は呼吸が浅くなってリラックスしていないと気が付いたときには、もっと深く吐いてみよう、あるいは長く吐いてみよう、というように生理的状態を意識の力でコントロールすることで、リラックスの状態に近づけられるようになります。そうすると、息の力を借りなくても瞬間でぼーっとする状態を作れますし、逆に瞬間で集中を取り戻せるなど、そこは練習なのではないかと思います。
石戸:なるほど。ありがとうございます。まだ聞きたいことはたくさんあるのですが、お時間になってしまいましたので、最後に、ニューロダイバーシティ社会実現に向けて、一言メッセージをいただいて、おしまいにしたいと思います。
大武氏:そもそも物忘れに興味を持ったのは、子どもの時から忘れ物が多く、この忘れるということは一体どういうことなのだろうと自分事として興味を持ったからです。そこから、認知症の方のように自宅へ戻れないほどに忘れてしまうのを防ぐにはどうしたらいいのだろうと思い、この研究が始まりました。
どんな人でも多様性があり、特性、得意不得意に『でこぼこ』があると思いますが、そんな中で自分のでこぼこをみんながお互いに知っている、自分のことも知っているし、相手のこともある程度知っている、そうなれば、でこぼこがあることを客観視できるようになるでしょう。そして、みんなが衝突しないで快適に過ごせるようになればと考えています。
自分のことがわかってくると、おそらく認知症になる人も減ると考えられますし、でこぼこがあって生きづらいという人も減ってくると考えられます。みなが気持ちよくご機嫌に過ごせるように自他ともになりたい、そんな『ほのぼの社会』の実現を目指しています。
ニューロダイバーシティプロジェクトはすごく面白いプロジェクトであり、他の方のお話も面白く拝見しましたが、みんなで良い社会にしていけたらいいと率直に思いました。この取り組みを推進されている石戸さんに本当に感謝しています。
石戸:ありがとうございます。私もみんながご機嫌に過ごせる社会の実現に向け、頑張ります。