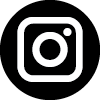トークショー「ニューロダイバーシティ社会に向けて」の開催
2024年9月19日

おもしろい未来をみんなでつくるラボ「B Lab」は、ひとりひとりがそれぞれの場所で各々の「ちから」を発揮できる社会の構築を目指して「ニューロダイバーシティプロジェクト」を発足しました。その第一弾の取り組みとして、2023年09月17日と18日の2日間、東京ポートシティ竹芝にて開催されたイベント『ちょっと先のおもしろい未来 –CHANGE TOMORROW-』(ちょもろー)内で展示「みんなの脳世界~ニューロダイバーシティ展 2023~」を開催。本稿では18日に行われた「ニューロダイバーシティ社会に向けて」をテーマとしたトークショーの様子を紹介します。
トークショー概要
「ニューロダイバーシティ社会に向けて」
■日時:
2023年9月18日(月)13時~14時00分
■登壇者 :
伊藤 穰一 (千葉工業大学 学長)
牛場 潤一 (慶應義塾大学理工学部 教授)
南澤 孝太 (慶應義塾大学KMD 教授)
吉藤 オリィ(株式会社オリィ研究所 代表取締役所長 CVO)
■モデレーター:
石戸 奈々子(B Lab 所長)
ニューロダイバーシティとは
すべての人が生きやすく力を発揮しやすい社会を推進する取り組み

石戸「ニューロダイバーシティ」という言葉を聞いたことはありますか。人間の脳や神経はとても多様で独自の特徴を持っています。それらの違いを強みとして生かしていこうというのがニューロダイバーシティの考え方です。私たちは、一人ひとりが、それぞれの場所で各々の力を発揮できる社会の実現を目指して、ニューロダイバーシティプロジェクトを発足しました。その第一弾が今回の「みんなの脳世界~ニューロダイバーシティ展 2023~」です。日本を代表するさまざまな大学、研究所、企業が参画し、33もの展示コンテンツが集まりました。
さて、人はみな個性や特性を持っていますが、それがゆえに生きづらさを感じている人もいます。ときには発達障害など個人の特性が問題であるかのように言われてしまうこともあります。しかし、その人たちが感じる生きづらさは、個人の特性だけに起因するものではありません。個人の特性と環境との相互作用によって生じているものです。
つまり、環境次第でその個性や特性がとても大きな力となることがあるということ。例えば、歴史的な発明家や社会に大きなインパクトをもたらしている起業家には発達障害であることを自ら話されている方も多くいらっしゃいます。しかし彼ら彼女らは自身の特性を活かせる環境に身を置くことで、発達障害という特性が「強み」となっています。全く同一の特性を持っている人が、環境次第でカリスマ経営者になったり、就業に困難を抱えたりすることがあります。ですから私たちは個性を尊重し、適切な環境を整えることで生きづらさを解消し、すべての人が自分らしく活躍できる社会を実現していきたいと考えているのです。
私たちは2つのアプローチを試みています。ひとつは、テクノロジーによって個の力を拡張する取り組みです。例えば眼鏡を思い浮かべてください。メガネがない時代には、視力が悪いと生きづらかったと思います。今は視力が悪い人を障がいとは言わないと思います。さらには、ファッションとして眼鏡をかける人もいます。このようにテクノロジーによって身体や脳機能を拡張することで、人の可能性はぐっと大きく広がるのです。
もう一つは、環境を調整するというアプローチです。私たちの日常は物理的な環境や、社会的な制度、ルールや慣習、人間関係などによっていろいろな影響を受けています。例えば色覚障害の方には信号機の赤と緑が判別しにくいことがあります。しかし、別の色なら見えるとしたら、信号機の色を変えれば生きづらさが減るとも考えられるのです。
また、感覚過敏で制服が重く感じたり、肌がチクチクするからと学校に通えなくなる子どもたちがいます。制服着用のルールがそもそもなければ、そうした子どもたちも学校に問題なく通えるかもしれません。このように、環境を調整することで生きやすい社会を実現していこうという取り組みも進めています。

「みんなの脳世界~ニューロダイバーシティ展 2023~」では5つのコーナーで、「個の拡張」や「環境の調整」などをテーマにした展示をしています。

ぜひ、『ニューロダイバーシティ社会を自分の力で実現する』という視点で展示をご覧いただき、『へぇ、なるほど、そうなんだ』で終わらせずに、『どうすればすべての人が生きやすい社会を作れるのか』、『自分だったらどんな行動ができるのか』に考えを巡らせていただければと思います。このトークセッションも、その視点で議論を進めていきます。
それでは、登壇者の方々のお話を伺います。『ニューロダイバーシティに向けた発表』というテーマで、まずは千葉工業大学 学長の伊藤 穰一さんからお願いします」
天才の多くは自閉症である
能力を発揮できる環境が重要

伊藤氏「ニューロダイバーシティという言葉を耳にすると、思い浮かべるのは自閉スペクトラム症(以下、ASD)です。私の父は、診断されてはいませんがきっとASDです。それと私は、自閉症の学生が多いとされるマサチューセッツ工科大学(MIT)で、2011年~2019年にメディアラボの所長していました。当時の同僚からは『きちんと診断すると、MITの学生の6~7割は自閉症だろう』という話も聞いています。
MIT出身のノーベル賞学者は98人もいますが、ほとんどの天才は自閉症です。ほとんどの自閉症は天才ではありませんが、『天才が多い』だけでもかなりスペクトラム(ASDとそうでない人との境界が明確でない)であることは忘れてはいけません。
アメリカには自閉症の人たちのカルチャーがあり、自閉症の人々に対する理解とサポートがたいへん進んでおり、その人たちの個性を尊重する文化が確立されつつあります。日本はいわば全員が大企業の会社員を目指すというように標準化された人間を一生懸命作ってきました。標準に当てはまらない人が出てくると、その人にしかない強みがあっても無視されて、外されてしまうのが実情でしょう。そこで、まずは標準化が最優先とされるような、『標準化しなければならない』社会を変えなければいけないと思います。
これは笑い話ですが、MITのメディアラボで個人的に自閉症スペクトラムの研究をしていたところ、同僚に『自閉症の子どもを育てるのはとても大変で、自閉症の専門家の育成が急務だ。伊藤さんの子どもが自閉症であってほしいね』と冗談を言われました。すると生まれた娘は自閉症でした。
その娘を連れて日本に戻って、日本の自閉症の子どもたちに対する環境整備が遅れていると感じました。何とかしなければいけないと思い、2024年に自閉症の子どもとそうでない子どもたちを混ぜたプログラムを立ち上げ、日本での活動を開始しました。」
石戸「ありがとうございました。次は慶應義塾大学KMD教授の南澤 孝太先生です」
自らの可能性を広げる
「新しい身体」を手に入れる研究

南澤氏「私たちは、身体がテクノロジーとつながることでどんな新しいことができるようになるのだろうかという『身体性メディア』の研究を進めています。ロボットやバーチャルリアリティ、触覚を再現する技術などを開発しています。

まずは『Dementia Eyes』です。ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を身に着けると『認知症の方が見ている世界』に没入でき、空間がゆがんだり距離がわかりにくくなったり、椅子に座るのが難しくなったりする体験ができます。この開発には、実際に高齢者の介護をしている人にもご協力いただきました。介護士や医師がこのHMDをつけて体験してみると、その後の患者との接し方や話し方が変わるそうです。

もう一つが『個の拡張』の研究です。例えば、自分の体をデザインするというテーマでは、人間が尻尾を持てたらどんな新しいことができるだろうという研究プロジェクト「Aique」に取り組んでいます。
さらに、「Musiarm」というプロジェクトでは、尻尾をつける技術を手足にも応用し、右腕から肘先がない人のご協力を得て『楽器を弾きたい』という希望を叶えようと腕自体が楽器になる装置も開発しました。これらは『みんなが同じ身体でなくてもいい』、『個々になりたい身体になる』ことを実現するプロジェクトです。

こうした研究の究極の形が、この展示会でも披露した武藤 将胤さんという筋萎縮性側索硬化症(ALS)の当事者のパフォーマンスです。ALSは進行する病気で、どんどん体が動かなくなってしまうのですが、目を使って会話をしたり、BMIを活用し脳の動きでロボットアームを動かしたりすることで会場の人たちと一緒に盛り上がることができました。
そして、これらの研究成果を踏まえた『社会の創造』をテーマとした研究も進めています。この後にご登壇いただく吉藤オリィさんと一緒に進めている研究で、さまざまな理由で家から出られない人たちが、自宅からでもいろいろなことができ、社会参加できるようになる世界を作り、そこで新しい働き方や学び方を生み出そうという取り組みです。

眼鏡やコンタクトレンズで障がいを克服できているように、新しい身体を新しいテクノロジーと組み合わせながら、新しい社会を作る研究を進めています。

石戸「テクノロジーを活用することで広がる脳や身体の可能性をご紹介いただきました。最後は株式会社オリィ研究所 代表取締役所長 CVO 吉藤オリィさんです。よろしくお願いします」
分身ロボットで「コミュ力」を拡張し
人の孤独を解消する

オリィ氏「私は子どものころ、学校にあまり通えませんでした。身体が弱くて入院し、精神的にも不安定だったのです。オリィと呼んでいただいていますが、本名は吉藤健太朗です。健康に、太っていて、朗らかで。しかし、まったく違っていました。この名前が大嫌いで、健太朗と呼ばれても無視し続けるような子どもでした。名前と容姿が違うということは、もはや自分を自分と思えないということ。その状態がずっと続いていたのです。自己認知やメタ認知の芽生えも、他人よりかなり遅かったのです。
自分のアイデンティティが確立できずふわふわした状態で、学校で居場所を得ることができませんでした。他の人と違うことや生きにくさを感じながら不登校になっていたときは、本当に孤独を感じていました。何もすることがなく、天井を眺め続けていると日本語を忘れかけたりするのです。笑い方も忘れました。
そのような経験をずっとしてきましたが、高校生のときに電動車椅子の新機構の発明に関わり高校生科学技術チャレンジで優勝し、文部科学大臣賞を受賞して世界大会にも参加しました。しかし、その時、本当は車椅子を作りたいのではなく、車椅子がないと外出できない人が自宅にこもってしまい感じる孤独を解消するものを作りたいのだと思ったのです。そこで、離れていても人とコミュニケーションができる分身コミュニケーションロボット『OriHime』を開発しました。
能力、力といいます。先ほど眼鏡の話がありましたが、私は目にコンタクトレンズを移植するICLの手術でサイボーグ化していて、視力の障がいはなくなりました。車椅子は脚力をサポートします。英語力なら通訳システムがあります。しかし、コミュニケーション力に対するものがなかった。そこでコミュニケーション力のサポートについて研究し、カフェという名前を使った研究所を作りました。地下の研究室で作ったものをお客様の前で実験し、暴走してお客様に謝ることを繰り返す、いわば『世界一失敗するカフェ』です。この分身ロボットカフェのDAWNで、ここのロボットは、引きこもり、病気で学校に通えない人、長く仕事を休んで会社に戻れなくなってしまった人、人前に出るとパニックになってしまう人たちが遠隔から動かしています。このロボットを使えば人前で話せて、接客もできるのです。

先ほど、自己アイデンティティという話をしました。私の名前の『オリィ』は、折り紙が好きで入院中ずっと折り紙をしていたことからつけました。この黒いビジュアルも18才の頃からで、人生の半分は黒を着続けています。この格好とオリィで自分を確立しています。私は、オンラインゲームもこれに近いものがあると思っています。リアルの世界で自分の居場所を見つけることができない人も、オンラインゲームなら夢中になれるし、友達も作れます。
VR空間にダイブするのがヘッドマウントディスプレイだとすれば、このロボットは、いわばVR世界の住民がリアルの世界にダイブするための装置でもあります。これで入院している子どもたちが学校に通えるようになったり、人前で話せるようになったりもしています。

さまざまな装置を使えば、例えばALSで目しか動かなくなった人でも目だけでデバイスを操作して絵を描き上げることができます。

私は、できないからこそやろうと思えるし、できないことには価値があると本気で思っています。そしてそのような人たちの能力を拡張する新しいシステムを作っています。目指している最終形は、身体を動かすことができなくなったときに自分で自分を介護することです。自分で身の回りのことするのは、個の確立にたいへん重要です。自分でやったと思えて、他の人がやってくれたことにお返しができたという実感を得るための装置、私がOriHimeというロボットの開発を通じて取り組んでいるのは、そのような研究です」

多様性こそがイノベーションの源泉となる社会を
石戸「ありがとうございました。不登校や引きこもりという言葉がありましたが、お話しを聞いていてそもそも学校に行くことだけが登校なのか、自分の人生を充実させる活動をオンラインでしていても引きこもりなのか、これまでの言葉の定義をすべてアップデートする必要があるのではと思いました」
オリィ氏「今、この会場の中に『人混みに行くと絶対にしんどくなるけど、OriHimeで人混みに紛れてみた。今日が人生初、という人がいます」
石戸「確かに聴覚過敏の方などがOriHimeに乗っていたら、しんどいと思ったときは音を遮断することもできますし、自分に快適な環境を調整しやすくなると思います。
4人の方のお話しで、未来の新しい希望を感じられたと思いますが、テーマのニューロダイバーシティに戻ってみたいと思います。Joiさんにお伺いします。ニューロダイバーシティという言葉は日本でまだそれほど広がっていません。世界と比較して遅れているように思いますが、海外に比べていかがでしょうか」
伊藤氏「アメリカでは人種差別の長い歴史もあり、ニューロダイバーシティは新しい人権問題にもなっています。1960~70年代頃は医者が自閉症の治療を行っていましたが、その後に親が『(治療して)普通の子にしよう』から、『自分のままでいい』とのムーブメントを起こし、最近では当事者が『自分が幸せかどうかを大事にする』という動きが強くなっています。セラピーの方法もかなり多様になってきています。このような点、日本はちょっと遅れているイメージがあります。
ただアメリカは、普通の人に合わせるために健常者の視点からサポートする観点のテクノロジーが多く、ニューロダイバーシティの人たちを賞賛する考え方は遅れていて、オリィさんのお話にあったような取り組みはあまりないです。日本は昔から『オタク社会』などコミュニティの中に多様な賞賛のかたちが存在していたと思います。このような文化をきちんと混ぜ込むと、日本のニューロダイバーシティの取り組みは海外と比べて劣るようなものにはならないと感じています。アメリカのムーブメントと日本のイノベーションがリンクすると、すごく意味があるものができるではないかと思いました」
石戸「私たちのプロジェクトでは『テクノロジーで課題を解決していく』ことと同時に『当事者と一緒にテクノロジーの開発や環境構築をする』ことを重視しています。みなさんのご意見をお聞きしたいです」
オリィ氏「障がいがある人をサポートしようとする人の会に私がOriHimeを持っていったら『当事者が来たのは初めてだ』と言われたことがあります。当事者としての意見を言ったら、その場が凍りついてしまったこともありました。今までは、テクノロジーをどう導入すると介護が楽になるかという介護者だけの視点が多かったのです。OriHimeのように当事者の分身となって一緒に動くものはなかったのです。それに気づいてから、当事者と介護する人、そこにテクノロジーと考えるようになりました。最近では、さらにそれを応援する人たちも含めてテクノロジーの進化を楽しんでくれています。コミュニティ的に浸透するのが正解なのだろうと感じています」
南澤氏「2015年ぐらいから、3DプリンタやVR、最近はAIも、今までは専門家のためだけだったのものが誰でも使えるものになってきたことは大きな変化だと思います。当事者が『こうしたい』、『これを使ってこう作ろう』を言いやすくなったと思います。
今はそこからもう一段階進み、それをしっかり社会にインストールするためにはどうすればいいかまで考えられてきています。Orihimeを盲導犬のように抱えて店に入れるようにしようというプロジェクトが立ち上がったり、アニメや漫画の世界を実現するために社会のルール変えようとのムーブメントが起き始めたりしていることは、面白いと思います」
石戸「昨年の『ちょもろー』では、ロボットが街を歩くハロウィンパレードをしたのですが、ロボットが道路を歩くことにも、いろいろな規制がありました。ちょもろーはテクノロジーを社会実装するにあたり、ボトルネックになっていることを明確にする機会という位置づけでもあります。
今回、展示で紹介されているテクノロジーは、生きづらさや困りごとを助ける手段として開発されたものですが、そこから一歩踏み込んで『今までの「普通」を変えたほうがいいのでは』という視点にたどり着ところがとても重要だと感じます。これまでの普通の方がむしろ変わったほうがいい、いままでも普通もテクノロジーを使った方がよりアップデートされた社会になるのではないかという問題提起につなげていきたいと思っています。ニューロダイバーシティプロジェクトで実現したい社会は、まさに次の時代に当たり前にあると思います。一方で、社会受容が一番のボトルネックではないかと思っています。初めにJoiさんがおっしゃっていた、日本の標準化、同調圧力のようなことについては、他国と比べてどのように捉えていらっしゃいますか」
伊藤氏「去年、国連がかなり辛辣な言葉で日本を名指ししました。日本は障がいがある人をサポートすると言いながら標準的な人しか普通の学校に行けないシステムができています。このことが意味しているのは、普通の人が『(世の中には)普通の人しかいない』と思っているということです。
標準的な脳のことを英語ではニューロティピカルと言い『ニューロティピカル・シンドローム』という言葉もあります。これは、自信をもって自分のことを普通だと思っていて、事実を確認することより、人にどう思われるかを重視する人たちのことです。日本にたくさんいます。
日本社会の『普通』は普通ではありません。これは重要です。障がいがある人が入っていない状態が『普通』になっています。私は健常者と自閉症の子が一緒に通える学校を作ろうとしています。そのプレゼンをしたとき、ある『偉そうなおじさん』に『普通の子どもの親は、自分の子どもを障がい者の子どもと混ぜたいとは思わない』と言われました。『いや、混ぜないとあなたみたいな大人に育ってしまいます』と思わず言いそうになりました。このようなことを普通に言う人が、偉いポジションにいるということも日本社会のリスクだと思います。
障がい者は社会で活躍できないと思っている人たちがいることも、すごく貧しい国だと思います。今日のような場が普通になれば、それも改善するのではないかと思います」

石戸「おっしゃる通り、「健常者」とされている方以外が排除されたあとの普通が、日本の状況だったのかなと思います。だからこそ、日本のインクルーシブ教育に関する国連の勧告もあったのだろうと思います。この展示でお互いの感覚の違いを体験する場を用意しなければいけないことすら恥ずかしいことかもしれません。でも過渡期としてはこうして情報を共有しつつ、みんなで考えていくことが大事なのかなと思いました。
『新しい自分をデザインする』とありました。テクノロジーを使ってありのままに生きられる自分や取り巻く環境をデザインできることが次の時代なのかなと思います。みなさんは2050年ぐらいに、どう自分らしいデザインを、どんな状況でできていると思いますか」
南澤氏「2050年といえば私は70歳手前ぐらいですね。今、私たちはSNSなどでいろいろな自分を「演出して」生きている傾向があるのではないかと思います。それが今後は、本来の自分はこんなことができたとか、自分の人生経験の中にこんなものがあったから今の自分があるということを拡げられるようなテクノロジーの使い方や社会をつくっていけたらいいと思っています。一人ひとりが多様な経験を積み重ねることによって、個々の世界そのものが拡がっていく、そして私たちのさまざまな経験は実はテクノロジーがいろいろな形でサポートしてくれている、そういった社会を思い描いています」
オリィ氏「2050年だと60歳ぐらいです。高齢というには早いかもしれません。私は本当に身体が弱くて、17歳の時には30歳になったら死ぬと本気で思い、あと17年で何ができるかと人生30年計画を立てました。でも、終わりを意識することはすごく有効だったと思います。そうすると1日1日を大事に生きることができます。悔いのない人生を選択できることが大事かなと思います。その時に自分がやりたいと思うことがあり選択肢があるかどうかが大切だと思います。夜の自分らしさと朝の自分らしさは全然違うし、空腹のときと満腹のときの自分も全然違います。私はテクノロジーを通して、選択を作っていきたいと思っています。
私は仕事柄、寝たきりの人にたくさん会ってきました。老後に寝たきりになったときに何があるか、最近考えます。お金や趣味も大事なのですが、一周まわって関係性が最も重要だと思っています。地位もお金もあって子どもいるはずなのに、誰もお見舞いに来なくて放置されているおじいちゃんの一方で、ALSで寝たきりでもヘルパーさんたちとワイワイ楽しそうな人もいます。この分岐点はやはり関係だと思います。寝たきりになっても周りに人が集まる状態を作るために必要なのは、『スナックのママのコミュ力』かもしれません。最近、分身ロボットカフェにも『スナックOriHime』と看板を立てています。言ってみれば『スナックテック』だなと思い、その研究をしていきたいというのが、最近のテーマです」
石戸「実は私、スナックのママになりたいとずっと憧れていました」
オリィ氏「遠隔でスナックのママもできますよ」
石戸「それ、やりたいです。随分前から自分のやりたいことリストにスナックのママと書いてあるんですよ」
オリィ氏「寝たきりの先のキャリアにぜひ」
石戸「真剣に考えておきます。脱線してしまいましたが、障がいという言葉をどう使うかどうか、この展示において、すごく議論しました。何をもって障がいとするか、ということです。例えば、環境の展示のところに四角いタイヤの自転車を置いていますが、床が平らなら丸いタイヤの自転車は進みやすく、四角いタイヤだと進みにくい。ところが、でこぼこした床だと四角いタイヤのほうが進みやすくて、丸いタイヤだと進まないこともあるのです。環境によって変わる。何をもって障がいと考えるかは難しい、ということになると思います。Joiさんはいかがですか」
伊藤氏「2050年には、私は84歳です。何年か前にある博士を日本に呼んで彼の研究の会議を2日間、行いました。彼は70何歳でしたが、『私の知識で皆さんが持っていないものはない、もう安心して死ねる』と言っていました。私の理想も将来には、今の自分の知識をみんながすべてネットワークで持っていて、自分が今までやりたかったことを自分よりも上手に一生懸命にできる後輩や教え子がたくさんいる、自分がいなくなっても自分の夢は続いていく社会となるといいなというものです。テクノロジーの進化もあり、2050年頃には自分よりも自分の考えていることをうまく実現してくれるようなシステムが生まれているだろうと思いますので、私は永久に生きたいと考えるよりはリタイヤします」
石戸「一生現役で、いつもでも生き続けていただかないと困ります。そろそろ時間になってしまいましたが、最後、『ニューロダイバーシティ社会実現に向けて』のメッセージをいただきたいと思います」
オリィ氏「ダイバーシティを考えるときに、それを理解しようとはするのではなく、当事者の人たちと友達になってください。寝たきりの人が身近になる時代が来ます」
南澤氏「時代もテクノロジーもどんどん変わってきます。できないことがどんどんできるようになっていくことを前提に、新しい自分の人生を作っていければ良いと思います。どう自分の人生を作っていきたいかを一緒に考えていければと思います」
伊藤氏「子どもたちの弱いところを強化することに集中して、強いところをほったらかしにするよりも、強いところを拡張することがすごく重要だと思います。子どもの頃には多くが自分はアーティストだといわんばかりに絵を描いたりするのに大人になると誰もしなくなってしまうのは、自信を失っているからだと言えます。英語ではクリエイティブ・コンフィデンスと言いますが『周囲を変えることができるという自信』、それを持ち続けられるかどうか、子どもたちにそれを失わせないことがとても大切だと思います」
石戸「この展示を作るとき、多様性こそがイノベーションの源泉であるということをベースに組み立てたいと思いました。多様性の受容は『ダイバーシティ・インクルージョン』とも言われるようになりましたが、日本は男女のダイバーシティすら実現できていません。本当の意味で多様性に対する寛容な社会を実現するためには、一人ひとりの積極的な社会参画が必要だと思います。みなさんで共に新しい未来を作っていけたらと思います。本日はみなさん、ありがとうございました」