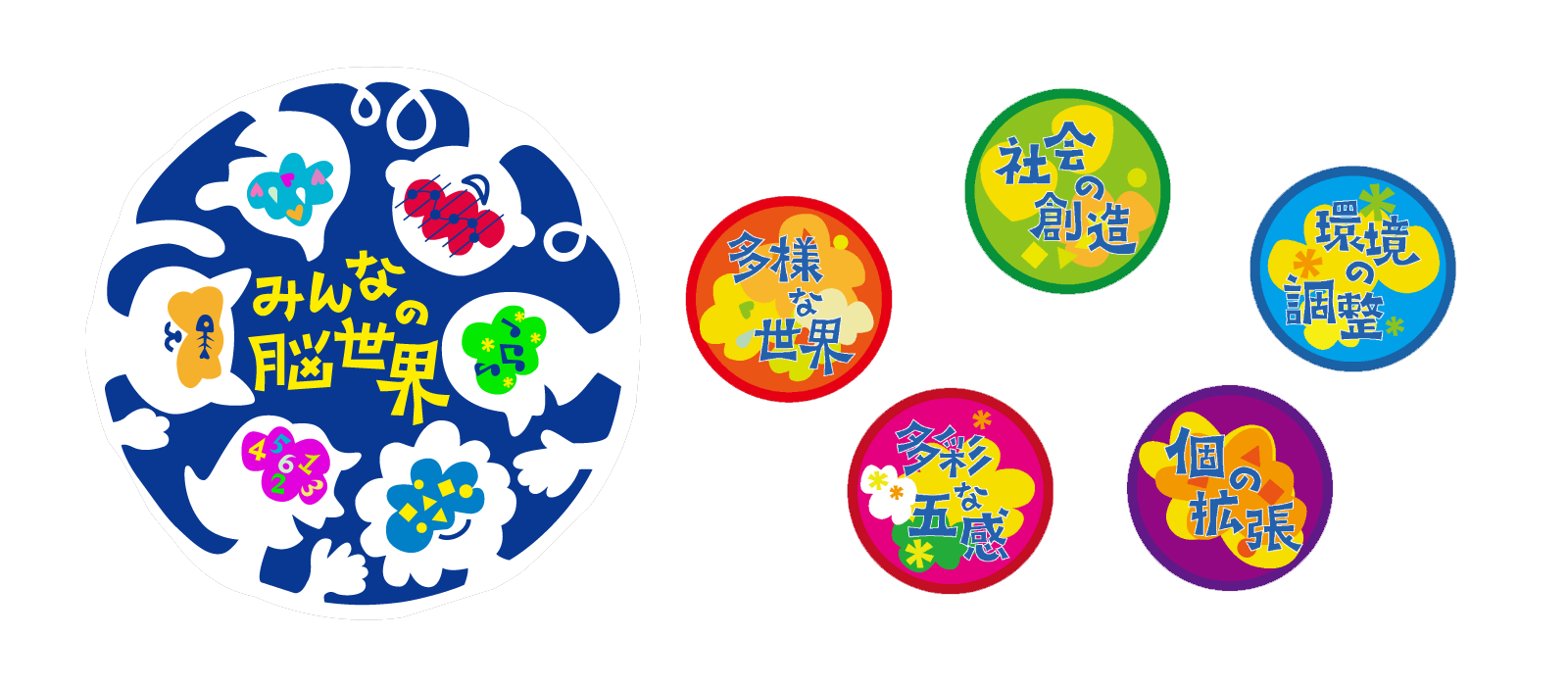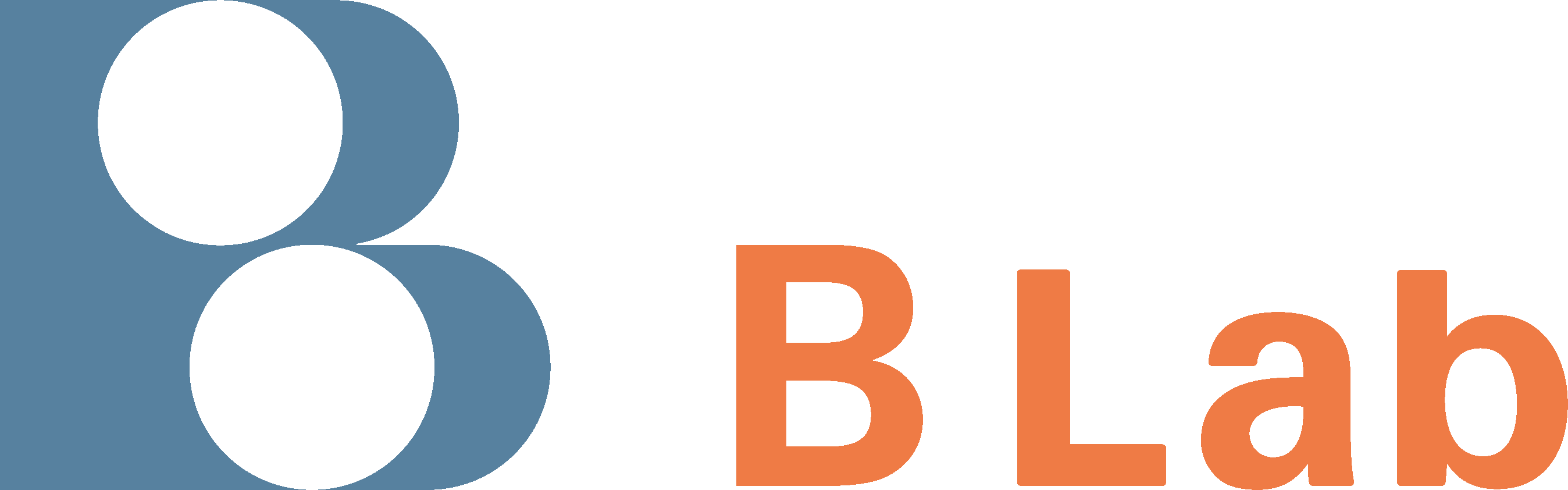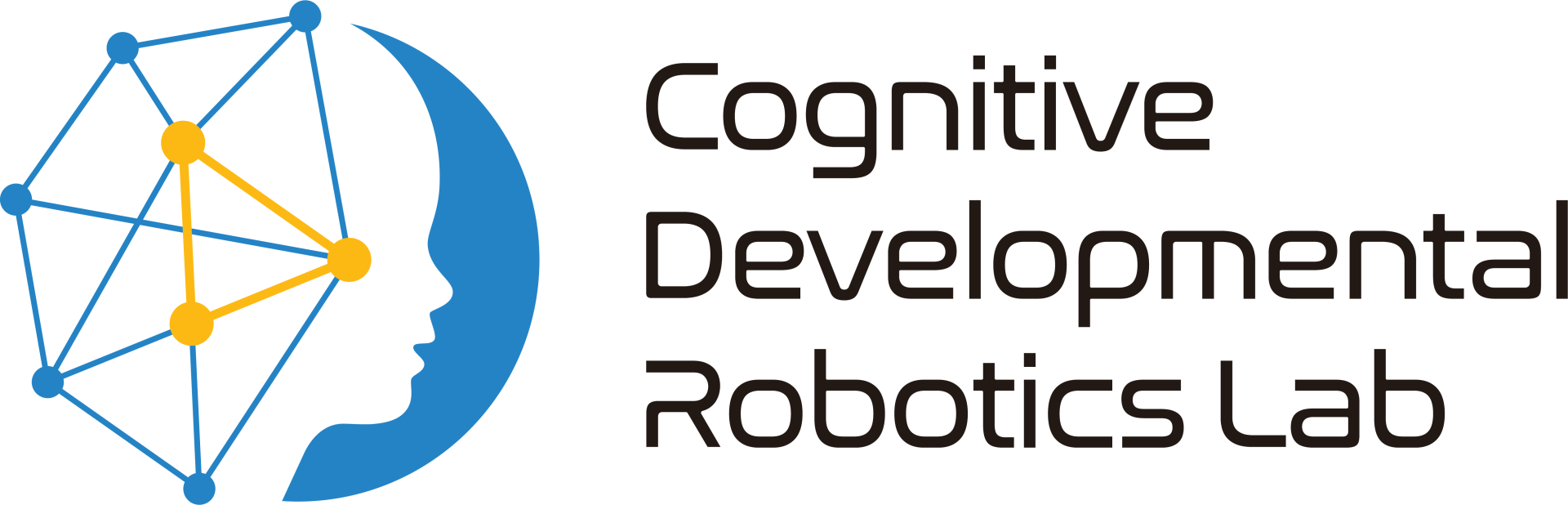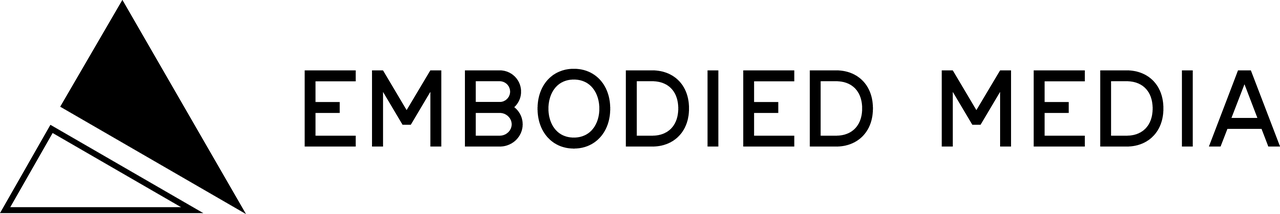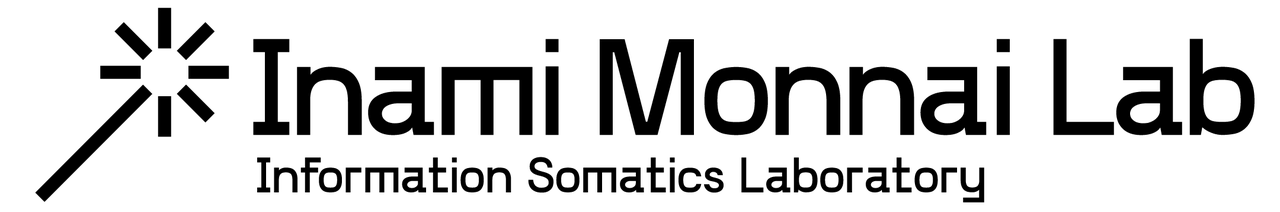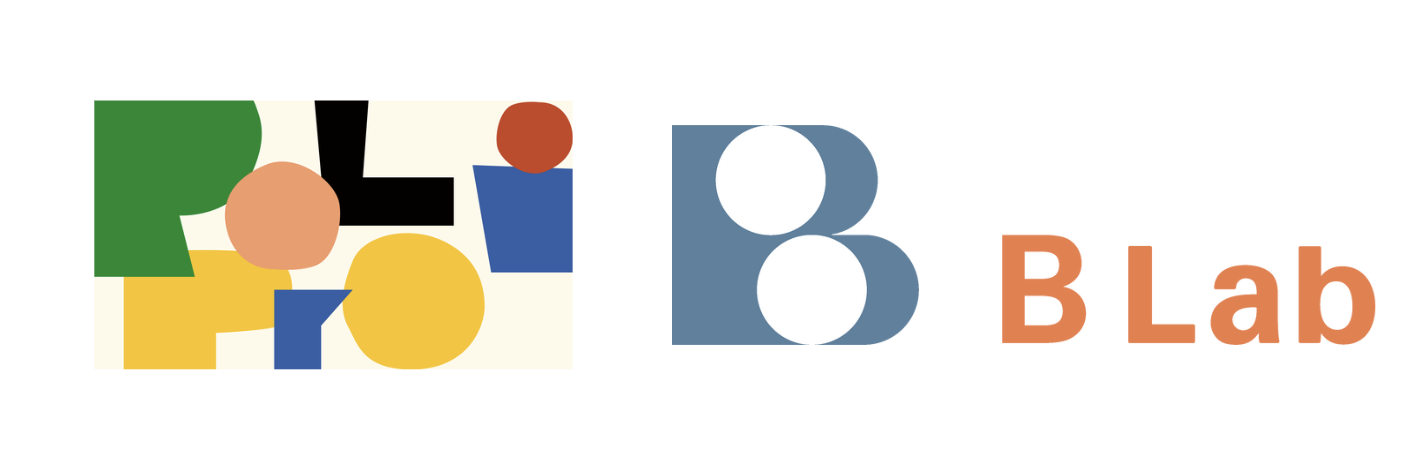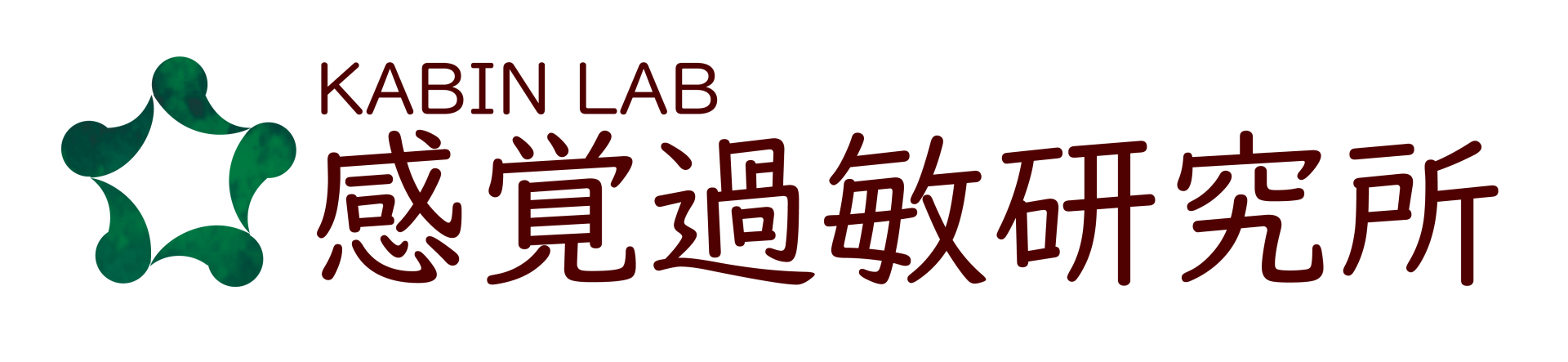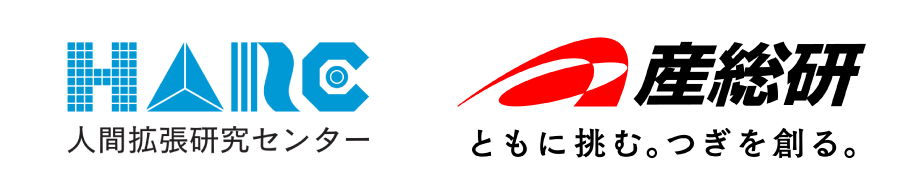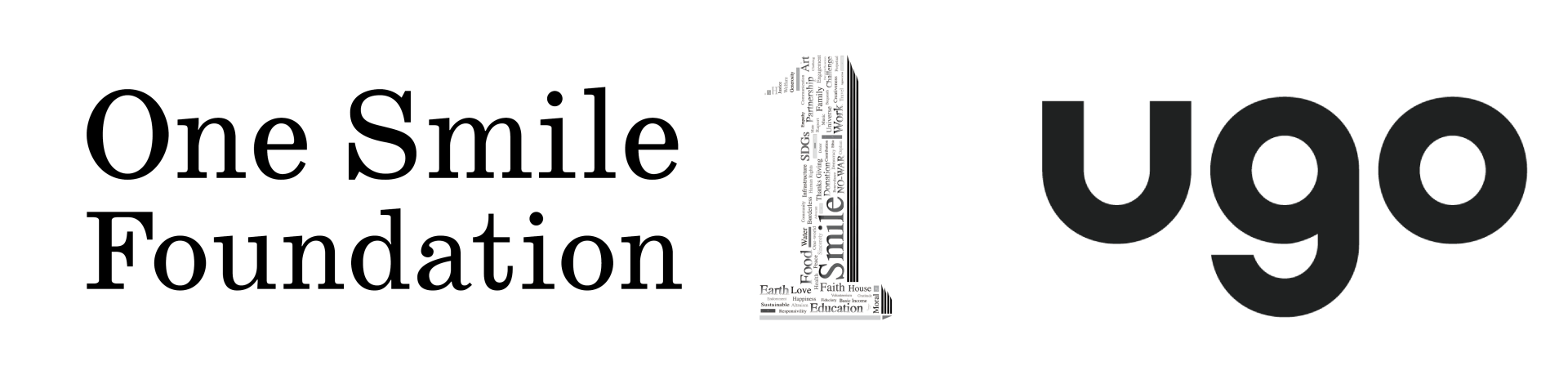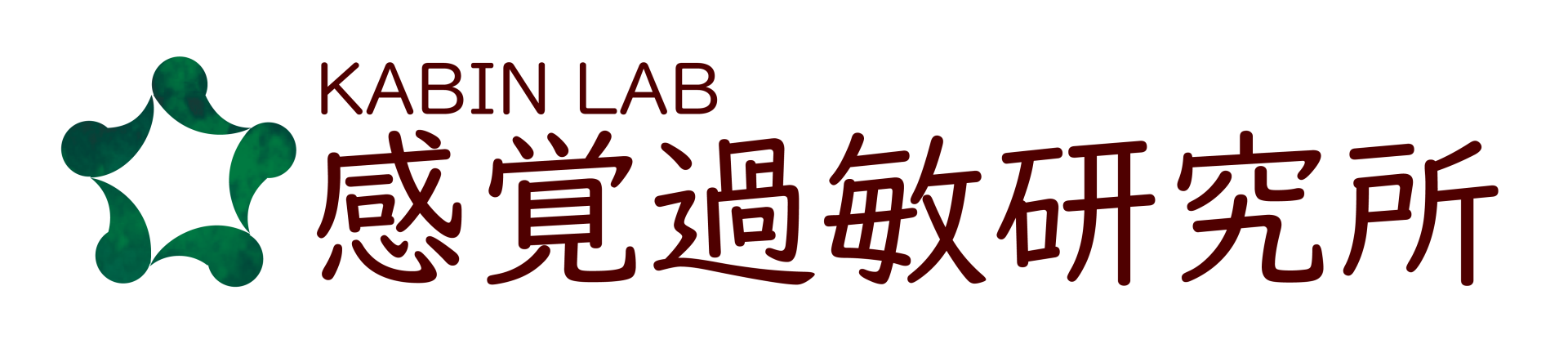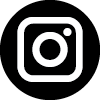みんなの脳世界2024
みんなの脳世界2024 ~超多様~
展示「みんなの脳世界2024~超多様~」を2024年10月12日(土)・13日(日)に東京都港区の東京ポートシティ1F ポートホールにて開催します。
日程
2024年10月12日(土)・13日(日)
時間
10月12日(土) 11:00〜17:00
10月13日(日) 11:00〜17:00
場所
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー1階ポートホール
東京都港区海岸1-7-1
入場料
無料
その他
「ちょっと先のおもしろい未来 –CHANGE TOMORROW-」内にて開催
5つの展示エリア
多様な世界
一人ひとりの脳は多様です。
多彩な世界
視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚。
個の拡張
私達は、見て聞いて、触ることで世界と繋がっています。そして今、テクノロジーによって私たちの力が拡がっています。
環境の調整
私たちの日常は、物理的な環境、社会的制度やルール・慣習、人間関係によって影響を受けています。
社会の創造
これまでの展示を通じて「どのような発見があったか」「ニューロダイバーシティ社会の実現に向けて、何ができるだろう?」という問いを再考します。
展示コンテンツ
「こんなにも違って見えるの?」錯視(さくし)の不思議を体験しよう(フロア番号1-3)
Why do they look so different? Let's experience the wonder of optical illusion!
自分の見え方と隣の人の見え方が違ったり、視点を変えれば他のものが見えたりする「錯視(さくし)」の不思議を体験してみましょう!「私は〇〇に見えるけど、あなたはどう見える?」とぜひ周りの人と見え方について話してみてください。同じように見えていますか?もしかしたら全く別のものに見えているのかも。この展示のように、日常生活の中でもあなたと周りの人とでは見えている世界が全く違うのかもしれません。錯視による見え方の違いと同じように、「違うこと」をポジティブに楽しみながら「超多様(ちょう たよう)」を一緒に楽しみましょう!それでは、超多様な世界へ行ってらっしゃい!
「こんなにも違って見えるの?」錯視(さくし)の不思議を体験しよう(フロア番号1-3)
Why do they look so different? Let's experience the wonder of optical illusion!
自分の見え方と隣の人の見え方が違ったり、視点を変えれば他のものが見えたりする「錯視(さくし)」の不思議を体験してみましょう!「私は〇〇に見えるけど、あなたはどう見える?」とぜひ周りの人と見え方について話してみてください。同じように見えていますか?もしかしたら全く別のものに見えているのかも。この展示のように、日常生活の中でもあなたと周りの人とでは見えている世界が全く違うのかもしれません。錯視による見え方の違いと同じように、「違うこと」をポジティブに楽しみながら「超多様(ちょう たよう)」を一緒に楽しみましょう!それでは、超多様な世界へ行ってらっしゃい!
Experience the wonder of optical illusions, where what you see may differ from what others see, or where shifting your perspective reveals something entirely new. Ask those around you, “I see this, but what do you see?” You might be surprised to find that others see something completely different. Just as in this exhibit, our everyday perceptions may vary greatly from person to person. Embrace and enjoy these differences as we explore a world of “hyper-diversity” together. Now, step into this world of infinite perspectives and enjoy the journey!
多感覚情動推定システム(フロア番号1-4)
Multimodal Emotion Estimation System
心の中にある感情を、顔に出したり言葉でうまく説明できなかったことはありませんか。神経多様性のある人の中には、自己の感情を認識して表現したり、他者の感情を読み取ることが難しい人もいます。
東京大学認知発達ロボティクス研究室
Cognitive Developmental Robotics Lab, The University of Tokyo
多感覚情動推定システム(フロア番号1-4)
Multimodal Emotion Estimation System
心の中にある感情を、顔に出したり言葉でうまく説明できなかったことはありませんか。神経多様性のある人の中には、自己の感情を認識して表現したり、他者の感情を読み取ることが難しい人もいます。
Have you ever felt emotions inside but found it difficult to recognize and/or show them on your face or express them in words? For some people—especially those with neurodiverse traits—expressing emotions outwardly can be challenging.
東京大学認知発達ロボティクス研究室
Cognitive Developmental Robotics Lab, The University of Tokyo
MEMBER
長井 志江(東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任教授)
エルブエラ ヴォンラルフディンマルケズ(東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任助教)
空気触感伝送による情動共有鑑賞体験
Emotion-sharing viewing experience with air-transmit haptic communication
「手に汗握る」という言葉があるように、何かを面白いと思ったり、すごいと思ったときには、思わず手に力が入ります。この体験では、二つのボールとそれらを結ぶチューブからなる空気触感伝送ツールを使って、心つながる展示鑑賞体験を実現します。このツールは、二つのボールのそれぞれを別の人が握り、片方のボールを強く握ると、ボールの空気がもう一方へ送られ、もう一方を持つ手の平が広げられ、力が入っているとことが生々しい触感として伝わります。ボールを持ちながら展示を回ることで、普段では気がつかない心の動きも含めて触感で気持ちをお互いに感じ合いながら、展示を体験することができます。 参考文献:渡邊ら 日本VR学会 25(4) 2020.
渡邊淳司(NTT コミュニケーション科学基礎研究所)
Junji Watanabe(NTT Communication Science Laboratories)
空気触感伝送による情動共有鑑賞体験
Emotion-sharing viewing experience with air-transmit haptic communication
「手に汗握る」という言葉があるように、何かを面白いと思ったり、すごいと思ったときには、思わず手に力が入ります。この体験では、二つのボールとそれらを結ぶチューブからなる空気触感伝送ツールを使って、心つながる展示鑑賞体験を実現します。このツールは、二つのボールのそれぞれを別の人が握り、片方のボールを強く握ると、ボールの空気がもう一方へ送られ、もう一方を持つ手の平が広げられ、力が入っているとことが生々しい触感として伝わります。ボールを持ちながら展示を回ることで、普段では気がつかない心の動きも含めて触感で気持ちをお互いに感じ合いながら、展示を体験することができます。 参考文献:渡邊ら 日本VR学会 25(4) 2020.
When we find something interesting or amazing, our hands involuntarily tense up. In this experience, an air-transmission haptic communication tool consisting of two balls and a tube connecting them is used to create an emotion-sharing experience. When a person grips one of the two balls and squeezes it hard, the air from the ball is sent to the other, causing the palm of the hand holding the other to expand. By going around the exhibition while holding the ball, visitors can experience the exhibition while feeling each other’s emotions through haptic sensations. Ref. Watanabe et al. VRSJT 25(4) 2020.
渡邊淳司(NTT コミュニケーション科学基礎研究所)
Junji Watanabe(NTT Communication Science Laboratories)
MEMBER
渡邊淳司(NTT コミュニケーション科学基礎研究所)
鼓動に触れるワークショップ「心臓ピクニック」
Heartbeat Picnic”: A workshop for touching your heartbeat
心臓は、生まれてからずっと私たちの生命活動を支えるために、休むことなく動き続けていています。「心臓ピクニック」は、その心臓を身体の外に出して、手のひらの上の触感として感じるワークショップです。自分自身の心臓はどんなふうに動いているのか、手のひらの上でじっくりと味わい、また運動したり寝転んだりしながらその変化を確かめ、さらに他の参加者と心臓を交換してその違いを感じながら対話を試みます。 参考文献:渡邊ら 日本VR学会 16(3) 2011.
渡邊淳司(NTT コミュニケーション科学基礎研究所)
Junji Watanabe(NTT Communication Science Laboratories)
鼓動に触れるワークショップ「心臓ピクニック」
Heartbeat Picnic”: A workshop for touching your heartbeat
心臓は、生まれてからずっと私たちの生命活動を支えるために、休むことなく動き続けていています。「心臓ピクニック」は、その心臓を身体の外に出して、手のひらの上の触感として感じるワークショップです。自分自身の心臓はどんなふうに動いているのか、手のひらの上でじっくりと味わい、また運動したり寝転んだりしながらその変化を確かめ、さらに他の参加者と心臓を交換してその違いを感じながら対話を試みます。 参考文献:渡邊ら 日本VR学会 16(3) 2011.
The heart has been beating without a break since birth to support our vital activities. The “Heart Picnic” is a workshop that takes the heart out of the body and lets us feel it as a haptic sensation in the palm of our hand. Participants will carefully feel how their own hearts are beating in the palm of their hands, and confirm the changes by exercising or lying down, and then exchange hearts with other participants to feel the differences and engage in a dialogue. Ref. Watanabe et al. VRSJT 16(3) 2011.
渡邊淳司(NTT コミュニケーション科学基礎研究所)
Junji Watanabe(NTT Communication Science Laboratories)
MEMBER
渡邊淳司(NTT コミュニケーション科学基礎研究所)
交差性の視点で "日常" をとらえなおす
Rethinking "everyday life" from the perspective of intersectionality
女性だから、男性だから、文系だから、理系だから、Z世代だから…そんな雑なカテゴリでの議論に、どこかモヤっとしたことはありませんか?
実践女子大学 標葉研究室
Shineha Lab., Jissen Women's University
交差性の視点で "日常" をとらえなおす
Rethinking "everyday life" from the perspective of intersectionality
女性だから、男性だから、文系だから、理系だから、Z世代だから…そんな雑なカテゴリでの議論に、どこかモヤっとしたことはありませんか?
Because you’re a woman, because you’re a man, because you’re a liberal arts student, because you’re a science student, because you’re a member of Generation Z…
実践女子大学 標葉研究室
Shineha Lab., Jissen Women's University
MEMBER
標葉靖子(実践女子大学人間社会学部社会デザイン学科 准教授)
LGBTech: VR for Therapy
LGBTech: VR for Therapy
これはLGBTQ+コミュニティのためにデザインされたVRセラピーの展示です。自分の写真からオリジナルアバターを作成し、バーチャルリアリティがメンタルヘルスのサポートをどのように変えるかを体験できます。安全で快適な環境の中で、グループセラピーの手法を探るバーチャル・ルームに浸ってください。この考え方は、LGBTQ+コミュニティが直面する課題に取り組み、ウェルネスを促進する効果的な方法を提供します。また、自分のアイデンティティを反映した空間で、本当の自分を表現することが可能です。
Minds1020Lab(横浜市立大学COI-NEXT + 慶應義塾大学KMD)
LGBTech: VR for Therapy
LGBTech: VR for Therapy
これはLGBTQ+コミュニティのためにデザインされたVRセラピーの展示です。自分の写真からオリジナルアバターを作成し、バーチャルリアリティがメンタルヘルスのサポートをどのように変えるかを体験できます。安全で快適な環境の中で、グループセラピーの手法を探るバーチャル・ルームに浸ってください。この考え方は、LGBTQ+コミュニティが直面する課題に取り組み、ウェルネスを促進する効果的な方法を提供します。また、自分のアイデンティティを反映した空間で、本当の自分を表現することが可能です。
This is a VR Therapy Exhibition designed for the LGBTQ+ community. Discover how virtual reality can transform mental health support as you create your personalized avatar from your own photos. Immerse yourself in a virtual room for exploring group therapy techniques in a safe and supportive environment. This approach offers an empowering way to address challenges faced by the LGBTQ+ community and promotes wellness, allowing you to express your true self in a space that reflects your identity.
Minds1020Lab(横浜市立大学COI-NEXT + 慶應義塾大学KMD)
MEMBER
Anish Kundu, Tanner Person, Kinga Skiers, Peng Danyang
あなたの見るもの、私の見るもの -人それぞれのコミュニケーション-
What You See and What I See: Diversity in Communication
私達は日常的に色んな人とコミュニケーションをしています。その時に、あなたの見ているものと私の見ているものはどれだけ異なっているのでしょうか。展示ではVRを使って、複数の人が参加するリアルなコミュニケーション場面を再現します。その参加者の一人となって、自閉スペクトラム症の人と、定型発達の人の視線の動きの違いを是非体験みてください。
JST未来社会創造事業 個人に最適化された社会の実現領域「ニューロダイバーシティ環境下でのコミュニケーション双方向支援」
JST-Mirai Program Society Optimized for Diversity mission area “Bidirectional communication support in neurodiverse environments”
あなたの見るもの、私の見るもの -人それぞれのコミュニケーション-
What You See and What I See: Diversity in Communication
私達は日常的に色んな人とコミュニケーションをしています。その時に、あなたの見ているものと私の見ているものはどれだけ異なっているのでしょうか。展示ではVRを使って、複数の人が参加するリアルなコミュニケーション場面を再現します。その参加者の一人となって、自閉スペクトラム症の人と、定型発達の人の視線の動きの違いを是非体験みてください。
We communicate with many people. How different is what you see and what I see? The exhibition uses VR to recreate realistic communication situations in which multiple people participate. We invite you to become one of the participants and experience the gaze directions of people with autistic spectrum disorder and those with typical development.
JST未来社会創造事業 個人に最適化された社会の実現領域「ニューロダイバーシティ環境下でのコミュニケーション双方向支援」
JST-Mirai Program Society Optimized for Diversity mission area “Bidirectional communication support in neurodiverse environments”
MEMBER
大須理英子(早稲田大学)
大須理英子(早稲田大学)
脳波で捉える「あなたのモノの見方」
EEG shows "how you perceive things."
同じ画像を見ていても、人によって、また場合によって、さまざまなモノの見方があります。
NTT人間情報研究所
NTT Human Informatics Laboratories
脳波で捉える「あなたのモノの見方」
EEG shows "how you perceive things."
同じ画像を見ていても、人によって、また場合によって、さまざまなモノの見方があります。
The same image is perceived differently by different people and in various cases. Some people look at the whole image, others focus on the details, others on the colors, others on the text…what people tend to focus on differs from person to person. It has also been found that even among the same person, what they focus on changes depending on their attitude toward what information they are trying to obtain from the image, their mood at the time, and other factors. These differences lead to differences in impressions, what is remembered, etc.
NTT人間情報研究所
NTT Human Informatics Laboratories
MEMBER
志水信哉(NTT人間情報研究所 特別研究員)
志水信哉、中根愛、太田藍李、村岡慶人、児玉大樹(NTT人間情報研究所)
身体性シミュレーション:当事者の視点から世界を見てみよう!
Embodied Simulations: Looking Through the Lens of People With Lived Experience
動物の視覚や聴覚が人間とは異なることはよく知られている。しかし、人間の視覚、聴覚、触覚もまた、年齢や性別、その他の理由によって異なることをご存知だろうか。年老いた自分、触覚の違う自分、どんな感じなのか気になりませんか?ぜひ一度、デモをご体験ください!
ムーンショット目標1 Project Cybernetic being(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)
身体性シミュレーション:当事者の視点から世界を見てみよう!
Embodied Simulations: Looking Through the Lens of People With Lived Experience
動物の視覚や聴覚が人間とは異なることはよく知られている。しかし、人間の視覚、聴覚、触覚もまた、年齢や性別、その他の理由によって異なることをご存知だろうか。年老いた自分、触覚の違う自分、どんな感じなのか気になりませんか?ぜひ一度、デモをご体験ください!
It is known that animals have different visual and hearing experience from human being. But do you know that human being also have different visual, hearing, touching experience from each other depends on their age, gender, and other reasons. Are you curious about how it feels like to be an older version of yourself, or you with a different tactile sensation? Please come experience our demonstration!
ムーンショット目標1 Project Cybernetic being(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)
MEMBER
沈襲明(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project)
裸眼立体視ディスプレイを用いた非対称コミュニケーション
Asymmetric communication with a stereoscopic display
非対称コミュニケーション,それは多様な個人にとって「心地よい」コミュニケーション空間を実現する試み.対面のコミュニケーションは,お互いに同じものを見たり聞いたりしているからといってすべての人が心地よくコミュニケーションできるとは限りません.「面と向かって話すのが苦手」,「表情を作ったり,読み解くことが苦手」,「アバターを使って話したい」,そんなことを感じている人たちのコミュニケーションをホンヤクするために裸眼立体視ディスプレイを用いて心地よいコミュニケーション空間を提供します.
東京大学先端科学技術研究センター 稲見・門内研究室
Information Somatic Laboratory, RAST, U-Tokyo
裸眼立体視ディスプレイを用いた非対称コミュニケーション
Asymmetric communication with a stereoscopic display
非対称コミュニケーション,それは多様な個人にとって「心地よい」コミュニケーション空間を実現する試み.対面のコミュニケーションは,お互いに同じものを見たり聞いたりしているからといってすべての人が心地よくコミュニケーションできるとは限りません.「面と向かって話すのが苦手」,「表情を作ったり,読み解くことが苦手」,「アバターを使って話したい」,そんなことを感じている人たちのコミュニケーションをホンヤクするために裸眼立体視ディスプレイを用いて心地よいコミュニケーション空間を提供します.
Asymmetric communication is an attempt to realize a communication space that is “comfortable” for various individuals. Face-to-face communication is not necessarily comfortable for everyone just because they see and hear the same things. We provide a comfortable communication space with a stereoscopic display for various individuals.
東京大学先端科学技術研究センター 稲見・門内研究室
Information Somatic Laboratory, RAST, U-Tokyo
MEMBER
稲見昌彦 (東京大学 先端科学技術研究センター 教授)
櫻田国治(東京大学 先端科学技術研究センター 特任助教)
立場を自由に変化させる?!「スタンスポーカー」
Stance Poker
コミュニケーションにおいて人と人の立場の違いがストレスや悩みの要因になっています。
大阪芸術大学アートサイエンス学科
Department of Art Science, Osaka University of Arts
立場を自由に変化させる?!「スタンスポーカー」
Stance Poker
コミュニケーションにおいて人と人の立場の違いがストレスや悩みの要因になっています。
Differences in people’s positions often cause stress and concerns in communication. Problems include being verbally attacked, often with harassment, by those in different positions, minority opinions being overshadowed by the majority, and physical limitations hindering effective communication. However, evolving body augmentation technologies, like avatars, are emerging not only to alleviate stress and concerns but also to transform societal norms. We have developed “realAIze,” a system that combines avatars and AI to control appearance, gestures, voice pitch, intonation, and phrasing in real-time, enabling manipulation of positions and attributes for better communication.
大阪芸術大学アートサイエンス学科
Department of Art Science, Osaka University of Arts
MEMBER
安藤英由樹(大阪芸術大学教授)
大谷智子,久保田健二,大野凪咲,西尾拓真,大川ひなた,駒井浩紀,有富伯玖,菅生恒総,中条雅仁,石田景資
違いを体験しよう!見え方の多様性(フロア番号1-1)
Biodiversity
生物によって世界がどれほど違って見えるかを体感してみませんか?人間同士であっても見え方や感じ方が違うように、人間にとって良いと思われているものが、他の生物にとっては良いものとは限らない場合があります。例えば、夜の暗い道。照明があると安心する人が多いですが、虫や植物にとってはどうでしょう。成長の妨げになる場合もあります。このように今回はクイズやアプリを通して、生物における見え方の違いを実感できます。人間だけでなく、生物全体に目を向け、見ている世界の多様さを一緒に体験してみませんか?
違いを体験しよう!見え方の多様性(フロア番号1-1)
Biodiversity
生物によって世界がどれほど違って見えるかを体感してみませんか?人間同士であっても見え方や感じ方が違うように、人間にとって良いと思われているものが、他の生物にとっては良いものとは限らない場合があります。例えば、夜の暗い道。照明があると安心する人が多いですが、虫や植物にとってはどうでしょう。成長の妨げになる場合もあります。このように今回はクイズやアプリを通して、生物における見え方の違いを実感できます。人間だけでなく、生物全体に目を向け、見ている世界の多様さを一緒に体験してみませんか?
Would you like to see the world through the eyes of different creatures? Just as humans have unique perspectives, so do other living things. Learn about biodiversity through quizzes and apps. The app allows you to explore the world from the perspective of living things, highlighting these differences. Experience the diversity of the world together by considering all living things, not just humans.
MEMBER
西本愛由(B Lab / 慶應義塾メディアデザイン研究科修士課程1年)
見えない『痛み』が見える! ぺぺぺペインカード体験
Making Invisible Pain Visible : PePePe Pain Card Experience
ムズムズ、痒い!
医学の世界では、いや~な感覚はすべて「痛み」の中の感覚だと分類されています。
見えない『痛み』が見える! ぺぺぺペインカード体験
Making Invisible Pain Visible : PePePe Pain Card Experience
ムズムズ、痒い!
医学の世界では、いや~な感覚はすべて「痛み」の中の感覚だと分類されています。
Itchy and scratchy! Stinging and burning! I’m completely exhausted…
In the medical world, all unpleasant sensations are classified as “pain.”
Join Dr. Miosin, a pain clinician, in a workshop where children recall their own “painful” experiences.
This workshop aims to enhance understanding and self-management of pain.
MEMBER
みおしん(麻酔科医TikToker&YouTuber/デジタルハリウッド大学大学院)
清野晶子(㈱電通クリエーティブプロデューサー)
ASD知覚体験シミュレータ(フロア番号2-11)
ASD Sensory Experience Simulator
外に出ると「眩しくてつらい」「目が痛い」、そんな声を耳にしたことはありませんか。自閉スペクトラム症(ASD)の人の多くは、視覚・聴覚・触覚などに感覚過敏を抱えています。ここでは、そのような感覚の困りごとを体験できる「ASD知覚体験シミュレータ」を紹介します。
東京大学認知発達ロボティクス研究室
Cognitive Developmental Robotics Lab, The University of Tokyo
ASD知覚体験シミュレータ(フロア番号2-11)
ASD Sensory Experience Simulator
外に出ると「眩しくてつらい」「目が痛い」、そんな声を耳にしたことはありませんか。自閉スペクトラム症(ASD)の人の多くは、視覚・聴覚・触覚などに感覚過敏を抱えています。ここでは、そのような感覚の困りごとを体験できる「ASD知覚体験シミュレータ」を紹介します。
Have you ever heard someone say, “It’s too bright” or “My eyes hurt” when they go outside? Many people with Autism Spectrum Disorder (ASD) experience sensory hypersensitivity in vision, hearing, and touch. Here, we introduce the ASD Sensory Experience Simulator. By quantitatively analyzing these subjective experiences, we can identify when and where sensory hypersensitivity occurs. This simulator helps us better understand how people with ASD perceive the world, why noisy places are so challenging, and why it can be difficult for them to understand others’ feelings.
東京大学認知発達ロボティクス研究室
Cognitive Developmental Robotics Lab, The University of Tokyo
MEMBER
長井 志江(東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任教授)
エルブエラ ヴォンラルフディンマルケズ(東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任助教)
脳がみている“あなたの世界”
The World as Your Brain Sees It
私たちは目で見たもので周りの状況を「わかっている」と思っていますが、実は、意識にのぼるこの状況は、あなたの脳が創り出しているものなのです。意識にのぼったことが、その実際の特性とは必ずしも一致しないことがあります。この展示では、1)数が多い、少ないという主観が実際の数とズレて感じることや、2)リズムを速く感じる、遅く感じることが状況によって変わってしまうこと、3)人の顔の見え方が簡単にくずれて見えることを、錯覚を使った実験で体験してみましょう。
国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所脳情報通信融合研究センター
National Institute of Information and Communications Technology (NICT) Advanced ICT Research Institute, Center for Information and Neural Networks (CiNet)
脳がみている“あなたの世界”
The World as Your Brain Sees It
私たちは目で見たもので周りの状況を「わかっている」と思っていますが、実は、意識にのぼるこの状況は、あなたの脳が創り出しているものなのです。意識にのぼったことが、その実際の特性とは必ずしも一致しないことがあります。この展示では、1)数が多い、少ないという主観が実際の数とズレて感じることや、2)リズムを速く感じる、遅く感じることが状況によって変わってしまうこと、3)人の顔の見え方が簡単にくずれて見えることを、錯覚を使った実験で体験してみましょう。
We often believe that we use our vision to obtain information about our surroundings and perceive situations accurately, but in reality, these perceptual experiences are constructed by the brain. What we perceive doesn’t always align with the actual physical properties of objects. In this exhibition, you will experience 1) cognitive bias, where the perceived quantity of objects differs from the actual number, 2) how the perception of rhythm speed can change depending on the situation, and 3) how easily our perception of human faces can be distorted through experiments using optical illusions.
国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所脳情報通信融合研究センター
National Institute of Information and Communications Technology (NICT) Advanced ICT Research Institute, Center for Information and Neural Networks (CiNet)
MEMBER
西堤優(国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所脳情報通信融合研究センター)
感覚探偵スタンプラリー
Sensory Detective Stamp Rally
2024年10月。ここ、竹芝の街で謎めいた連続失踪事件が発生。ある日、感覚過敏を抱える一人の少女が、突然姿を消してしまいました。彼女はその並外れた感覚を駆使し、探偵として活動していたのです。しかし、事件に巻き込まれた彼女は、感覚過敏の症状と戦いながらも、いくつものヒントを残していました。あなたの使命は彼女が残した感覚に関連するパズルや謎解きを解き明かし、スタンプを集めていくこと!それぞれの手がかりは、視覚、聴覚、嗅覚、触覚といった感覚に深く結びついています。さあ、あなたもこの感覚探偵の世界に飛び込み、少女を見つける旅に出ましょう!
Policy Project + B Lab
Policy Project + B Lab
感覚探偵スタンプラリー
Sensory Detective Stamp Rally
2024年10月。ここ、竹芝の街で謎めいた連続失踪事件が発生。ある日、感覚過敏を抱える一人の少女が、突然姿を消してしまいました。彼女はその並外れた感覚を駆使し、探偵として活動していたのです。しかし、事件に巻き込まれた彼女は、感覚過敏の症状と戦いながらも、いくつものヒントを残していました。あなたの使命は彼女が残した感覚に関連するパズルや謎解きを解き明かし、スタンプを集めていくこと!それぞれの手がかりは、視覚、聴覚、嗅覚、触覚といった感覚に深く結びついています。さあ、あなたもこの感覚探偵の世界に飛び込み、少女を見つける旅に出ましょう!
In October 2024, a series of mysterious disappearances struck Takeshiba, and a young girl with sensory hypersensitivity suddenly vanished. Using her extraordinary senses, she had worked as a detective but left behind clues despite struggling with her condition. Your mission is to solve sensory-based puzzles, gathering stamps that lead to her location. Each clue ties to sight, sound, smell, and touch, offering insight into the challenges of sensory hypersensitivity. Immerse yourself in this detective adventure, unravel the mystery, and find the missing girl before it’s too late!
Policy Project + B Lab
Policy Project + B Lab
MEMBER
西本愛由(Policy Project / 慶應義塾メディアデザイン研究科修士課程1年)
感覚統合ー様々な感覚を整理する脳の働きーをVRで体験してみよう
Experience sensory integration - the brain's function to organise the various senses - in VR
バーチャルリアリティを使って、視覚と固有受容覚の「感覚統合」ー様々な感覚を整理する脳の働きーを体験することができます。固有受容覚とは、筋肉や関節を通して、体の動きや位置を感じる感覚のことです。この展示では、ハンドリダイレクションと呼ばれる実際の手とバーチャル環境上での手であるバーチャルハンドの位置や姿勢をずらすバーチャルリアリティ技術を行うことで普段とは異なる感覚統合体験ができます。さらに、ヘッドマウントディスプレイを通して提示する視覚情報にさまざまなノイズをかけることで、感覚統合が変化する体験もできます。
東京大学 葛岡谷川鳴海研究室 株式会社クリスタルロード 感覚過敏研究所
Cyber Interface Lab. The University of Tokyo, kabin Lab. (Crystalroad Inc.)
感覚統合ー様々な感覚を整理する脳の働きーをVRで体験してみよう
Experience sensory integration - the brain's function to organise the various senses - in VR
バーチャルリアリティを使って、視覚と固有受容覚の「感覚統合」ー様々な感覚を整理する脳の働きーを体験することができます。固有受容覚とは、筋肉や関節を通して、体の動きや位置を感じる感覚のことです。この展示では、ハンドリダイレクションと呼ばれる実際の手とバーチャル環境上での手であるバーチャルハンドの位置や姿勢をずらすバーチャルリアリティ技術を行うことで普段とは異なる感覚統合体験ができます。さらに、ヘッドマウントディスプレイを通して提示する視覚情報にさまざまなノイズをかけることで、感覚統合が変化する体験もできます。
Using virtual reality, you can experience the ‘sensory integration’ of vision and proprioceptive sensation – the brain’s function to organise the various senses. Proprioceptive sensation is the sensation of movement and position of the body through the muscles and joints. In this exhibition, visitors can experience an unusual sensory integration experience through hand redirection, a virtual reality technology that shifts the position and posture of the actual hand and the virtual hand in the virtual environment. Furthermore, by applying various noises to the visual information presented through the head-mounted display, visitors can also experience a change in sensory integration.
東京大学 葛岡谷川鳴海研究室 株式会社クリスタルロード 感覚過敏研究所
Cyber Interface Lab. The University of Tokyo, kabin Lab. (Crystalroad Inc.)
MEMBER
松本啓吾(東京大学大学院情報理工学系研究科 助教)
加藤路瑛(株式会社クリスタルロード代表、感覚過敏研究所所長),畑田裕二(東京大学大学院情報学環 助教)
イベント会場内や周辺を五感を使いながら散策します。照度計や騒音計も使い、「眩しいってなんだろう?」「静かってどんなこと?」など、普段意識しない日常的な環境を考えるワークです。地図にセンサリーマップシールを貼って、自分だけのオリジナルセンサリーマップを作成します。年齢不問、どなたでもご参加いただけます。(所要時間:30分程度。参加費:500円)
株式会社クリスタルロード 感覚過敏研究所
kabin Lab. (Crystalroad Inc.)
イベント会場内や周辺を五感を使いながら散策します。照度計や騒音計も使い、「眩しいってなんだろう?」「静かってどんなこと?」など、普段意識しない日常的な環境を考えるワークです。地図にセンサリーマップシールを貼って、自分だけのオリジナルセンサリーマップを作成します。年齢不問、どなたでもご参加いただけます。(所要時間:30分程度。参加費:500円)
We will explore the event venue and its surroundings using all five senses. Using lux meters and sound level meters, we will consider everyday environments that we usually do not pay attention to, asking questions like “What does bright mean?” and “What does quiet feel like?” Participants will create their own original sensory maps by placing sensory map stickers on the provided map.
株式会社クリスタルロード 感覚過敏研究所
kabin Lab. (Crystalroad Inc.)
MEMBER
加藤路瑛(株式会社クリスタルロード代表、感覚過敏研究所所長)
はこのなかでは何がおきている?
What on earth is happening inside the box?
映像表現技術の発展により、頭の中で想像した世界を可視化して、より多くの人にそのイメージを共有することができるようになってきました。では、聴覚や触覚ではどのくらい伝わるのでしょうか?この展示では、おもに聴覚と触覚の情報から、箱の中の世界でおきていることを想像し、言葉や絵で表現して頂きます。え?中になにかいる?それはどんな姿かたちでしょうか。みんなが同じ世界をイメージするでしょうか。ぜひ体験してみてください。
NHK放送技術研究所
NHK Science & Technology Research Laboratories
はこのなかでは何がおきている?
What on earth is happening inside the box?
映像表現技術の発展により、頭の中で想像した世界を可視化して、より多くの人にそのイメージを共有することができるようになってきました。では、聴覚や触覚ではどのくらい伝わるのでしょうか?この展示では、おもに聴覚と触覚の情報から、箱の中の世界でおきていることを想像し、言葉や絵で表現して頂きます。え?中になにかいる?それはどんな姿かたちでしょうか。みんなが同じ世界をイメージするでしょうか。ぜひ体験してみてください。
With the development of visual expression technology, it has become possible to visualize the world imagined in our minds and share that image with more and more people. But how well do the senses of hearing and touch convey these images? In this exhibition, we invite you to imagine what is happening in the world inside the box, based mainly on auditory and tactile information, and express it in words and pictures. What? Is there something inside? What does it look like? Will everyone imagine the same world? Please experience it for yourself.
NHK放送技術研究所
NHK Science & Technology Research Laboratories
MEMBER
半田拓也(NHK放送技術研究所)
東真希子 柳原耕平 水谷沙耶 界瑛宏 菊地幸大 内田翼 加納正規 澤畠康仁 小峯一晃(NHK)
甘い形と苦い形 ー風味の視覚化ー
Does the Form look Sweet or Bitter? -Flavor Visualization-
味覚や視覚は全く違う感覚ですが、私たちは食べ物の風味にも視覚的な形態にも共通の印象を感じることがあります。その印象を通じて、味嗅覚で感じる食品の印象を抽象的な形で表現できるし、感じ取ることもできます。しかし、同じ食品でも全く違う味になってしまったら、印象も変わってしまうのでしょうか?実際に体験してみましょう!
立命館大学 多感覚・認知デザイン研究室
Multisensory Cognitive Design Laboratory Ritsumeikan University
甘い形と苦い形 ー風味の視覚化ー
Does the Form look Sweet or Bitter? -Flavor Visualization-
味覚や視覚は全く違う感覚ですが、私たちは食べ物の風味にも視覚的な形態にも共通の印象を感じることがあります。その印象を通じて、味嗅覚で感じる食品の印象を抽象的な形で表現できるし、感じ取ることもできます。しかし、同じ食品でも全く違う味になってしまったら、印象も変わってしまうのでしょうか?実際に体験してみましょう!
Gastation and vision are completely different senses, whereas we can feel a common impression both in flavor and visual form. If this is the case, visual form can express flavor by medium of impression. BTW, if the identical food tastes completely different, does that change our impressions of the food? Let’s try it!
立命館大学 多感覚・認知デザイン研究室
Multisensory Cognitive Design Laboratory Ritsumeikan University
意識と無意識を感じてみよう
Let's feel consciousness and unconsciousness.
無意識ではうまくできていたのに、意識し始めた途端にうまくいかなくなること、ありませんか?たとえば、普段は簡単にゴミをゴミ箱に投げ入れられるのに、成功や失敗を意識すると急に入らなくなることがあります。実は、これと同じようなことが、我々が身体を動かす際にも起こり、意識すればするほど動きがぎこちなくなる、もしくは動かなくなってしまうことがあるのです。私たちは、このように意識が正常な動きを妨げる現象を、うまくサポートすることで、無意識の能力を引き出す方法を探っています。今日は、意識すればするほどできなくなるのに、ふと無意識になると成功する、そんな不思議な体験をしてみましょう。
産業技術総合研究所
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
意識と無意識を感じてみよう
Let's feel consciousness and unconsciousness.
無意識ではうまくできていたのに、意識し始めた途端にうまくいかなくなること、ありませんか?たとえば、普段は簡単にゴミをゴミ箱に投げ入れられるのに、成功や失敗を意識すると急に入らなくなることがあります。実は、これと同じようなことが、我々が身体を動かす際にも起こり、意識すればするほど動きがぎこちなくなる、もしくは動かなくなってしまうことがあるのです。私たちは、このように意識が正常な動きを妨げる現象を、うまくサポートすることで、無意識の能力を引き出す方法を探っています。今日は、意識すればするほどできなくなるのに、ふと無意識になると成功する、そんな不思議な体験をしてみましょう。
Have you ever noticed that something you could do effortlessly becomes difficult at the moment you start thinking about it? For example, you might easily toss trash into a bin without a second thought, but as soon as you focus on succeeding, you suddenly miss. The same thing can happen when we move our bodies— the more we concentrate, the more awkward or even paralyzed our movements become. We are exploring ways to support people in overcoming this phenomenon, helping them unlock their unconscious abilities. Today, let’s experience the curious sensation of succeeding when you stop trying so hard.
産業技術総合研究所
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
MEMBER
村井昭彦(産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究チーム長)
鮎澤光,松原晟都,宮脇裕,Alvaro Costa Garcia,加地智哉,下田真吾,平田仁,上田彩子
触覚は、私たちがモノの形や素材感、熱さや冷たさ、痛みを感じるために重要な感覚です。触覚の鋭敏さを測定し、個々の触覚特性を理解することを目的とした触力検査では、触覚が敏感すぎる人や感じにくい人の状態や特性を把握できます。これにより、生活をより快適にするためのサポートが考えられるようになります。たとえば、視力検査が目の状態を知り、適切な眼鏡や対処法を見つける手助けをするのと同様に、触力検査も触覚の状態に応じた適切な対策を見つける手助けをしてくれます。触力検査に参加して、自分の触覚について知ってみましょう!
B Lab +名古屋工業大学ハプティクス研究室/稲盛科学研究機構+慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project + 株式会社NTTドコモ
触覚は、私たちがモノの形や素材感、熱さや冷たさ、痛みを感じるために重要な感覚です。触覚の鋭敏さを測定し、個々の触覚特性を理解することを目的とした触力検査では、触覚が敏感すぎる人や感じにくい人の状態や特性を把握できます。これにより、生活をより快適にするためのサポートが考えられるようになります。たとえば、視力検査が目の状態を知り、適切な眼鏡や対処法を見つける手助けをするのと同様に、触力検査も触覚の状態に応じた適切な対策を見つける手助けをしてくれます。触力検査に参加して、自分の触覚について知ってみましょう!
B Lab +名古屋工業大学ハプティクス研究室/稲盛科学研究機構+慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project + 株式会社NTTドコモ
見たい景色を音で感じてみよう
Let's feel the scenery through sound!
皆さんが普段聴いている音は、360度の全方向から、無数の音が複雑に組み合わさったものです。その聴こえ方は、音そのものの広がり方や部屋や物の配置によって大きく変わります。もし聴こえてくる範囲を150度や60度に絞ることができたら、どうなるでしょう。この体験では、360度動画と合わせて、思い通りの範囲の音を立体的に聴くことができます。タッチパネルを操作して、あなた好みの音の景色を探してみましょう。
株式会社KDDI総合研究所
KDDI Research, Inc.
見たい景色を音で感じてみよう
Let's feel the scenery through sound!
皆さんが普段聴いている音は、360度の全方向から、無数の音が複雑に組み合わさったものです。その聴こえ方は、音そのものの広がり方や部屋や物の配置によって大きく変わります。もし聴こえてくる範囲を150度や60度に絞ることができたら、どうなるでしょう。この体験では、360度動画と合わせて、思い通りの範囲の音を立体的に聴くことができます。タッチパネルを操作して、あなた好みの音の景色を探してみましょう。
The sounds you usually hear are a complex mixture of countless sounds coming from all directions in a 360-degree space. How you perceive these sounds can vary greatly based on the way the sound spreads, as well as the arrangement of the room and objects within it. What would happen if you could narrow the range of sounds to 150 degrees or 60 degrees? In this experience, you can listen to sounds in three dimensions within your desired range, accompanied by 360-degree video. Use the touch panel to explore the scenery of sounds that suit your preferences.
株式会社KDDI総合研究所
KDDI Research, Inc.
MEMBER
谷地卓(株式会社KDDI総合研究所)
スライドリフト(フロア番号5-7)
SlideRift
電動アシストにより全方向移動及びドリフト運動が可能な車椅子型身体拡張器具を用いて、下肢の身体的多様性を問わず新たな運動能力を楽しむことが可能なレース競技を実施します。
AXEREAL株式会社・超人スポーツプロジェクト
AXEREAL,inc. / Superhuman Sports Project
スライドリフト(フロア番号5-7)
SlideRift
電動アシストにより全方向移動及びドリフト運動が可能な車椅子型身体拡張器具を用いて、下肢の身体的多様性を問わず新たな運動能力を楽しむことが可能なレース競技を実施します。
Using a wheelchair-type body extension device equipped with electric assist that allows omnidirectional movement and drifting, we will conduct a racing competition where participants can enjoy new athletic abilities regardless of lower limb physical diversity.
AXEREAL株式会社・超人スポーツプロジェクト
AXEREAL,inc. / Superhuman Sports Project
MEMBER
安藤良一(AXEREAL株式会社代表取締役 超人スポーツプロジェクト事務局長)
スピリットオーバーフロー
SpiritOverflow
Spirit Overflowはバイクベースのテリトリーバトルです。老若男女、障がいの有無や地理的拘束を超える、情報処理社会の新たなスポーツ、Figital Sportsを是非お楽しみください!
AXEREAL株式会社・超人スポーツプロジェクト
AXEREAL,inc. / Superhuman Sports Project
スピリットオーバーフロー
SpiritOverflow
Spirit Overflowはバイクベースのテリトリーバトルです。老若男女、障がいの有無や地理的拘束を超える、情報処理社会の新たなスポーツ、Figital Sportsを是非お楽しみください!
Spirit Overflow is a territory battle based on biking. Enjoy Figital Sports, a new sport of the information processing society that transcends age, gender, disability, and geographical constraints! Spirit Overflow aims to merge an authentic esports experience with high-intensity bike workouts.
AXEREAL株式会社・超人スポーツプロジェクト
AXEREAL,inc. / Superhuman Sports Project
MEMBER
安藤良一(AXEREAL株式会社代表取締役 超人スポーツプロジェクト事務局長)
体を傾けるとドリフト移動するカラダ(Sli de Rift – Seahare)を装着し、フィールドに次々現れる「カク」という光を素早く捉え、制限時間に捉えたカクの数を競うゲーム。
AXEREAL株式会社・超人スポーツプロジェクト
AXEREAL,inc. / Superhuman Sports Project
体を傾けるとドリフト移動するカラダ(Sli de Rift – Seahare)を装着し、フィールドに次々現れる「カク」という光を素早く捉え、制限時間に捉えたカクの数を競うゲーム。
Wearing the body extension device (Sli de Rift – Seahare) that enables drifting movement when you tilt your body, you will compete to quickly capture lights called ‘Kaku’ that appear sequentially on the field, aiming to capture as many as possible within the time limit. The key to victory lies in precise control of your centre of gravity and quick reflexes. Each ‘Kaku’ you capture presents a new challenge, testing your bodily control skills and mental resilience. Challenge your limits and aim for the highest score. Enjoy the new sport of the information processing society, Figital Sports!
AXEREAL株式会社・超人スポーツプロジェクト
AXEREAL,inc. / Superhuman Sports Project
MEMBER
安藤良一(AXEREAL株式会社代表取締役 超人スポーツプロジェクト事務局長)
2050年には、自分ではない他者の立場や経験を自分の身体で経験することで、自分ごととして感じたり、考えたりすることができるようになります。
アバターを通じて誰かの人生(ライフヒストリー)を追体験してみましょう。自分とは違う立場や境遇を体感することで、自分の過去・現在・未来を見つめ直したり、その人生の持ち主との対話が促されたり、新たな人生経験の気づきが得られたり、より多彩な人生を歩む
きっかけになるかもしれません。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 東京大学 葛岡・谷川・鳴海研究室
2050年には、自分ではない他者の立場や経験を自分の身体で経験することで、自分ごととして感じたり、考えたりすることができるようになります。
アバターを通じて誰かの人生(ライフヒストリー)を追体験してみましょう。自分とは違う立場や境遇を体感することで、自分の過去・現在・未来を見つめ直したり、その人生の持ち主との対話が促されたり、新たな人生経験の気づきが得られたり、より多彩な人生を歩む
きっかけになるかもしれません。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 東京大学 葛岡・谷川・鳴海研究室
2050年には、ロボットの能力と人間の創造性による共創によって、誰もがスポーツや芸術で突出した能力や独自の世界観を発揮できる未来がやってきます。
まるで自分の身体の一部のように滑らかに動くロボットを通じて、AIとの共創により新たな能力を獲得し、これまでの自分にはできないと思っていたことができるようになります。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 明治大学 複雑ロボットシステム研究室、Sony CSL、東海大学観光学部佐藤研究室
2050年には、ロボットの能力と人間の創造性による共創によって、誰もがスポーツや芸術で突出した能力や独自の世界観を発揮できる未来がやってきます。
まるで自分の身体の一部のように滑らかに動くロボットを通じて、AIとの共創により新たな能力を獲得し、これまでの自分にはできないと思っていたことができるようになります。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 明治大学 複雑ロボットシステム研究室、Sony CSL、東海大学観光学部佐藤研究室
2050年、サイバネティック・アバターと人とは高度な身体感覚でつながり、ロボットやバーチャルな身体を通じた体験を、全身で経験できるようになります。
様々な形状に変容する身体を得たとき、私たちはそれをどのように感じ、どのように行動するのでしょうか。 全身触覚チェア「Synesthesia X1」はそのような時代の到来を予感させる、人とサイバネティック・アバターとの新たなインタフェースです。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project、Enhance Experience Inc.、Synesthesia Lab
2050年、サイバネティック・アバターと人とは高度な身体感覚でつながり、ロボットやバーチャルな身体を通じた体験を、全身で経験できるようになります。
様々な形状に変容する身体を得たとき、私たちはそれをどのように感じ、どのように行動するのでしょうか。 全身触覚チェア「Synesthesia X1」はそのような時代の到来を予感させる、人とサイバネティック・アバターとの新たなインタフェースです。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project、Enhance Experience Inc.、Synesthesia Lab
2050年、テクノロジーによって進化した生活空間は、人々の経験を記録・保存し、再生するための新たなインタフェースとなります。
他者の経験を時間と空間を超えて共有できる未来では、人と空間との関わりに、より豊かな身体性がもたらされます。床を通じて触覚的な体験を記録・再生する「HaptoRoom」で、未来への一歩を踏み出してみましょう。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project
2050年、テクノロジーによって進化した生活空間は、人々の経験を記録・保存し、再生するための新たなインタフェースとなります。
他者の経験を時間と空間を超えて共有できる未来では、人と空間との関わりに、より豊かな身体性がもたらされます。床を通じて触覚的な体験を記録・再生する「HaptoRoom」で、未来への一歩を踏み出してみましょう。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project
2050年、私たちは身体感覚を共有することで、リアルとバーチャルの境界が溶け合った空間で生活を送っています。
そのとき、私たちはどのように情報を伝え合うのでしょうか。触り心地や力の感覚を伝える「FEEL TECH Wear」は、現実世界の体験を拡張し、言葉では伝わらない、これまで想像することしかできなかった「触覚」の世界に直接触れることを可能にします。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project、株式会社NTTドコモ、株式会社commissure、株式会社SPLINE DESIGN HUB
2050年、私たちは身体感覚を共有することで、リアルとバーチャルの境界が溶け合った空間で生活を送っています。
そのとき、私たちはどのように情報を伝え合うのでしょうか。触り心地や力の感覚を伝える「FEEL TECH Wear」は、現実世界の体験を拡張し、言葉では伝わらない、これまで想像することしかできなかった「触覚」の世界に直接触れることを可能にします。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project、株式会社NTTドコモ、株式会社commissure、株式会社SPLINE DESIGN HUB
2050年には、他者と能力を共有することで、年齢や病気など関係なく助け合え、いつでもチャレンジできる社会がやってきます。
感覚刺激を提示する装置で、他者の感覚を受け取りながら、2人でドラムセッションを行います。このように身体能力を共有することで、息の合ったパフォーマンスを発揮でき、衰えゆく身体状態であるフレイルの予防や幼児期の教育に役立ちます。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 名古屋工業大学ハプティクス研究室、名古屋大学大学院医学系研究科、東海大学観光学部佐藤研究室
2050年には、他者と能力を共有することで、年齢や病気など関係なく助け合え、いつでもチャレンジできる社会がやってきます。
感覚刺激を提示する装置で、他者の感覚を受け取りながら、2人でドラムセッションを行います。このように身体能力を共有することで、息の合ったパフォーマンスを発揮でき、衰えゆく身体状態であるフレイルの予防や幼児期の教育に役立ちます。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 名古屋工業大学ハプティクス研究室、名古屋大学大学院医学系研究科、東海大学観光学部佐藤研究室
身体感覚を他者と共有することで、より高い能力や創造性を発揮できる時代が2050年には到来します。
得意なことは掛け合わせ、苦手なことは補い合うことで、新しい能力をあっという間に学べる未来が実現します。 複数人で連携して操作するロボットを通じて、能力を補うだけではなく、元の能力を遥かに超える技や感性など、1 + 1 > 2になる共創を生み出します。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 名古屋工業大学ハプティクス研究室、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project、一般社団法人日本工芸産地協会、有限会社育陶園
身体感覚を他者と共有することで、より高い能力や創造性を発揮できる時代が2050年には到来します。
得意なことは掛け合わせ、苦手なことは補い合うことで、新しい能力をあっという間に学べる未来が実現します。 複数人で連携して操作するロボットを通じて、能力を補うだけではなく、元の能力を遥かに超える技や感性など、1 + 1 > 2になる共創を生み出します。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 名古屋工業大学ハプティクス研究室、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project、一般社団法人日本工芸産地協会、有限会社育陶園
2050年には、人は身体を拡張する技術により、障害を乗り越えて行動することができるようになります。
拡張された身体を自らの意思で動かし、家族や周囲の人と触れ合える未来が訪れます。「Brain Body Jockey Project」は、脳波を用いて動かせるアームによって、重度の障害があったとしても想いを実際の行動で伝え合える、新たな日常を提案します。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project、一般社団法人WITH ALS、株式会社オリィ研究所、NOUPATHY、東京大学、株式会社電通サイエンスジャム
2050年には、人は身体を拡張する技術により、障害を乗り越えて行動することができるようになります。
拡張された身体を自らの意思で動かし、家族や周囲の人と触れ合える未来が訪れます。「Brain Body Jockey Project」は、脳波を用いて動かせるアームによって、重度の障害があったとしても想いを実際の行動で伝え合える、新たな日常を提案します。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project、一般社団法人WITH ALS、株式会社オリィ研究所、NOUPATHY、東京大学、株式会社電通サイエンスジャム
2050年の社会では、サイバネティック・アバターを用いることで、障害の有無に依らず、場所を問わず、誰でも人と関わり活躍できるようになります。
国内外から毎月何千人もの人が訪れる分身ロボットカフェDAWN ver.βでは、ALS、SMAなどをはじめ様々な理由による移動困難者が分身ロボットOriHimeを操縦し、接客をしています。自宅にいながら店内の分身ロボットを操り、人と接していきいきと働く姿は、身体的制約を乗り越えられる新時代の到来を感じさせます。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 株式会社オリィ研究所
2050年の社会では、サイバネティック・アバターを用いることで、障害の有無に依らず、場所を問わず、誰でも人と関わり活躍できるようになります。
国内外から毎月何千人もの人が訪れる分身ロボットカフェDAWN ver.βでは、ALS、SMAなどをはじめ様々な理由による移動困難者が分身ロボットOriHimeを操縦し、接客をしています。自宅にいながら店内の分身ロボットを操り、人と接していきいきと働く姿は、身体的制約を乗り越えられる新時代の到来を感じさせます。
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being) 株式会社オリィ研究所
リアルとバーチャル、親子で協力!
Parent-child bonding between real and virtual worlds.
このワークショップでは、親子で力を合わせてバーチャル世界の冒険に挑戦します。親はバーチャルな世界に飛び込み、1人でミッションに挑戦します。一方で子どもは強力な能力を得て、外から親をサポートします。「次はあっちだよ!」と道を教えたり、危険が迫ったときに「気をつけて!」と守ってあげたり、普段とは少し違った親子の絆を感じながら、2人で世界を攻略しましょう。
東京大学 葛岡・谷川・鳴海研究室
Cyber Interface Lab, The University of Tokyo
リアルとバーチャル、親子で協力!
Parent-child bonding between real and virtual worlds.
このワークショップでは、親子で力を合わせてバーチャル世界の冒険に挑戦します。親はバーチャルな世界に飛び込み、1人でミッションに挑戦します。一方で子どもは強力な能力を得て、外から親をサポートします。「次はあっちだよ!」と道を教えたり、危険が迫ったときに「気をつけて!」と守ってあげたり、普段とは少し違った親子の絆を感じながら、2人で世界を攻略しましょう。
In this workshop, parents and children work together in a virtual world adventure. The parent is immersed in the virtual world and takes on the mission alone. Meanwhile, the child gains powerful abilities and supports the parent from the real environment. The child shows the parent the way or protects the parent in times of danger. Now, conquer the world with a slightly different parent-child bond!
東京大学 葛岡・谷川・鳴海研究室
Cyber Interface Lab, The University of Tokyo
脳波レーシングゲーム
Brainwave Speedway
私たちは、大脳皮質の神経細胞を流れる電気信号を使って情報をやり取りすることで、考えたり、感じたり、動いたりすることができます。その電気信号は波として頭皮から計測することができます。脳波といいます。この波にはいくつかの種類があり、10Hz前後の波を「アルファ波」と呼びます。集中することで信号が小さくなるアルファ波で、レーシングゲームの車を運転してください。さあ、みなさん、集中です!
国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所脳情報通信融合研究センター
National Institute of Information and Communications Technology (NICT) Advanced ICT Research Institute, Center for Information and Neural Networks (CiNet)
脳波レーシングゲーム
Brainwave Speedway
私たちは、大脳皮質の神経細胞を流れる電気信号を使って情報をやり取りすることで、考えたり、感じたり、動いたりすることができます。その電気信号は波として頭皮から計測することができます。脳波といいます。この波にはいくつかの種類があり、10Hz前後の波を「アルファ波」と呼びます。集中することで信号が小さくなるアルファ波で、レーシングゲームの車を運転してください。さあ、みなさん、集中です!
Our ability to think, feel and move is based on the exchange of information using electrical signals that flow through the nerve cells of the cerebral cortex. These electrical signals can be measured from the scalp as waves. They are called brain waves. There are several types of these waves, with waves around 10 Hz being called “alpha waves”. You can drive a car in a racing game with alpha waves, where the signal is weakened by concentrating. Let’s try it out!
国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所脳情報通信融合研究センター
National Institute of Information and Communications Technology (NICT) Advanced ICT Research Institute, Center for Information and Neural Networks (CiNet)
MEMBER
西堤優(国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所脳情報通信融合研究センター)
"脳波でゲームを操作しよう! "
Let's play a game with EEG!
この展示では、運動をイメージしているときのあなたの脳活動(脳波)を計ります。
NTT人間情報研究所
NTT Human Informatics Laboratories
"脳波でゲームを操作しよう! "
Let's play a game with EEG!
この展示では、運動をイメージしているときのあなたの脳活動(脳波)を計ります。
In this exhibit, we measure your brain activity (EEG) when you are imagining a movement.
NTT人間情報研究所
NTT Human Informatics Laboratories
MEMBER
志水信哉(NTT人間情報研究所 特別研究員)
小池幸生、沖津健吾、伊勢崎隆司、神田琢也、村上由美(NTT人間情報研究所)
色のめがね・色のシミュレータ
Chromatic Glass, Chromatic Vision Simulator
「色のめがね」は、色覚異常などが原因で、色が見えにくい、色を見分けにくい人のための色覚補助ツールです。科学的な理論に基づき、見えにくい色の一部をリアルタイムに見えやすい色に変更することによって、色をわかりやすくします。「色のシミュレータ」は、様々な色覚特性を持つ人の色の見え方を体験するための色覚シミュレーションツールです。それぞれの色覚タイプではどのように色が見えるのか、シミュレーションを行います。
株式会社ハウディ/ViXion株式会社
Haudi, Inc./ViXion Inc.
色のめがね・色のシミュレータ
Chromatic Glass, Chromatic Vision Simulator
「色のめがね」は、色覚異常などが原因で、色が見えにくい、色を見分けにくい人のための色覚補助ツールです。科学的な理論に基づき、見えにくい色の一部をリアルタイムに見えやすい色に変更することによって、色をわかりやすくします。「色のシミュレータ」は、様々な色覚特性を持つ人の色の見え方を体験するための色覚シミュレーションツールです。それぞれの色覚タイプではどのように色が見えるのか、シミュレーションを行います。
“Chromatic Glass” is a color vision aid for people who have difficulty seeing or distinguishing colors due to color blindness. Based on scientific theory, it makes colors easier to understand by changing some of the hard-to-see colors to easier-to-see colors in real time. The “Chromatic Vision Simulator” is a color vision simulation tool to experience how people with various color vision characteristics see colors. It simulates how colors are seen by each color vision type.
株式会社ハウディ/ViXion株式会社
Haudi, Inc./ViXion Inc.
MEMBER
浅田 一憲
浅田一憲(株式会社ハウディ/ViXion株式会社)
「ジザイ・フェイス」は自由自在に遊べる人工身体部位である。玩具のような見た目の眼・眉・口・鼻・耳といった「顔パーツ」をそこらじゅうにくっつけて、自分の身体の延長・代替として存在させることができる。無線カメラが仕込まれた「ジザイ・アイ」は、瞼がパチパチ開閉して存在感抜群。文字通り自分の眼を増やせる。無線スピーカーが内蔵された「ジザイ・マウス」も唇開閉機能を搭載。自分の口の代わりにペチャクチャ喋ってくれる。自分の身体に装着したら、沢山の顔パーツを持った「バケモノ」になれる。誰かの身体に装着すれば、まるでその人に憑依するような体験を作れる。家具や家電にくっつければ、物を生き物のようにアレンジできる。
東京大学先端科学技術研究センター 稲見・門内研究室
Information Somatic Laboratory, RAST, U-Tokyo
「ジザイ・フェイス」は自由自在に遊べる人工身体部位である。玩具のような見た目の眼・眉・口・鼻・耳といった「顔パーツ」をそこらじゅうにくっつけて、自分の身体の延長・代替として存在させることができる。無線カメラが仕込まれた「ジザイ・アイ」は、瞼がパチパチ開閉して存在感抜群。文字通り自分の眼を増やせる。無線スピーカーが内蔵された「ジザイ・マウス」も唇開閉機能を搭載。自分の口の代わりにペチャクチャ喋ってくれる。自分の身体に装着したら、沢山の顔パーツを持った「バケモノ」になれる。誰かの身体に装着すれば、まるでその人に憑依するような体験を作れる。家具や家電にくっつければ、物を生き物のようにアレンジできる。
JIZAI Face is a set of toy-like devices representing the human facial parts: eyes, mouth, nose, and ears. JIZAI, a Japanese term, means the state in which one freely operates oneself and the things surrounding him/her. JIZAI Facial Parts can be attached everywhere and exist as external or alternative facial parts.
東京大学先端科学技術研究センター 稲見・門内研究室
Information Somatic Laboratory, RAST, U-Tokyo
MEMBER
稲見昌彦 (東京大学 先端科学技術研究センター 教授)
瓜生大輔(東京大学 先端科学技術研究センター 客員研究員、芝浦工業大学 デザイン工学部 デザイン工学科 助教)
個人の拡張ってどういうこと?
What is personal extension?
あなたはどんな理由で眼鏡をかけていますか?眼鏡は個人の視力を補助するための道具として生まれましたが、時代の変化に伴って変化する人々の要求に応えるアイテムとしてその役割を広げてきました。
個人の拡張ってどういうこと?
What is personal extension?
あなたはどんな理由で眼鏡をかけていますか?眼鏡は個人の視力を補助するための道具として生まれましたが、時代の変化に伴って変化する人々の要求に応えるアイテムとしてその役割を広げてきました。
For what reason do you wear eyeglasses? Eyeglasses originated as a tool to aid an individual’s vision, but they have expanded their role. Today, there are glasses that block blue light and ultraviolet rays and glasses that read text when you wear them. In addition, many people enjoy customizing the frames of their eyeglasses, wearing date glasses and colored sunglasses as a part of fashion. Technology has the potential to not only complement and assist the individual, but to extend the individual and become part of the individual’s personal tastes and preferences.
スライドリフト(フロア番号5-7)
SlideRift
電動アシストにより全方向移動及びドリフト運動が可能な車椅子型身体拡張器具を用いて、下肢の身体的多様性を問わず新たな運動能力を楽しむことが可能なレース競技を実施します。
AXEREAL株式会社・超人スポーツプロジェクト
AXEREAL,inc. / Superhuman Sports Project
スライドリフト(フロア番号5-7)
SlideRift
電動アシストにより全方向移動及びドリフト運動が可能な車椅子型身体拡張器具を用いて、下肢の身体的多様性を問わず新たな運動能力を楽しむことが可能なレース競技を実施します。
Using a wheelchair-type body extension device equipped with electric assist that allows omnidirectional movement and drifting, we will conduct a racing competition where participants can enjoy new athletic abilities regardless of lower limb physical diversity.
AXEREAL株式会社・超人スポーツプロジェクト
AXEREAL,inc. / Superhuman Sports Project
信号機が赤・青じゃなかったら?(フロア番号4-2)
What if Traffic Lights Weren't Red and Green?
日常で見ている赤、黄、青の信号機。しかし、人によってはこれらの色が違う風に見えているかもしれません。このブースでは、「自分の普通」の視点とは異なる視点から信号機の色がどのように見えているのかを知り、環境側から変えていくということを考えるきっかけを提供します。ではどんな色ならみんなにとって見やすい・見にくいのだろう?是非、このブースで信号機の色の違いを新しい視点から体験し、多様な視点を持つ私たちみんなに優しい未来の社会を一緒に考えてみませんか?
信号機が赤・青じゃなかったら?(フロア番号4-2)
What if Traffic Lights Weren't Red and Green?
日常で見ている赤、黄、青の信号機。しかし、人によってはこれらの色が違う風に見えているかもしれません。このブースでは、「自分の普通」の視点とは異なる視点から信号機の色がどのように見えているのかを知り、環境側から変えていくということを考えるきっかけを提供します。ではどんな色ならみんなにとって見やすい・見にくいのだろう?是非、このブースで信号機の色の違いを新しい視点から体験し、多様な視点を持つ私たちみんなに優しい未来の社会を一緒に考えてみませんか?
The familiar red, yellow, and green traffic lights we see every day. However, for some, these colors might appear differently. At this booth, we invite you to understand how traffic light colors might be perceived from a perspective different from “your normal” and to consider the possibility of making changes from the environment’s side. What colors would be easy or difficult for everyone to see? Come and experience these variations in traffic light colors from a new perspective at our booth. Let’s think together about a future society that’s kinder to all of our diverse viewpoints.
みんなにやさしい自動ドア ミライロドア
MIRAIRO DOOR The inclusive automatic doors
これまでの自動ドアはセンサー技術の進歩などにより安全性を高めてきました。一方、どのような人が通る時も同じタイミング、同じ速度で開閉するため、障がいのある方やベビーカーを使う方がスムーズに通行できず、不便や不安を与えてしまうことがありました。
株式会社ハウディ フルテック株式会社 株式会社ミライロ
Haudi, Inc. Fulltech INC. Mirairo Inc.
みんなにやさしい自動ドア ミライロドア
MIRAIRO DOOR The inclusive automatic doors
これまでの自動ドアはセンサー技術の進歩などにより安全性を高めてきました。一方、どのような人が通る時も同じタイミング、同じ速度で開閉するため、障がいのある方やベビーカーを使う方がスムーズに通行できず、不便や不安を与えてしまうことがありました。
We introduce our MIRAIRO DOOR, the inclusive automatic doors to all of you.
株式会社ハウディ フルテック株式会社 株式会社ミライロ
Haudi, Inc. Fulltech INC. Mirairo Inc.
MEMBER
浅田風太(株式会社ハウディ 代表取締役)
浅田一憲、浅田風太、永山純一、小山内大輔、伊藤将太郎、鯉沼海太、安部徹(株式会社ハウディ)
古野元昭、高杉義幸、長門誠、三澤樹、渡部浩二、亀井哲郎(フルテック株式会社)
あつまれおんがくの森
Gathering in the music forest
「あつまれおんがくの森」ブースでは、メタバース空間を利用した多彩な音楽体験を楽しめます。音楽の起源に想いを馳せながら、森の中で音を楽しんだ祖先たちのように、現代の技術で音の楽しさとつながりを感じることができます。多様なリズム、多彩なメロディ、個性豊かな表現、心地よい音の空間、みんなで創る音の世界を体験できる展示です。子供から大人まで、誰でも楽しく参加し、音楽の力を感じながら、新しい仲間とのつながりを楽しむことができます。
Minds1020Lab(横浜市立大学COI-NEXT)
Minds1020Lab(YCU COI-NEXT)
あつまれおんがくの森
Gathering in the music forest
「あつまれおんがくの森」ブースでは、メタバース空間を利用した多彩な音楽体験を楽しめます。音楽の起源に想いを馳せながら、森の中で音を楽しんだ祖先たちのように、現代の技術で音の楽しさとつながりを感じることができます。多様なリズム、多彩なメロディ、個性豊かな表現、心地よい音の空間、みんなで創る音の世界を体験できる展示です。子供から大人まで、誰でも楽しく参加し、音楽の力を感じながら、新しい仲間とのつながりを楽しむことができます。
The “Gathering in the Music Forest” booth offers a captivating musical experience in a metaverse space. Drawing inspiration from the origins of music, visitors can immerse themselves in the joy and connection our ancestors felt in forests, brought to life through sound and technology. The exhibit features diverse rhythms, colorful melodies, unique expressions, soothing soundscapes, and a collaborative musical world. Designed for visitors of all ages, this engaging exhibit provides a unique opportunity to enjoy music and connect with new friends.
Minds1020Lab(横浜市立大学COI-NEXT)
Minds1020Lab(YCU COI-NEXT)
MEMBER
宮﨑智之(横浜市立大学研究・産学連携推進センター教授/横浜市立大学COI-NEXTプロジェクトリーダー)
藤井進也(慶應義塾大学環境情報学部准教授)
環境によって変わるってどういうこと? (フロア番号4-1)
How does the environment affect it?
この展示では、環境の変化が個人の強みや弱みにどのように影響するかを体感します。馴染みのある丸い車輪の三輪車と、あんまり目にすることのない四角い車輪の三輪車が用意されています。平坦な地面を走ろうとすると丸い車輪の三輪車の方がよく前に進みますが、では凹凸のある地面ではどうでしょう?その結果は驚きかもしれません。私たち個人の特性は変わらずとも、環境が変わればその特性はどう生きるのでしょうか。体験してみましょう!
環境によって変わるってどういうこと? (フロア番号4-1)
How does the environment affect it?
この展示では、環境の変化が個人の強みや弱みにどのように影響するかを体感します。馴染みのある丸い車輪の三輪車と、あんまり目にすることのない四角い車輪の三輪車が用意されています。平坦な地面を走ろうとすると丸い車輪の三輪車の方がよく前に進みますが、では凹凸のある地面ではどうでしょう?その結果は驚きかもしれません。私たち個人の特性は変わらずとも、環境が変わればその特性はどう生きるのでしょうか。体験してみましょう!
In this exhibit, you will experience how changes in the environment impact an individual’s strengths and weaknesses. We have provided both a familiar tricycle with wheels and a less commonly seen tricycle with square wheels. While the tricycle with wheels moves forward better on flat ground, how about on uneven terrain? The result might surprise you. Even if our characteristics remain unchanged, how will they manifest when the environment shifts? Come and find out for yourself!
和文化スヌーズレン
Japanese Cultural Snoezelen
五感で癒される和の体験をしてみませんか?和文化スヌーズレンは茶室をコンセプトとした空間にて日々のストレスや疲れを忘れ、心をリラックスさせられる時間を提供します。スヌーズレンとは様々な感覚を刺激することで、リラクゼーションと探索の効果がある空間です。和文化スヌーズレンではここに「静」の和文化を取り入れることで、心を落ち着かせられる狙いがあります。和文化に触れながら、照明や触り心地など自分の好きな感覚を探すこともできます。茶室の戸を引いて、現実を忘れる至福の時間を体験しませんか?「和文化スヌーズレンルーム」で心と体をリフレッシュし、日常に新たなエネルギーを見つけましょう。
Policy Project + B Lab
Policy Project + B Lab
和文化スヌーズレン
Japanese Cultural Snoezelen
五感で癒される和の体験をしてみませんか?和文化スヌーズレンは茶室をコンセプトとした空間にて日々のストレスや疲れを忘れ、心をリラックスさせられる時間を提供します。スヌーズレンとは様々な感覚を刺激することで、リラクゼーションと探索の効果がある空間です。和文化スヌーズレンではここに「静」の和文化を取り入れることで、心を落ち着かせられる狙いがあります。和文化に触れながら、照明や触り心地など自分の好きな感覚を探すこともできます。茶室の戸を引いて、現実を忘れる至福の時間を体験しませんか?「和文化スヌーズレンルーム」で心と体をリフレッシュし、日常に新たなエネルギーを見つけましょう。
Experience the calming fusion of Japanese culture and sensory relaxation at our “Japanese Culture Snoezelen Room.” Designed with a tea room concept, this space offers a peaceful retreat from daily stress. Snoezelen stimulates various senses for relaxation and exploration, while incorporating elements of traditional Japanese tranquility. Adjust lighting and textures to your preference and immerse yourself in a serene environment. Open the tea room door and escape reality to rejuvenate both mind and body. Discover new energy and refresh your daily routine in our unique relaxation space.
Policy Project + B Lab
Policy Project + B Lab
MEMBER
合田涼帆(B Lab / 慶應義塾メディアデザイン研究科修士課程1年)
「Smiral-Robo」笑顔が寄付に
”Smiral-Robo” Smiles become donations
「笑顔」が「寄付」に
私たちは、生まれた時から言葉よりも先に笑顔でコミュニケーションを取ってきました。笑顔は喜びや楽しさを表現するだけでなく、相手の気持ちを尊重し”つながり合う力”を生み出します。 SmiralRoboは、みなさんの笑顔を検知し、周囲の人にも笑顔を連鎖させます。その連鎖はみなさんの周りに留まらず、笑顔が寄付となって遠く離れた人たちにも役立てられさらなる笑顔を生み出します。そんな私たちが持つつながり合う力をより大きなものにする取り組みです。 分断と対立が広がる現代だからこそ、年齢や性別、国籍、宗教、価値観、障がいの有無など様々な違いを尊重し、つながり合う事が大切です。そのためにも、私たち一人ひとりがまずは笑顔で相手の気持ちを受け止める事が大切だと考えます。
One Smile Foundation × ugo
「Smiral-Robo」笑顔が寄付に
”Smiral-Robo” Smiles become donations
「笑顔」が「寄付」に
私たちは、生まれた時から言葉よりも先に笑顔でコミュニケーションを取ってきました。笑顔は喜びや楽しさを表現するだけでなく、相手の気持ちを尊重し”つながり合う力”を生み出します。 SmiralRoboは、みなさんの笑顔を検知し、周囲の人にも笑顔を連鎖させます。その連鎖はみなさんの周りに留まらず、笑顔が寄付となって遠く離れた人たちにも役立てられさらなる笑顔を生み出します。そんな私たちが持つつながり合う力をより大きなものにする取り組みです。 分断と対立が広がる現代だからこそ、年齢や性別、国籍、宗教、価値観、障がいの有無など様々な違いを尊重し、つながり合う事が大切です。そのためにも、私たち一人ひとりがまずは笑顔で相手の気持ちを受け止める事が大切だと考えます。
One Smile Foundation × ugo
物語からいっしょに未来をつくる「Neu World」
Co-Creating the Future through Storytelling "Neu World"
考えるだけでロボットを自分の身体のように動かせたら…。
ムーンショット目標1金井プロジェクトInternet of Brains
Moonshot Goal 1 Kanai Project: Internet of Brains
物語からいっしょに未来をつくる「Neu World」
Co-Creating the Future through Storytelling "Neu World"
考えるだけでロボットを自分の身体のように動かせたら…。
What if we could move robots like our own body…?
ムーンショット目標1金井プロジェクトInternet of Brains
Moonshot Goal 1 Kanai Project: Internet of Brains
MEMBER
金井良太(ムーンショット目標 1金井プロジェクト Internet of Berainsプロジェクトマネージャー / 株式会社アラヤ代表取締役)
宮田龍(株式会社アラヤ サイエンスコミュニケーター)
お子さまを特性から理解する:LITALICO発達特性検査
Comprehending your child's characteristics : LITALICO Developmental Characteristics Assessment
お子さま一人ひとりには、多様な特性があります。
LITALICO発達特性検査では、特性について検査することで、特にお子さまの困りごとがなぜ起きているのか、その背景を知ることができます。また、それらの背景に合わせて、より良い関わり方や環境調整を提案します。検査を通じてお子さまの理解を深めてみませんか?
株式会社LITALICO
LITALICO Inc.
お子さまを特性から理解する:LITALICO発達特性検査
Comprehending your child's characteristics : LITALICO Developmental Characteristics Assessment
お子さま一人ひとりには、多様な特性があります。
LITALICO発達特性検査では、特性について検査することで、特にお子さまの困りごとがなぜ起きているのか、その背景を知ることができます。また、それらの背景に合わせて、より良い関わり方や環境調整を提案します。検査を通じてお子さまの理解を深めてみませんか?
Everyone has a variety of characteristics. A characteristic is a unique property, such as a way of receiving sensory stimuli or a habit of thinking, based on a person’s mental and physical conditions. The characteristics themselves can be either positive or negative, but they can lead to difficulties or strengths depending on the environment.
The LITALICO Developmental Characteristics Assessment measures these characteristics, which allows us to understand the background of difficulties. We will also suggest better ways to adjust the environment according to these backgrounds. Would you like to deepen your understanding of your child through the assessment?
株式会社LITALICO
LITALICO Inc.
MEMBER
榎本大貴(執行役員CQO/LITALICO研究所所長)
野田遥(株式会社LITALICO)
どうしたらみんなが協力できるんだろう
How can everyone cooperate together?
私たちの住み世界では、いろんな人たちがいろんな目的を持って行動しています。そうした個々の人たちが自分だけが得するように行動してしまうと、まわりまわって自分自身も損してしまうことがあります。他の多くの生物とは違い、人類は長い歴史の中でこの問題を解決してきたからこそ、これだけの発展できたとも考えられています。この展示では、来場者の皆さまに簡単な経済ゲームを体験してもらうことで、多様な人々がどうしたら協力し合える社会を築くことができるかを考えるきっかけを作ってもらいたいと思います。
明治学院大学実験経済学研究室+明治学院大学情報科学融合領域センター+科学研究費助成事業 学術変革領域研究(B) デジタル身体性経済学の創成(2023年度終了)
Meijigakuin Univ. Experimental Economics Lab, center for interdisciplinary informatics, Foundations of Digital Embodied Economics, Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (B) (ended in FY2023)
どうしたらみんなが協力できるんだろう
How can everyone cooperate together?
私たちの住み世界では、いろんな人たちがいろんな目的を持って行動しています。そうした個々の人たちが自分だけが得するように行動してしまうと、まわりまわって自分自身も損してしまうことがあります。他の多くの生物とは違い、人類は長い歴史の中でこの問題を解決してきたからこそ、これだけの発展できたとも考えられています。この展示では、来場者の皆さまに簡単な経済ゲームを体験してもらうことで、多様な人々がどうしたら協力し合える社会を築くことができるかを考えるきっかけを作ってもらいたいと思います。
In the world we live in, people act with various goals in mind. When individuals act solely for their own benefit, it can sometimes lead to their own loss in the long run. Unlike many other species, humanity has been able to achieve significant progress by solving this issue over its long history. In this exhibition, we hope to provide visitors with a simple economic game to spark thinking about how a diverse group of people can build a cooperative society.
明治学院大学実験経済学研究室+明治学院大学情報科学融合領域センター+科学研究費助成事業 学術変革領域研究(B) デジタル身体性経済学の創成(2023年度終了)
Meijigakuin Univ. Experimental Economics Lab, center for interdisciplinary informatics, Foundations of Digital Embodied Economics, Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (B) (ended in FY2023)
ニューロダイバーシティアワード(フロア番号5-1)
Neurodiversity Award
「ニューロダイバーシティアワード」では、革新的なアイデアや技術、商品、イベントを通じて、ニューロダイバーシティの新たな可能性を見出すことを目的としています。社会実装、研究開発、企画の3部門で、学生や研究者、企業などからの応募が寄せられました。本展示では、これらの応募者の中から選ばれた受賞者を紹介します。彼らの取り組みは、ニューロダイバーシティの普及と推進に貢献するものばかりです。各受賞者のプロジェクトが、どのように社会にインパクトを与えているのか、ぜひご覧ください。
ニューロダイバーシティアワード(フロア番号5-1)
Neurodiversity Award
「ニューロダイバーシティアワード」では、革新的なアイデアや技術、商品、イベントを通じて、ニューロダイバーシティの新たな可能性を見出すことを目的としています。社会実装、研究開発、企画の3部門で、学生や研究者、企業などからの応募が寄せられました。本展示では、これらの応募者の中から選ばれた受賞者を紹介します。彼らの取り組みは、ニューロダイバーシティの普及と推進に貢献するものばかりです。各受賞者のプロジェクトが、どのように社会にインパクトを与えているのか、ぜひご覧ください。
The Neurodiversity Award celebrates innovative ideas, technologies, products, and events that discover new possibilities for neurodiversity. Projects across three categories—Social Implementation, Research and Development, and Planning—were submitted by students, researchers, and companies. This exhibition showcases the winners, whose outstanding contributions advance the understanding and promotion of neurodiversity in society. Each displayed project demonstrates how neurodiversity can be harnessed to create a more inclusive world. Please explore the groundbreaking work of these award recipients and learn how they are making a difference.
「こまりごと翻訳」プロジェクトは、発達障害を持つ人々が日常生活で直面する困難や挑戦を、比喩や物語を用いてわかりやすく表現することを目指しています。発達障害を持つ人々の多くは、外見からはわからない困難を抱えており、その困難さは周囲の人々にとって理解しにくいものです。そのため、発達障害を持つ人々は誤解されやすく、適切な支援を受けることが難しい状況にあります。本プロジェクトでは、これらの困難を具体的かつ理解しやすい形で「翻訳」し伝えることで、周囲の人々が彼ら彼女らの状況を具体的に理解しやすくし、周囲の方々からの適切な支援や共感を得られるようにすることを目的としています。
「こまりごと翻訳」プロジェクトは、発達障害を持つ人々が日常生活で直面する困難や挑戦を、比喩や物語を用いてわかりやすく表現することを目指しています。発達障害を持つ人々の多くは、外見からはわからない困難を抱えており、その困難さは周囲の人々にとって理解しにくいものです。そのため、発達障害を持つ人々は誤解されやすく、適切な支援を受けることが難しい状況にあります。本プロジェクトでは、これらの困難を具体的かつ理解しやすい形で「翻訳」し伝えることで、周囲の人々が彼ら彼女らの状況を具体的に理解しやすくし、周囲の方々からの適切な支援や共感を得られるようにすることを目的としています。
カームダウンボックス体験
Calmdown Box
発達障害や精神疾患、感覚過敏のある方の中には、音や光などの環境刺激によって体調不良やパニック症状が出ることがあります。そのような時に体調を整え、落ち着いて休息できるカームダウン・クールダウンスペースのニーズが高まってきています。このスペースは、知的障害や発達障害、感覚過敏、パニック障害のある方にとっての休憩所や避難所として利用できます。日本ではJIS規格のピクトグラムも設定されており、今後普及が期待される施設です。イベント会場内には、2つのカームダウンスペースを用意しています。
株式会社クリスタルロード 感覚過敏研究所
kabin Lab. (Crystalroad Inc.)
カームダウンボックス体験
Calmdown Box
発達障害や精神疾患、感覚過敏のある方の中には、音や光などの環境刺激によって体調不良やパニック症状が出ることがあります。そのような時に体調を整え、落ち着いて休息できるカームダウン・クールダウンスペースのニーズが高まってきています。このスペースは、知的障害や発達障害、感覚過敏、パニック障害のある方にとっての休憩所や避難所として利用できます。日本ではJIS規格のピクトグラムも設定されており、今後普及が期待される施設です。イベント会場内には、2つのカームダウンスペースを用意しています。
Some people with developmental disabilities, mental disorders, or sensory hypersensitivity may experience physical discomfort or panic symptoms due to environmental stimuli such as sound and light. The need for calm-down and cool-down spaces where individuals can stabilize their condition and rest is increasing. These spaces can serve as rest areas or shelters for them. There are two calm-down spaces available within the event venue.
株式会社クリスタルロード 感覚過敏研究所
kabin Lab. (Crystalroad Inc.)
MEMBER
加藤路瑛(株式会社クリスタルロード代表、感覚過敏研究所所長)
環境マップ:あなたの発見をシェアしよう! (フロア番号5-13)
Environment Map: Let's share your discoveries!
会場内のどの場所があなたにどんな感情をもたらしたか、共有してみませんか?このブースでは、感情別に色分けされたシールと付箋を使って、あなたのイベント体験を可視化します。会場のどの部分がみんなにとって最も魅力的で、どの部分が改善の余地があるかを知る貴重な手がかりとして、あなたのフィードバックが役立ちます。おそらく感じ方は人それぞれです。あなたならではの感情をマッピングして、他のみんなと感想をシェアしませんか?
科学研究費助成事業 学術変革領域研究(B) デジタル身体性経済学の創成(2023年度終了)+ B Lab
Foundations of Digital Embodied Economics, Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (B)(ended in FY2023)+ B Lab
環境マップ:あなたの発見をシェアしよう! (フロア番号5-13)
Environment Map: Let's share your discoveries!
会場内のどの場所があなたにどんな感情をもたらしたか、共有してみませんか?このブースでは、感情別に色分けされたシールと付箋を使って、あなたのイベント体験を可視化します。会場のどの部分がみんなにとって最も魅力的で、どの部分が改善の余地があるかを知る貴重な手がかりとして、あなたのフィードバックが役立ちます。おそらく感じ方は人それぞれです。あなたならではの感情をマッピングして、他のみんなと感想をシェアしませんか?
Would you like to share which areas of the venue evoked certain emotions in you? At this booth, using color-coded stickers and notes based on emotions, you can visualize your event experience. Your feedback will serve as valuable insight to understand which parts of the venue are most appealing to everyone, and which might need some improvements. Emotions might vary from person to person. Why not map out your unique feelings and share your impressions with others?
科学研究費助成事業 学術変革領域研究(B) デジタル身体性経済学の創成(2023年度終了)+ B Lab
Foundations of Digital Embodied Economics, Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (B)(ended in FY2023)+ B Lab
身体マップ:感じるままのキモチを書こう!(フロア番号5-14)
Body Map: Let's write down feelings as they come!
私たちは鼻、耳、口、目、皮膚と多彩な感覚を持っており、それらの感覚から日々たくさんの刺激を受けとっています。このブースでは、身体マップにあなたの過去の体験や日々抱いている感情を書いて貼ってもらうことで、みんながそれぞれの身体で感じているキモチを可視化します。こんな感じ方をしている人がいるんだ!こう感じているのは私だけじゃなかったんだ!といろんな発見があるかもしれません。些細なことでも悩んでいることでもなんでも良いです!あなたの感じ方について教えてください。
科学研究費助成事業 学術変革領域研究(B) デジタル身体性経済学の創成(2023年度終了)+ B Lab
Foundations of Digital Embodied Economics, Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (B) (ended in FY2023)+ B Lab
身体マップ:感じるままのキモチを書こう!(フロア番号5-14)
Body Map: Let's write down feelings as they come!
私たちは鼻、耳、口、目、皮膚と多彩な感覚を持っており、それらの感覚から日々たくさんの刺激を受けとっています。このブースでは、身体マップにあなたの過去の体験や日々抱いている感情を書いて貼ってもらうことで、みんながそれぞれの身体で感じているキモチを可視化します。こんな感じ方をしている人がいるんだ!こう感じているのは私だけじゃなかったんだ!といろんな発見があるかもしれません。些細なことでも悩んでいることでもなんでも良いです!あなたの感じ方について教えてください。
We possess a diverse range of senses through our nose, ears, mouth, eyes, and skin, and we receive numerous stimuli from them daily. At this booth, by writing and attaching your past experiences and daily emotions to a body map, we aim to visualize the feelings everyone experiences through their bodies. You might discover others who feel the same way as you do or realize that you’re not alone in how you feel! Whether it’s something trivial or something you’re concerned about, everything counts. Please share with us how you feel.
科学研究費助成事業 学術変革領域研究(B) デジタル身体性経済学の創成(2023年度終了)+ B Lab
Foundations of Digital Embodied Economics, Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (B) (ended in FY2023)+ B Lab
イベント情報
第1回ニューロダイバーシティアワード 表彰式
ニューロダイバーシティに対する理解をさらに深めるとともに、社会における多様性と包摂性を推進するための新しい道を切り開くことを目指し、第1回ニューロダイバーシティアワードを開催します!表彰式は2024年10月12日(土) 14:30より東京都竹芝「ちょもろー」内にて開催します。審査員に下記のみなさをお迎えします。是非ご応募・ご参加ください!
詳細はこちら
審査員
石川 准
静岡県立大学名誉教授/有限会社エクストラ取締役社長/障害学会会長
伊藤 穰一
株式会社デジタルガレージ共同創業者取締役/学校法人千葉工業大学学長/Neurodiversity School in Tokyo 共同創立者
稲見 昌彦
東京大学総長特任補佐/先端科学技術研究センター副所長・教授
季里
アーティスト/女子美術大学アート・デザイン表現学科メディア表現領域教授)
黒川 清
東京大学・政策研究大学院大学名誉教授/東海大学特別栄誉教授/日本医療政策機構終身名誉チェアマン)
藤井 直敬
株式会社ハコスコ取締役CTO/医学博士・脳科学者/ブレインテックコンソーシアム代表理事)
パネルディスカッション「ニューロダイバーシティポテンシャルプロジェクト」
概要 日時 登壇者(敬称略)
お申し込みはこちら
ちょもろーアカデミア「超未来学!〜ニューロダイバーシティ視点から考える未来〜」
概要 日時 登壇者(敬称略)
お申し込みはこちら
B2J:BRAIN BODY JOCKEY PROJECT
概要 日時
昨年の様子はこちら
・当日の記録写真等について
スポンサー