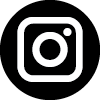発達障がい者が見ている世界をシミュレータで再現
一人ひとりに最適な支援の道を探る
2025年12月3日

B Labが主催する「ニューロダイバーシティプロジェクト」では、脳や神経の多様性を尊重し、誰もが自分らしく力を発揮できる社会の実現を目指しています。今回のニューロダイバーシティプロジェクト・インタビューシリーズでご紹介するのは、東京大学 ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任教授の長井 志江氏の取り組みです。自閉スペクトラム症の方が見ている視覚過敏の世界を再現するASD知覚体験シミュレータと多感覚情動推定システムを「みんなの脳世界2025」で紹介した長井 志江氏(▲写真1▲)に、本シミュレータの研究背景や具体的な内容、目指していることなどについて、B Lab所長の石戸 奈々子(▲写真2▲)がお聞きしました。


>> インタビュー動画も公開中!
自閉スペクトラム症の当事者が抱えている
一般にはわかりにくい困り事を見える化
石戸:「皆さんこんにちは。本日は東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構の長井 志江先生にお越しいただいています。長井先生は2024年度から『みんなの脳世界』に出展いただいており、2025年も出展していただきました。出展内容、そして研究内容についてお聞きしたいと思います」。
長井氏:「私たちの研究室では、ロボットやAIで使われているさまざまな工学的な技術を使って、発達障がい者の方が抱えている『一般には見えにくい困り事』を明らかにし、見える化をする技術を開発しています。今回のイベントでは2つのデモを用意しました。
まずは自閉スペクトラム症の方が見ている視覚過敏の世界を再現するヘッドマウントディスプレイ型のシミュレータです。こちらは、東京大学の先端科学技術研究センターで発達障がい当事者研究を推進されている熊谷 晋一郎先生、綾屋 紗月先生と共同で開発したシミュレータです。
自閉スペクトラム症の方の多くは視覚過敏など、さまざまな感覚に過敏性を持たれていることがわかっています。しかし、これまで、そうした主観的な知覚世界の体験というのは周囲の人たちが気づきにくいものでした。そうした中、綾屋先生の当事者研究の中から、自閉スペクトラム症の方が主観的に見ている世界が他の方の経験とは違っており、その違いが結果的に社会的な困難さを生み出しているのではないかという仮説が提案されました。そこで、私たちは工学的な技術を使うことによって、今まで自閉スペクトラム症の当事者の方々が主観的にしか体験できなかったものを多くの人も共有できる形にしようと考え、シミュレータを開発しました。
具体的には、ヘッドマウントディスプレイをかけていただくと、見ている世界のコントラストが変わったり、点のちらつきが見えたりします。しかも、周りで起きているさまざまな事象によって、例えば音の強さや光、人や物の動きなどの影響によって、リアルタイムに見え方の過敏性が変わってくることもヘッドマントディスプレイで体験していただけます。
そうした体験を通して、自閉スペクトラム症の方など発達障がいの方が見ている世界、聞こえている世界がいかに違うかを理解していただき、その違いを知ることによって、今までとは違った支援のあり方を考える機会になればと思っています。これが自閉スペクトラム症視覚体験シミュレータです。
もう一つは、マルチモーダルな信号からその人の心の状態、感情の状態を見える化する技術です。最近、ムーンショットプロジェクトで新たに開発に取り組んでいるものです。こちらのシミュレータには、その人の笑った表情や怒った表情、声のピッチや強弱などから情動を推定する技術が採用されています。
同時に、興味深いポイントとして、その人の生理信号から同じように情動を推定する技術も実装しています。生理信号とは、具体的には脳の活動である脳波、心拍、皮膚電気抵抗などで、これらの信号から、その人の心の状態を推定します。怒ったときや驚いたときは心拍がすごく高くなるなど変化が現れます。もちろん脳の活動の中にも、その人の心の状態が現れます。
その人の感情の状態がどのように変わっていくのか、また生理信号から推定される心の状態と、その人の『表に出てくる心の状態』、つまり顔の表情や声の調子などとの間にギャップがあるのかないのか、そういったことをシミュレータで体験できます。
どちらのシミュレータも、発達障がいの方が自分の心の状態を認識するのが難しいというところから開発をスタートしました。そういった人たちがなぜ心の状態を理解するのが難しいのか、もしくは表に出すのが難しいのかを技術を使って多くの人に体験していただくことで、さまざまな多様性を知っていただきたいと思っています」。
石戸:「非常に興味深い内容です。特に最初のシミュレータは、私自身も何度か体験させていただいたことがあります。まさに、私たちが見ている世界は、必ずしも他の人が見ている世界と同じではない、当たり前と思っていた感覚が、実は人それぞれ異なる、自分が見ている世界と他者が感じている世界が違うということに気づかされる体験となります。
ニューロダイバーシティプロジェクト『みんなの脳世界』のコーナーの1つに、『多彩な世界』をテーマにした展示があります。私たちが見て、聞いて、感じている世界と、他の誰かが見て、聞いて、感じている世界は同じではない。その違いを、体験を通じて理解してもらうことを目的とした展示です。2024年の長井先生の展示は、まさに『他者の視覚世界を体験できる』ものとして大きな反響を呼びました。
そのうえで、長井先生にぜひお伺いしたいことがあります。見える化によって発達障がいのある方々の特性を理解しやすくなる一方で、場合によっては『ラベリング』や『差別的な感情』を助長してしまうリスクもあるのではないでしょうか。実際の研究の中では、どのような反応が見られるのか。また、そうしたネガティブな反応や意見に直面された際には、どのように向き合い、対応されているのでしょうか」。
長井氏:「自閉症の方の視覚世界を再現するシミュレータについては、今までに一般の方々に向けて数多くのワークショップを開いてきました。その中で実際に体験された方からは『怖さを感じる』という声もありました。発達障がいの方々が抱えている難しさへの理解が進み、それならばこういうケアやサポートができるのではないかというポジティブなご意見がある一方で、怖さを感じてしまうというのも実際の声として上がってきています。
そうした中で私たちが気をつけているのは、世界の見え方が違うこと、見え方に違いがあるというのは、なにも発達障がいの方々に限らず、『全ての人たちに程度の差こそあれ、共通して起こっている』ことをきちんと丁寧に説明することです。しかも、ただ話すだけではなく、その背後にある科学的な根拠、例えば目のメカニズムや脳のメカニズムなどで見え方に違いがでることも説明しています。具体的には、コントラストを強く感じる、点がノイズとなって現れるといったことが脳の働きとしてどう起こっているのか、そういったメカニズムは自閉症の方に特別なものではなく、定型発達の方にも少なからず起こっているのです。
それがどのくらい強く長く起こるかによって、困り事になるか否かが変わってくるというのが私たちの仮説です。つまり、定型発達の方と発達障がいの方の体験は地続きである、まさにスペクトラムであるということです。起こっている現象そのものは空想上のものではなく、きちんと脳科学的にも説明できるメカニズムとして起こっていることを理解していただくことによって、恐怖心や怖さを感じることがないように心がけています」。
発達障がいの当事者の自己理解と
周囲の人たちの他者理解の両方を促す
石戸:「もともとニューロダイバーシティの概念は、発達障がい、特に自閉スペクトラム症の当事者による運動から始まりました。一方で、私たちは、すべての人に脳や神経の多様性があり、それらは互いに地続きのスペクトラムとして存在している、という考えのもとで活動を続けています。今後、一人ひとりの違いを『多様性』として捉える社会へとシフトしていくためには、どのような視点やアプローチが重要だとお考えでしょうか」。
長井氏:「私たちもこれまでにワークショップを通じて、学校の先生や医師、医療従事者、教育システムを作っている政府の方などとお話しをする機会がありました。そうした取り組みを通じて、今まで発達障がいと定型発達に二分されていたものが、実は両者の間は地続きであり、皆さんが同じ体験をしていて、その体験がどのくらい強く長く続いてしまうかによって困り事になるのか否かが変わってくるということを、丁寧にご説明していくしかないのではないかと感じています。
学校の先生方や発達障がいのお子さんをお持ちの親御さんなどは、視覚過敏など発達障がいの方が抱えている困り事について、たくさんの知識をお持ちです。ただ一方で、知識だけですとラベル付けで終わってしまい、どうしても二分化されてしまいます。シミュレータのような形で、自分の実体験として困りごとを経験することによって、ご自身でも例えば疲れているときには視覚のコントラストが強いと感じたり、体調が良くないときには聴覚過敏のように耳鳴りがしたりといった体験を少なからずされていることがわかると思います。
そういった皆さんの普段の体験への気づきを、シミュレータを通じて発見していただくことが、今まで知識だけで知っていたものとの大きな違いになると考えています」。
石戸:「目に見えない困りごとを可視化することで、その課題を抱える当事者自身の行動や意識が変化し、同時に支援する側の姿勢や関わり方にも変化が生まれるのではないかと感じます。
実際に、これまでどのような心や行動の変化が見られたのでしょうか。先ほど学校教育の現場での事例にも触れられていましたが、例えば合理的配慮や支援の仕組みが変化した具体的なケースなどがあれば、ぜひお聞かせください」。
長井氏:「私たちも驚きだったのは、当事者の方の中にも大きな変化があったことです。ある当事者の方は、実験に参加していただいた当時、目が疲れるとか視覚過敏によって頭が痛くなってしまうなど、悩み事や困り事を多く抱えていらっしゃいました。ところが、実験に参加した2~3年後に取材のためにもう一度大学に来ていただき、お話を伺う機会がありました。すると、実験への参加を通じて『自分の困りごとが何であるかがよくわかった』とおっしゃってくださいました。外出すると目が痛くなって疲れるという体験がある方でしたが、それはもしかしたら眩しいからかもしれない、眩しいのであればサングラスをかければ良いという対処方法にご自身で気づかれ、我々の実験に参加した後から日常生活でサングラスをかけられるようになったというのです。また、同じ方から、家の中の蛍光灯が辛いということで、LEDの調光タイプの照明にご自身で変えられたというお話も伺うことができました。
私たちとしては、実験に参加していただき、データを集めるというのが第一の目的だったのですが、実は、そういった過程を通して当事者の方がご自身の困り事への気づきを得ていた、理解を深めることができたのは大きな成果だったと思っています。
また、シミュレータの体験を通じて、周囲の変化も見られました。今まで学校で行っていた対処方法として、例えば聴覚過敏の方に対して音をなるべく出さないよう、教室の椅子にテニスボールのような柔らかいアタッチメントを付けるということが挙げられます。先生方にお話を伺うと、『なんとなく、そうすれば良いらしい』と言われていたことを、確信のないまま実践されていた部分も多かったようです。それを実際に視覚過敏や聴覚過敏がなぜ起きるのか、どういう形で起きているのかをシミュレータを通して実体験していただくことで、それまでなされていた取り組みについて確信を持って『これで良かったんだ』と思っていただけるようになりました。
さらには、そういった視覚過敏、聴覚過敏は1つのパターンではなく、場所によって見え方、聞こえ方はさまざまに変わってくること、個人によっても異なることを理解していただくことで、今までの対処方法だけではない、新しい個人に応じた対処方法にも気づくことができたと多くの方に言っていただきました」。
石戸:「私たちのニューロダイバーシティプロジェクトでも、自己理解と他者理解の両方が大切であることを強調しています。自分がなぜ苦しいのか、その原因を理解できるようになると、自分にとってより過ごしやすい環境を自ら整えたり、自分で合理的配慮を工夫したりできるようになる。これはとても意義のあることだと思います。また、特性は十人十色であり、感じている生きづらさも十人十色です。
科学的根拠に基づく理解が進むことで、『この発達特性にはこの支援が良い』と一律に捉えるのではなく、『こうした背景があるから、この人にはこの支援が適しているのではないか』と、より個々に寄り添ったサポートが可能になると感じています。実際に、先生方の間でもそのような新たな気づきが生まれているということですよね」。
長井氏:「そうですね。『Aさんにはこういう対応、Bさんにはこういう対応』など、その場その場での対応はもちろん重要ですが、それだけを繰り返していると新しい場面に遭遇したときにどう対応すれば良いのかがわからないという問題もありました。そこで、私たちの研究で注目しているのは『予測する脳』という考え方です。人の脳は周りから入ってくる感覚信号を受け取るだけではなく、積極的に信号を作り出し、予測しています。予測信号と入ってくる感覚信号との間を統合すること、そのバランスに何か違いがあるのではないかといった仮説を提案しています。そういったメカニズムに関する仮説があることで、例えば、これまでとは違った視覚特性を持った方に対して何かしら新しいアプローチを提案できる、もしくは、視覚過敏で知られていることを聴覚過敏や触覚過敏など他のモダリティにも適用できるようになるのではないかと考えています。メカニズムを考えていくことの重要な意味合いが、そこにあると思っています」。
発達障がいの当事者の方々が自身の感情や
状態を理解し表現することを支援する
石戸:「もう一つ、マルチモーダルな信号から個人の心や感情の状態を可視化する技術についてお伺いします。一般的に、自閉スペクトラム症の方々は、外に表れる感情表現と内面的な感情との間にギャップが大きいと指摘されています。この研究を通じて、そうした感情の表出や内面の理解に関して、新たに明らかになった知見や発見があれば教えていただけますか」。
長井氏:「解明されたと言うには実験結果が足りませんが、私たちは、さまざまな感覚信号が同時に変化し、それらが整合して統合されることで、感情としての喜びや悲しみといったものが表出すると考えています。心拍、体温、脳の活動、顔の表情などのさまざまな感覚信号が変化するのです。そして、これらの多感覚な信号がうまく整合しないところに、発達障がいの方やニューロダイバーシティの方の自分の感情認知の難しさがあるのではないかと考えています。
綾屋 紗月先生は当事者研究に関するご自身の著書の中で、『お腹が空いたことがわからない』ということをご報告されています。我々は、お腹が空くことはあまりに当たり前すぎて、『なぜわからないのかが、わからない』と思ってしまいます。しかし実際には、自分の身体のさまざまな低次の感覚信号が意識に上ってきて、それをまとめ上げることでどういう状態なのかを認識しています。綾屋先生曰く、低次信号の中には、例えば、手足が冷たく感じるとか身体がうまく動かない、あるいは胃が動いているといったお腹が空いたときに感じる信号も含まれます。そういったさまざまな異なる感覚信号がある中で、関連するものだけをうまくまとめ上げることで、初めて『お腹が空いた』という抽象的な状態が出てくるのです。
さらに、その抽象的な『お腹が空いた』という状態は必ずしもスムーズに立ち上がるわけではなく、うまく情報を取捨選択し、その上で周りの文脈と整合して初めて『お腹が空いた』という身体の状態が立ち上がってくるとされています。もし、そうした感覚信号をうまくまとめ上げられないようなことが自閉症の方の特徴であるとしたら、感情も同じようなプロセスを経ているのではないかと思ったのです。
我々が嬉しい、悲しいというのも、嬉しいセンサーや悲しいセンサーが身体にあるわけではありません。さまざまな身体の変化、感覚信号の変化に対して、我々は嬉しい、悲しいというラベルを付けるわけです。さまざまな感覚信号をまとめ上げて、嬉しい、悲しいと思うためのプロセスに何かしら難しさがあるとしたら、それが発達障がいの方が抱える感情認識の難しさに対応するのではないかと考えます。そうであれば、さまざまな感覚信号がそもそもどう立ち上がって、どのように反応しているのか、心拍の状態、脳波の状態、顔の表情の状態が同じように『嬉しい』という感情に整合したものになっているのか、矛盾は生じていないのか、それを調べていくことでニューロダイバーシティの方々の感情認識の難しさも定量的に示せるのではないかと考えています。その仮説の検証のためにシミュレータを開発しています」。
石戸:「当事者の方々は、自分自身の心の状態を正確に認識することが難しいという辛さを抱える一方で、周囲の人もその心の動きを理解しきれないために、コミュニケーションの齟齬が生じやすい面があると感じます。その意味で、長井先生の研究は、自己理解の促進と同時に、他者理解を深めるきっかけにもつながる重要な取り組みだと思います。この研究の先に見据えていらっしゃる、当事者の方々への支援、そして周囲の方々への支援の新しいあり方について、どのようにお考えでしょうか」。
長井氏:「社会的なコミュニケーションの難しさは、自己の中の自分の認識の難しさに起因しているのではないかという仮説を立てています。例えば、発達障がいの方は相手の人の気持ちを読み取ることが難しいというのはよく言われていますが、そもそも相手の気持ちを読み取る以前に、自分の気持ち、自分の感情の状態をうまく認識できていなければ、結果的に相手の感情の状態もそこにうまくグラウンドできないのではないかと考えます。
つまり、自分の心の中の状態をうまく表現する言葉を持たなければ、相手が何かしら感情の状態を示していても、そこに当てはめる言葉を持ちにくいということです。そこで自分の身体や感情の状態の認識をいかにサポートするかを考えて研究を進めています。それによって発達障がいの方の自分の理解が進めば、結果的にそれが他者とつながり、齟齬を解消することにもつながるであろうということです。社会的なコミュニケーションをどうするかよりも、まずは当事者の方が自分の理解を進めるためにさまざまな技術を使うことができないか、というのが私たちの研究のアプローチです」。
発達障がいの方々が自身の感情・状態について
何を表現するべきか・しないべきかを「自在に」判断
石戸:「自己理解を主な目的とする場合には、必ずしも当てはまらない指摘かもしれませんが、あえてお伺いします。新しい技術には常にリスクが伴い、それに対する懸念の声も少なくありません。心の状態を可視化する技術についても、人の理解を深める可能性がある一方で、プライバシーの問題や、偏見を助長するリスクといった指摘がなされることがあります。こうした技術の二面性について、先生はどのように整理し、どのような視点から研究に取り組まれているのでしょうか」。
長井氏:「すごく難しい問題です。私たちもプロジェクトメンバーの先生方と、プロジェクト立ち上げ当初から議論してきたことですが、例えば心の状態に関しては、私たちも全て見せたくはないわけです。表情では笑いながら、心の中で怒っている、それを隠したい、そういうときもあります。理想としては、こういう感情だが今は表に出すべきではないといったことまでを、さまざまな生理信号や身体信号、脳波などから読み取り、それらも全て含めてシステムで『何を表現するべきか、しないべきか』を決断できるようにするというのが我々の最終的なゴールです。
そのプロジェクトの名前が『自在ホンヤク機』です。ドラえもんの道具のような名前ですが、『自在ホンヤク機』と呼んでいるところが重要なポイントです。自律ホンヤク機や自動ホンヤク機ですと全てが表に出てしまいます。それが『自在』となると、使っているユーザーが自在に何を表現して、もしくは何を読み取るかをコントロールできるということです。それを目指して、私たちは研究を進めています。ただし、全ての生理信号や身体信号などを読み取ることはまだ難しいので、何を読み取り、何を表現するかといったことは、当事者の方々と議論をしながら進めていきたいと考えています」。
石戸:「非常に興味深い研究です。現在は発達障がいの方々を主な対象として研究を進められているかと思いますが、定型発達の人々においても、『なぜ今日はこんなにイライラするのだろう』『どうして自分は怒りっぽくなっているのだろう』といったように、自分の心の状態をうまくつかめないことがあります。もしそれが事前にわかり、感情表現をより自在にコントロールできるようになれば、人とのコミュニケーションのあり方も大きく変わるのではないでしょうか。自己理解を深めるツールは、多くの人にとって非常に有用であると同時に、場合によってはアイデンティティの形成にも大きな影響を及ぼす可能性があると思います。この点について、先生はどのようにお考えでしょうか」。
長井氏:「アイデンティティというとすごく大きなテーマになるかと思いますが、確かに生理信号やさまざまな身体的な指標を長期的に計測しますと、その人の体調の波も見て取ることができるようになります。別のプロジェクトで母子の心拍信号を3日間連続して計測し、そこから母親が持っている主観的なストレス度を推定できるかという研究を行いました。すると、お母さんの心拍信号からお母さんのストレス度を推定することはできるのですが、非常に興味深かったのは、子どもの心拍信号も含めるとお母さんのストレス度の推定率が高くなるということでした。
インタラクションの重要性、長期的に信号を取ることの重要性があると考えられます。1分間や3分間といった実験室環境での生理信号だけではなく、寝ている時やお風呂に入っている時も計測可能な特殊なセンサーを使って丸3日間の心拍信号を測りますと、心拍の日内変動が綺麗に出る方と出にくい方がいらっしゃいます。そのこととお母さんが主観的に思うストレス度に強い関係性があるのではないかと考えられます。
しかも、子ども側もお母さんと接していると、お母さんの身体情報からさまざまな影響を受け、それがお母さんにも反映されます。そういった形のソーシャルな関係性からも、さまざまなことが見えてくると考えています」。
石戸:「自分の生体情報だけでなく、他者との関係性の中から見えてくる自分の姿もあるということですね。たしかに、職場での人間関係や友人とのやり取りのなかで、会話相手の心理状態や反応が自分の心に与える影響はとても大きいと感じます。そうした相互作用や関係性のダイナミクスも、今後さらに解明されていきそうですね」。
長井氏:「今までは、一人の人の生理信号や身体信号からその人の心的状態を読み取ることが多かったのですが、その場にいらっしゃる全ての人の生理信号がさまざまに影響し合う点にも着目するのは、非常に興味深いポイントかと思います」。
石戸:「私たちもニューロダイバーシティの活動を通じて、さまざまな障がいはしばしば『個人の問題』として語られがちですが、実際には環境との相互作用によって形成される側面が大きいということを伝えています。長井先生のお話を伺い、人間関係を含めた環境との相互作用が、私たちの感じ方や生きづらさに大きく影響していることを、改めて実感いたしました」。
研究・開発における重要なポイントは
当事者の方がその技術を使った時に嬉しいと思えるかどうか
石戸:「視点を変えますが、長井先生の研究は当事者の方々とともに進められていることが大きな特徴です。当事者の方々とともに研究を進める上で大切にしている、留意している点があれば教えていただけますでしょうか」。
長井氏:「当事者研究の先生方とは20年近く共同研究をさせていただいています。最初に重要なポイントだと思ったのは、発達障がいやニューロダイバーシティの方と実際に接してみると、周囲から『こういうことが苦手です』と一般的に言われていることと、当事者本人が『自分はこれが苦手です』と思っていることに大きなギャップがあるということでした。
例えば、教科書上では視覚過敏は以前から知られているのですが、視覚過敏を持つことでコミュニケーションの齟齬にどう影響するのかは、なかなか想像がつきにくいと思います。実際に私たちもシミュレータを作り、自分たちでもかけてみると、人がたくさんいるだけでノイズが生じて頭痛が起きたり、見え方が変わることで、必然的に自分の視線方向も変わることがわかりました。また、発達障がいの方とコミュニケーションをしているとアイコンタクトをなかなか取りにくいということが言われますが、目の部分がそもそもクリアに見えなかったり、目の動き以上に身体の動きの方が情報量を持っていることなど、実際に当事者の視点に立つことによって体感する困り事や難しさと、当事者ではなく外側から見ているときの困り事や難しさとは大きく違うということに気づかされました。
それ以降、こういったシステムを作ってニューロダイバーシティのサポートに使おうと考える際には、あくまでも『当事者の方がそれを使った時に嬉しいと思えるかどうか』、『当事者の方がそれを欲しいと思うかどうか』にポイントを置いて、開発を進めるようにしています。従来は、第三者が見て、例えば『定型の方と振る舞いが違うから同じように振る舞えるように支援をしましょう』、『ロボットを使いましょう』という取り組みが多かったのですが、そういった技術は必ずしも当事者の方が望んでいる技術であるとは限りません。もちろん、中にはそれが嬉しいと思ってくださる方もいますが、必ずしもそうではないのです。
ですので、私たちの技術開発のスターティングポイントは、あくまでも当事者の方が『こういう技術があったら良いよね』という声に始まります。そうした声を私たちの共同研究者の熊谷先生、綾屋先生がデータとして集めていらっしゃって、そういった当事者の声の中から、実際にそれが皆さんに欲しいと思われている技術をいかに作っていくかを目指して研究を進めています」。
石戸:「先生の研究は一貫して、『見えない世界を可視化する』『見えることによって理解を促していく』ところに焦点を当てていると思います。これから先、長井先生が『ここをさらに可視化することで、当事者の方々がより生きやすくなる』とお考えの、新たにチャレンジしていきたい可視化の領域はありますか」。
長井氏:「今、取り組んでいる情動もとても難しいと感じています。最初に取り組んだ視覚過敏は、どちらかというと、データに落としやすい、数値に落としやすい対象でした。実際にシミュレータを作った時も、当事者の方から『ああ、まさにこんな形で見てましたよ』というフィードバックをいただくことも多くありました。それに対して、喜びや悲しみなど、感情の状態の読み取りについては、そもそもどの身体のどの信号が感情に関わっているかもよくわかっていません。最近ではフリーのソフトウェアで顔の表情からその人の情動を読むという技術が数多く出ていますが、まだまだ実用化レベルには至っていません。日常生活のコミュニケーションでは、教科書に載っているような明らかな喜びの表情、悲しみの表情は表れないのです。ミクロな変化の中からどうやってその人の感情を読み取るのか、さらには、さまざまな感覚信号が統合されて初めて出てくる、より高次の認知機能と呼ばれる感情が、脳のどのようなプロセスを経て現れるのかについては、これから何十年もの実験と研究が必要な分野だと思っています」。
石戸:「壮大なチャレンジに取り組まれているのですね。心をどう捉えるかという問いは、これまで人類が幾度となく挑み続けてきたテーマであり、その難しさもよく知られています。AIの進展によって、この領域の解明がさらに加速していくことを大いに期待しています。そして、『見える化』によって人の違いが可視化されることは、どのように社会的包摂へとつながっていくのか、改めて先生のお考えをお聞かせいただけますでしょうか」。
長井氏:「発達障がいは、見えない障がい、もしくは見えにくい障がいと言われてきたのが、インクルーシブな社会を作る上での大きな難しさであったのではないかと思います。社会としては身体障がいと同じように、発達障がいの方にもきちんとサポートを整えたいというモチベーションや取り組みがあった中で、当事者の方が何に困っているのかが本当の意味でわかっていない、当事者にもわかっていないというところが重要なポイントでした。
私たちの技術を通して、それが、なぜ起こっているのか、そのメカニズムを含めて見える化していくという活動を進めたいと考えています。見えない障がいと言われていたものがきちんと見える形になり、かつ、それがなぜ起こっているのか、単純な事例紹介ではなく、それをきちんと繋ぐような脳のメカニズム、もしくは、診断のメカニズムにも言及していくことができれば、今までとは違ったインクルーシブ社会の設計方法を新しく提案できるのではないかと期待しています」。
石戸:「長井先生が思い描かれている、理想的なインクルーシブ社会とは、どのようなイメージなのでしょうか。非常に抽象的で言語化の難しいテーマかもしれませんが、ぜひお聞かせください。また、その理想の実現に向けて、現在の社会が抱えている課題や、乗り越えるべき壁はどのような点にあるとお考えでしょうか」。
長井氏:「理想的なインクルーシブ社会というのは、皆さんが画一的な、同じような行動や振る舞いをすることでインクルーシブとするのではなく、皆さんの多様性をきちんとお互いに理解し合って、多様性を生かした、尊重した社会を作っていくことが重要だと考えています。
教育現場の先生方とお話しをすると、先生方もすごくお忙しいですし、例えば10人の発達障がいの方がいても、10人それぞれに対応するのは難しいということも伺います。そういった現場の先生方の状況を理解した上で、先生方が多様性を持ったお子さんに適切に対応できるような仕組みを、こういったシステムの開発を通してサポートできたらと考えています。特に、今まで何をしてあげたら良いかがわからなく、どうしてもそこに必要以上に時間がかかってしまうとの課題に対して、当事者が何に困っているのかをシステムを通して伝えていくことが、現場の先生方にとっての支えになると思っています」。
石戸:「最後に一言、『みんなの脳世界』へ期待する一言をいただいてお終いにしたいと思います」。
長井氏:「『みんなの脳世界』のイベントでは、たくさんの研究機関や、さまざまな取り組みの中から出てきた、ニューロダイバーシティを考えるための新しいシステム開発が提案されています。私自身も勉強になる部分がたくさんあります。このイベントを通じて、ニューロダイバーシティについて今まで知らなかったことを体験することによって、より身近な問題として皆さんに考えていただくきっかけになれば良いと思っています」。